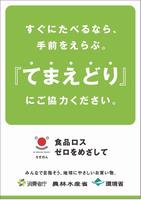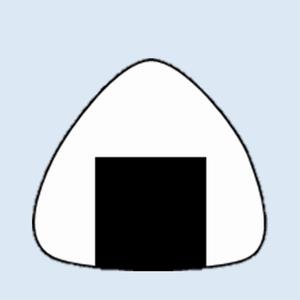食品ロスを減らしましょう
食品ロスとは?
食品ロスとは、まだ食べられるにも関わらず捨てられてしまう食品のことです。
日本全体の食品ロスは令和5年度推計で年間約464万トンに及びます(出典:農林水産省・環境省)。
家庭で発生する食品ロスは、大きく3つに分類されます。
「食べ残し」 食卓にのぼった食品で、食べ切られずに廃棄されたもの
「直接廃棄」 賞味期限切れ等により使用・提供されず、手つかずのまま廃棄されたもの
「過剰除去」 厚くむき過ぎた野菜の皮など、不可食部分を除去する際に過剰に除去された可食部分
なぜ食品ロスを減らす必要があるの?
環境への負荷
食品ロスで発生した生ごみが燃やせるごみとして出されると、近文清掃工場で焼却処理されます。
生ごみは水分を多く含むため、焼却の際に多くのエネルギーが必要となり、環境への負荷が懸念されます。
食糧問題
日本の食糧自給率(カロリーベース)は38%(令和5年度 農林水産省)であり、食糧の多くを輸入に頼っています。その一方で、日本の食品ロス量は年間約464万トンと推計されており、これは世界の食糧援助量の約1.3倍に相当します。
ごみ処理経費
令和6年度に旭川市がごみを収集・処理するためにかかった経費は約43.8億円です。
ごみ処理経費を節減するためにも、食品ロスの削減を始めとしたごみの減量化に取り組みましょう。
家庭でできる食品ロスを減らす取組
買いすぎない
- 食材を買う前に冷蔵庫や食品を保管している棚を確認する。
- メモを作るなど計画的に必要な分を購入して食べきるようにする。
- 消費期限や賞味期限が近いものや傷みやすいものなど、残っている食材から使う。
作り過ぎない
- 体調や家族の予定などを考えて、食べきれる分を調理する。
- 冷蔵庫の収納方法を工夫し、食材の使い忘れによる廃棄を防ぐ。
- 作り過ぎたり残った料理はリメイクやアレンジして食べきる。
※旭川市では食品ロス削減レシピを公開していますので、御活用ください。
上手に保存する
- すぐに食べない食材は冷凍するなど保存方法を工夫する。
- 一度に食べきれない野菜などは冷凍や乾燥の下処理をして小分け保存する。
外食の時は
- 小盛りメニューやハーフサイズを活用して食べきれる量を注文する。
- 料理を残してしまった場合はお店と相談して持ち帰ることを検討する。
※食品ロス削減に取り組んでいる「あさひかわ食品ロス削減協力店」はこちらです。お店選びの参考にしてください。
買い物するときはてまえどり
- すぐに使う・食べるなど衛生上支障のない範囲で、商品棚の手前側にある販売期限の迫った商品や見切り品を選ぶ。
フードドライブを活用する
- お土産やお中元・お歳暮などで手つかずのままになっている食品がある場合は、フードドライブに協力する。
※フードドライブに提供された食品はフードバンク団体を通じて、食料を必要とする方に提供されます。
消費期限と賞味期限を正しく理解する
消費期限
未開封の状態で、表示された方法を守って保存した場合に安全に食べられる期限のこと。この期限が過ぎたら食べない方がよい食品に表示されていますので、期限内に食べましょう。また、一度開封したら期限に関わらず早く食べきりましょう。
賞味期限
未開封の状態で、表示された方法を守って保存した場合においしく食べられる期限のこと。この期限が過ぎてもすぐに食べられなくなるわけではありません。なお、一度開封したら期限に関わらず早く食べきりましょう。
賞味期限が過ぎてもすぐに捨てるのではなく、自分でまだ食べられるか判断することも大切です。保存や調理を上手に行い、食品の廃棄を減らしましょう。
旭川市では食品ロス削減と同時に3Rを推進しています
詳しくは3R(リデュース・リユース・リサイクル)の推進のページを御覧ください。