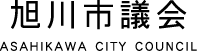あさひかわ市議会だより第118号-2
一般質問
一般質問は、定例会で議案に関係なく、市政の諸問題や将来の見通しなどについて市の考えを聞くものです。
第4回定例会では、12月10日、11日及び12日の3日間にわたり13人の議員が質問しました。その中から主な質問と答弁をお知らせします。
今定例会の質問者(発言順)
- (1)選挙の電子化
- (2)ユネスコ創造都市ネットワークサブネットワーク会議の成果と将来の展望
- (3)本市の雨水対策
- (4)災害対策
- (5)103万円の壁等における影響
- (6)花咲スポーツ公園内のプール整備
- (7)旭川市民文化会館の利用
- (8)旭川のナイトタイムエコノミー*の活性化
- (9)こども誰でも通園制度
- (10)「子どもに優しい」まちづくりの実現に向けた取組
- (11)学校の適正配置
- (12)地域の移動を守る
- (13)建設工事請負業者の格付
今定例会の質問者(発言順)
(1) 沼 﨑 雅 之(自民党・市民会議)
・第28回全国菓子大博覧会・北海道あさひかわ菓子博2025について
・市内公園におけるトイレ整備について
・5歳児健診について
・選挙の電子化について
(2) えびな 安 信(自民党・市民会議)
・市立病院の経営状況と今後の取組について
・Jリーグキャンプ誘致について
・ユネスコ創造都市ネットワークサブネットワーク会議の成果と将来の展望について
(3) 笠 井 まなみ(自民党・市民会議)
・本市におけるインクルーシブ遊具の導入について
・障がい児の子育てとその家族支援について
・本市の雨水対策について
(4) 髙 橋 紀 博(民主・市民連合)
・災害対策について
・雪対策について
・新庁舎における職員福利厚生について
(5) 金 谷 美奈子(無党派G)
・103万円の壁等における影響について
・熊駆除出動要請の原則拒否について
・旭川市のハラスメント対策について
・旭川市の宿泊税について
・中央中学校(学生対策便廃止)の課題について
・新文化会館における和室(茶室)の必要性について
・マイナンバーカードの健康保険証利用等について
(6) 佐 藤 さだお(自民党・市民会議)
・戦没者に対する慰霊について
・花咲スポーツ公園内のプール整備について
・自衛隊機の本市上空通過における騒音について
・今津市政の今年の主な成果と来年の抱負について
(7) 塩 尻 英 明(旭川市民連合)
・旭川市民文化会館の利用について
・水道管の漏水対応について
・旭川市放課後児童クラブの運営について
(8) 駒 木 おさみ(公明党)
・小中学校における消費者教育及び金融教育について
・買物公園エリアの社会実験について
・高齢や障害の有無にかかわらず楽しめるユニバーサルツーリズムについて
・旭川のナイトタイムエコノミーの活性化について
(9) 安 田 佳 正(無所属)
・カスタマーハラスメントについて
・除雪について
・休日等歯科対策について
・子どもの自転車用ヘルメットの着用について
・こども誰でも通園制度について
(10) 横 山 啓 一(無所属)
・「いじめ重大事態」調査の総括について
・「子どもに優しい」まちづくりの実現に向けた取組について
(11) 中 村 みなこ(日本共産党)
・物価高騰対策・福祉灯油の実施について
・学校の適正配置について
(12) 江 川 あ や(民主・市民連合)
・地域除雪の在り方について
・自分らしく働くこと~会計年度任用職員の待遇改善について
・地域の移動を守る
・ブックスタート事業について~子どもの体験格差を見据えて
(13) 能登谷 繁 (日本共産党)
・マイナ保険証の混乱と現行保険証の存続について
・バス減便と地域公共交通の課題について
・建設工事請負業者の格付について
・市長の政治姿勢について
(1)選挙の電子化
質問
大阪府四條畷市の市長選挙及び市議会議員補欠選挙において、国内では8年ぶりとなる電子投票が実施されます。本市における電子投票導入に向けた市の見解を聞かせてください。
回答
電子投票導入については、開票作業における人員削減と開票時間の大幅な短縮が見込まれるほか、候補者名の書き間違い等による無効票の減少、また、代理投票の際の秘密投票が可能となるなどが大きなメリットとして期待されます。
一方で、選挙という特性上、システムの不具合などにより投票に影響が生じるリスクの解消が必要であること、また、投票結果がシステムで集計となる際の公正性・信頼性の確保、さらに、導入費用等も課題として考えられますことから、導入に当たっては国の動向やほかの自治体の状況などを注視していきたいと考えています。【選挙管理委員会事務局長】
このページのトップへ
(2)ユネスコ創造都市ネットワークサブネットワーク会議の成果と将来の展望
質問
10月に本市で開催されたユネスコ創造都市ネットワークサブネットワーク会議では、21か国23都市からゲストを迎え、創造都市としての課題共有や事例の発表など熱心なディスカッションが行われ、日本文化体験やミニまちなかキャンパスなど様々な取組が行われたほか、デザインの力で持続可能で幸せな未来をつくるために必要な自然と社会の調和を図ることなど、5項目からなるデザイン都市旭川宣言が採択されました。この成果を本市の未来にどのように活かしていくのか、市長の考えを聞かせてください。
回答
これまで本市にとって経験のない規模の国際会議で、世界各国の関係者に本市のデザインの魅力を余すことなくお伝えし、参加者から高い評価を得て市民のシビックプライド*の向上にもつながったと認識しています。今後は、デザイン都市旭川宣言に基づき、創造都市とのネットワークを活かしながら、デザインの力はもちろん、本市の魅力と価値を世界に向けてしっかりとPRするなど、魅力的で持続可能なまちづくりを市民の皆様とともに進めていきます。【市長】
*シビックプライド:市民が都市に対してもつ自負と愛着
このページのトップへ
(3)本市の雨水対策
質問
気候変動の影響により、全国的に線状降水帯が発生し、これまで経験したことのないような豪雨災害が各地で発生しています。国では、流域治水の理念を掲げ、地域のあらゆるリソースを総動員して一体となった対策に取り組んでいます。本市においても、この考え方に基づき、雨水幹線の整備が急務ですが、整備率は低い状況にあり、整備進捗を図っていかなければならないとのことで、今後の整備に向けた水道局の見解を伺います。
回答
近年は、本市におきましても局地的短時間豪雨が増加傾向にありますが、道路冠水など被害発生から解消までが極めて短時間であるため、浸水被害の状況把握や降雨の実態を時系列的に把握することが困難な場面も増加しております。
このため、現在作成を進めております内水浸水想定区域図に基づき、客観的な浸水リスクを把握した上で整備箇所を選定するとともに、優先度を設定しながら効率的かつ効果的な整備推進を図っていきたいと考えています。
また、国や北海道など関係機関との連携をより一層密に、国土強じん化や流域治水の取組など、雨水浸水対策に関する最新の動向を把握し、あらゆる機会を捉えながら要望活動を行うことで必要な財源の確保に努め、雨水幹線整備が進捗するよう取り組んでいきます。【上下水道部長】
このページのトップへ
(4)災害対策
質問
災害発生時、単独で避難することが困難な人について、その中でも、障がいを持っている方が避難をしなければならなくなった場合、避難支援についてどのような形になっているのか、また、聴覚障がい者への避難所での支援についてどのようになっているのか、市の見解をお聞かせください。
回答
避難情報を発令した場合、まず発令された地区の視覚障がい者や同居する家族に対し、開設した避難所の所在地などの情報をしっかりとお知らせすることが重要となるので、福祉保険部と連携を図り、避難行動要支援者名簿等を活用しながら確実な情報の伝達をすることとしています。
同居する家族等との避難が困難な方については、ハイヤー協会との協定を活用して避難支援を行うほか、緊急事態が発生した際には、消防車両を出動させるなどの対応を行います。
また、聴覚障がい者につきましては、一時的には最寄りの指定避難所に避難していただくこととなりますが、長期間の避難生活が予想される場合には、避難生活に特別な配慮が必要な方に避難生活を送っていただくための福祉避難所を開設いたします。その際、旭川障害者連絡協議会、旭川市社会福祉協議会等との防災協定を活用して、手話通訳者を派遣してもらうなど、関係機関との連絡を図りながら、障がい者が安心して生活できる避難所運営に努めていきます。【防災安全部長】
このページのトップへ
(5)103万円の壁等における影響
質問
国において現在議論されている所得税の年収の壁について、178万円へ引き上げるとの話も出ている中、本市における税収及び財政面にはどの程度影響がありますか。また同時に、社会保険料についても、いわゆる106万円の壁、130万円の壁の撤廃論も出ていますが、それが本市にどのような影響を及ぼすと考えているのか、併せてお聞かせください。
回答
個人市民税の基礎控除額が所得税と同様に75万円に引き上げられたとした場合、令和6年度課税ベースでは個人市民税で約53億円の減収になるものと試算しており、地方交付税を考慮しても、本市の財政への実質的な影響額は約13億円程度になるものと試算しておりますが、103万円の壁の見直しにつきましては、国から規模や時期等が示されていないため、現時点では本市の令和7年度の市税予算への影響はないものと認識しています。
また、いわゆる106万円の壁、130万円の壁の社会保険料の議論につきましては、壁を越えると社会保険料の支払いで手取りが減少することでの働き控えに対する議論であると認識しておりますが、中小企業の中には労働者の社会保険料の新たな負担を伴うことも想定されますことから、市内におきましても、こうした負担増が中小企業者の経営面に影響を与えるおそれはあるものと認識しています。【税務部長・総合政策部長】
このページのトップへ
(6)花咲スポーツ公園内のプール整備
質問
先日、北見市にある北見市民温水プールを視察しましたが、本市には現在水泳連盟公認のプールがありません。道北地区を代表する本市に公認の屋内プールがないために、全道規模の大会が開催されていない状況を速やかに改善すべきだと思います。
また、北見市民温水プールは利用者全体の20%から25%が高齢者であり、午前10時の開館時には行列ができるほど高齢者の皆さんが温水プールでの運動を楽しんで健康増進に役立てているとのことでした。花咲スポーツ公園内に公認の屋内プールを整備して、水泳競技の大会開催だけでなく、北見市民温水プールのように、全世代の市民の皆さんが年間を通じて体力錬成や健康の維持増進ができる施設にしていただきたいと思いますが、今後のプール整備についての見解をお聞かせください。
回答
本年3月に策定しました花咲スポーツ公園再整備基本構想の中で、プールは既存機能の見直し検討が必要な施設として位置付けており、令和7年度には花咲スポーツ公園再整備基本計画を策定する予定です。
スポーツ環境の整備や競技環境の向上を図るとともに、スポーツに取り組むことは生涯を通じて健康増進や生きがいにつながることから、高齢者はもとより、誰もが気軽にスポーツに触れることのできる環境づくりを進めることが重要であると考えており、この計画の中で、公認プール設置の可否も含め、施設の利用状況や市民ニーズ、施設の規模や配置のバランスなどについて検討を行い、施設整備の方向性を整理していきます。【観光スポーツ部長】
このページのトップへ
(7)旭川市民文化会館の利用
質問
旭川市民文化会館の利用申請について、コロナ禍を契機として、令和3年5月からは一斉受付が採用されました。希望日を自由に指定できることや、申請手続を行うときだけ文化会館に行けばよいなどのメリットがありますが、メリットがありますが、その一方で、それまで行われていた集団受付では、団体が一堂に会することにより、抽選を行う前に各団体の使用希望日を全体で共有できることで、出席者同士の話合いによる調整が行え、円滑な利用につながっていたと思います。現在の管理運営や受付方法などについての改善の予定はありますか。また、文化会館の新設が予定されており、管理運営等の見直しを行う良いタイミングと思いますが見解を伺います。
回答
市民文化会館の使用に際しては多くの申請書類を記入しなければならず、使用者の負担となっている面があります。そのため、来年度から、使用者の住所や氏名など重複する箇所の記載を省略できるようにするなど、改善に向けた準備を進めているところです。なお、一斉受付の運用など、現状、特に要望等は寄せられていない事項についても、使用者の意見をお聞きしながら、よりよい施設運営に努めていきます。
市民文化会館の建て替えによる整備については、本年3月に施設の基本理念や基本的な役割、機能などを示した旭川市民文化会館整備基本構想を策定し、4月からは文化ホール整備担当を設け、具体的な施設の機能や規模、立地などを整理した基本計画の策定に向けた検討を進めているところです。現在は一部の業務を委託し、職員が施設管理等を行っておりますが、運営に当たっては専門的な知識が必要なことや、施設の利用率や使用者の利便性の向上にも関わるので、今後、いずれかの段階において検討する必要があると考えております。【社会教育部長】
このページのトップへ
(8)旭川のナイトタイムエコノミー*の活性化
質問
アシアナ航空路線の定期便が再就航し、今後ますます外国人観光客は増加する傾向にあります。旭川への旅行を満喫できる一つの方法として、スナックホッピングツアーが事業化できればよいと考えています。ナイトタイムエコノミーの基点として、さんろく街を中心に地域全体に経済効果を波及させられますし、スナック離れしている日本人客を呼び寄せることも期待できますが、本市としてはどのような課題意識・見解をお持ちか伺います。
回答
観光産業は裾野が広く、観光により市内の飲食業が活性化することで、その効果は、様々、波及するものと考えています。また、旅先での出会いが再度お越しいただく強い動機にもなりますことから、おもてなしの心は大変重要であると考えています。
スナックホッピングツアー実証事業は外国の方々に好評だった一方、外国人通訳が必要となり、常時対応が難しいことから、旅行会社等との連携が今後の課題です。今後は旭川観光コンベンション協会や大雪カムイミンタラDMOと連携し、観光客の受入れ体制を強化するとともに、ナイトタイムエコノミーの実施主体となる民間事業者や団体が活用可能な制度について、情報収集を行うなど、円滑に事業が実施できるよう支援をしていきたいと考えています。【観光スポーツ部長】
*ナイトタイムエコノミー:日没から日の出までの夜間に経済活動を行うことで、地域の魅力や文化を発信し、消費拡大につなげる考え方
このページのトップへ
(9)こども誰でも通園制度
質問
全ての子育て家庭に対して多様な働き方やライフスタイルに関わらない形での支援を強化するため、現行の幼児教育・保育給付に加え、0歳6か月から満3歳未満の子どもが、1か月一定時間までの利用可能枠の中で、親の就労要件を問わず、時間単位で柔軟に利用できる新たな通園給付として、今年度からこども誰でも通園制度が施行されています。月10時間の短い時間で預けられることが子育ての支援になるかどうか疑問ですが、市の考えを伺います。
回答
国の有識者会議の議論の中でも、利用者や実施施設からは月10時間の拡大を求める意見がある一方で、全国どこでも、一定量の支援を限られた施設や職員、財源の中で多くの児童に提供できるようにするためには、月10時間の枠で事業を開始するのが望ましいという意見もあります。
また、本市で実際に利用した保護者の反応につきましても、更に長い時間の実施を希望しながらも、現在の1回2時間から4時間程度の利用だとしても、子どもが通園によりほかの子どもや保育士と関わる時間ができたことや、保護者自身の時間の確保ができたことに喜びの声も寄せられています。【子育て支援部長】
このページのトップへ
(10)「子どもに優しい」まちづくりの実現に向けた取組
質問
教育予算の拡充、そして教職員の負担軽減について、人口減少が続き、財政状況もますます厳しさを増していくことは理解していますが、未来の旭川に対する最大の投資が、教育予算ではないかと思います。他の自治体では生き残りをかけて子ども予算を増やしている中、市財政の大胆な見直しが必要ではないかと思います。
そろそろ旭川もそういった転換を図らなければ、取り返しのつかない事態になるのではないか、そういう危機感を持つべきではないかと思いますが、教育長と市長の教育予算に関わる見解を伺います。
回答
人口減少や少子高齢化、ICTの著しい進展など、社会状況を背景として、教育を取り巻く環境が目まぐるしく変化する中、教育的ニーズも多様化しており、本市においても、GIGAスクール構想への対応や学校施設の耐震化、普通教室へのエアコン設置など、多額の予算措置を必要とする事業を進めてきているところです。日々の教育活動においては、教職員等の熱意や様々な工夫、保護者の皆さんの協力などもまた大きな支えであると認識をしています。
校教育は、未来の旭川を担う子どもたちを育む上で大変重要なものです。今後も、施策の優先度、そして緊急度なども考慮しながら、市長部局と連携して必要な予算の確保に努めたいと考えています。【教育長】
学校教育関係の予算は、本市の子どもたちが心身ともにたくましく成長する上で重要な役割を担っており、本市の将来を支える上で欠かせないものと認識しています。
本市では、厳しい財政状況の中、これまで、文部科学省などに要望し、国費を獲得しながら、いじめ防止対策をはじめ、小中学校の冷房設備整備や学校施設の増改築、給排水設備の改修などを進めており、さらには、特別支援教育の充実や給食費の値上げへの対応なども行ってきました。今後も、財政支援を国に要望するなど、財源の獲得に取り組みながら、必要な予算の確保に努めてまいります。【市長】
このページのトップへ
(11)学校の適正配置
質問
平成27年度に策定された、旭川市立小・中学校適正配置計画については、今年度で第2期計画が終わり、第3期改定案の策定に向けて動いているところだと思いますが、統廃合ありきで話が進んでいるように思います。
文科省からは「誰一人取り残さない令和の日本型教育の推進」が声高にうたわれています。その中には少人数によるきめ細かな指導体制の整備を進める「個に応じた指導」の充実とあります。統廃合を進めようとしている学校は、これらが実施できている学校です。ICTを活用した遠隔合同授業も可能となっていますし、今でも隣の学校と一緒に行事等を行っているところもあります。
今後は統廃合を進めるだけでなく、いかに小規模・過小規模学校を残していくか、ここも同時に考えていくようにすべきではないでしょうか。教育長にお伺いします。
回答
本市においては、子どもたちに未来を生き抜く力を育むために、個別最適な学びと協同的な学びの一体的な充実に取り組んでいるところです。児童生徒数が少ないことにより、教員の目が行き届き、きめ細かな指導がしやすくなる一方で、学級の人数が極端に少なくなった場合は、教員などの配置が少なくなるほか、グループでの対話の機会が減少し、集団学習への制約のほか、人間関係も限定され、社会性を養う面でも懸念があると考えています。
また、今の適正配置計画においても地域拠点校を存置する取り扱いをしているところですが、本市の児童生徒数は、昭和57年度以降減少し続けており、今年度はピーク時の4割の20,301人となっており、20年後にはさらに減少し、11,860人になると推計しております。子どもたちにとってより良い教育環境を整えるため、10年後、20年後を見据えて、望ましい学校規模を確保していく取組を進めていきます。【教育長】
このページのトップへ
(12)地域の移動を守る
質問
旭川市では、公共交通会議を設置し、公共交通グランドデザインから始まり、公共交通計画に至るまで、輸送密度を上げて採算性の改善を支え、そして維持をしてきたと思います。しかしながら、市民にきちんと説明できていないのではないかと思います。通勤、通学という、赤字であっても公共交通として最後まで維持をしなければならない部分ですが、市と近隣自治体等を結ぶ地域間幹線系統や一部地域のバス路線を中心に減便等を伴うダイヤ改正が行われ、今後、減便は更に増えると思われます。旭川市としての市民の移動と経済活動に関して、具体的にどのような対策を行っていくおつもりでしょうか。また、市民からの要望について、今後どのように対応していく予定なのか、併せて伺います。
回答
公共交通は、通勤、通学、買物などの市民生活のほか、観光などの経済活動においても不可欠となる重要な社会インフラであると認識しています。
市民の移動手段の確保に向けましては、地域における移動実態やニーズの把握を踏まえた検討が必要であることから、これまでも、デマンド型交通導入の要望があった地域におけるアンケート調査や、まちづくり推進協議会関係者との意見交換など、地域における移動手段の確保について協議を行ってきました。
公共交通を取り巻く環境は厳しさを増しておりますが、市としては、様々な場面で地域からの要望もお聞きしながら、最適な公共交通網を構築できるよう、引き続き、国や北海道、バス事業者など関係者と連携を図り、検討を進めていきたいと考えています。【地域振興部長】
このページのトップへ
(13)建設工事請負業者の格付
質問
建設工事請負業者の格付について、旭川市では特A、A、B、Cの等級にランク分けされています。経営事項審査の評価点以外に社会的価値を基準に入れる必要があるのではないかと思います。
社会的価値は、環境への配慮、障がい者雇用などの福祉に配慮しているか、男女平等を進めているか、雇用では公正な労働基準を適正に維持しているか、今の時期であれば除雪などの地域貢献を行っているかなど、旭川市の政策目的にも合致したものではないでしょうか。ランク分けの見直しや社会的価値を入れるなど、入札改革に取り組む必要があるのではないかと思いますが、市の見解を伺います。
回答
本市の建設工事等入札参加資格申請については、北海道市町村入札参加資格共同審査を活用していることから、一定程度、参加市町村間の申請内容について統一化が図られている状況です。
この共同審査に加え、本市の格付について、社会的価値など独自の審査基準を設定する場合、事業者に対して新たに関係資料の提出を求めることとなるため、事業者の負担増について配慮する必要があると考えています。
今回の質疑を踏まえ、他の自治体の状況も勘案しながら、御指摘のあった部分を含め、建設事業者の格付の在り方を検討していきたいと考えています。【総務監】
このページのトップへ