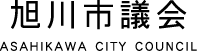あさひかわ市議会だより第117号-2
一般質問
一般質問は、定例会で議案に関係なく、市政の諸問題や将来の見通しなどについて市の考えを聞くものです。
今定例会では、9月18日から20日の3日間にわたり16人の議員が質問しました。その中から主な質問と答弁をお知らせします。
- 今定例会の質問者(発言順)
- (1)春光台公園・風の子館の解体・撤去の見直し等
- (2)北海道日本ハムファイターズ2軍本拠地の移転
- (3)中央中学校(学生対策便廃止)の課題
- (4)困難を抱える女性への支援
- (5)市立図書館のインターネット環境の整備
- (6)分煙施設整備促進
- (7)空き家対策
- (8)人口減少・少子化対策
- (9)旭川市に子どもの命は守れるのか
- (10)地域建設業界の役割と建設業を取り巻く諸課題
- (11)保育について
- (12)エネルギー安全保障とGX※施策等における本市の可能性
- (13)自分らしく働くこと
- (14)中心市街地活性化と大学等研究機関の役割
- (15)地域力の向上にむけて
- (16)選挙時の移動期日前投票所について
今定例会の質問者(発言順)
(1)品 田 ときえ(民主・市民連合)
- パークゴルフ場利用料金の改善について
- 北海道日本ハムファイターズ2軍本拠地を旭川市に誘致する取組について
- 春光台公園・風の子館の解体・撤去の見直し等について
(2)石 川 まさゆき(自民党・市民会議)
- 消防団員の確保のための施策と今後の展望について
- 大雪時の訪問系サービス事業者の利便性向上について
- 北海道日本ハムファイターズ2軍本拠地の移転について
(3)金 谷 美奈子(無党派G)
- 人口減少と若年女性の流出を止めるための課題について
- 市民活動交流センターCoCoDeの運営とカフェコーナーについて
- 米不足を招いた理由と農業政策について
- 中央中学校(学生対策便廃止)の課題について
(4)あ べ な お(自民党・市民会議)
- 醸造文化を活用した産業観光について
- 困難を抱える女性への支援について
(5)小 林 ゆうき(旭川市民連合)
- 住まいの貧困と市営住宅について
- 旭川市のジェンダーギャップ解消の取組について
- 市立図書館のインターネット環境の整備について
(6)安 田 佳 正(無所属)
- 令和6年度介護報酬改定による旭川市内の訪問介護事業所の経営状況について
- 少子化の影響による旭川市内の認可保育所の状況について
- 中央分離帯について
- 建築技術職員の資格取得について
- 分煙施設整備促進について
(7) 中 村 みなこ(日本共産党)
- ICT教育について
- 空き家対策について
- 防災対策について
(8) 沼 﨑 雅 之(自民党・市民会議)
- 人口減少・少子化対策について
(9)のむらパターソン 和孝(無党派G)
- 旭川市に子どもの命は守れるのか
(10)菅 原 範 明(自民党・市民会議)
- 地域建設業界の役割と建設業を取り巻く諸課題について
- 歴史的建造物の文化的価値について
(11) 石 川 厚 子(日本共産党)
- 軍用機の飛来と体験搭乗について
- 補聴器購入費の助成について
- 保育について
- ときわ市民ホールと勤労者福祉会館の現状と方向性について
(12)たけいし よういち(自民党・市民会議)
- エネルギー安全保障とGX施策等における本市の可能性について
- 本市におけるサイクルツーリズムの現在・過去・未来について
(13)江 川 あ や(民主・市民連合)
- 市民の意見の反映と子どもの意見の保障について
- 地域の移動を守る
- 自分らしく働くこと
- 「親なきあと」も自分らしく生きるために
(14)高 橋 ひでとし(自民党・市民会議)
- いじめ防止対策について
・有機農業とオーガニック給食について
・中心市街地活性化と大学等研究機関の役割について
・建設業界におけるDXの推進について
(15)高 木 ひろたか(旭川市民連合)
- 地域力の向上にむけて
(16) 高 花 えいこ(公明党)
- 精神障害者のバス運賃割引について
- ケアラー支援について
- 子どもの権利条約と包括的性教育について
(1)春光台公園・風の子館の解体・撤去の見直し等
質問
春光台公園の風の子館は日本で初めての木製屋根付き遊具で、既成品の遊具では代え難い魅力と価値を有しています。解体は早計ではないでしょうか。
公園遊具は、今後も老朽化が進み、更新等の対応が生じると思います。毎年の点検と同時に、耐用年数を伸ばせるように計画的なメンテナンス対応についての見解を聞かせてください。
回答
公園の遊具につきましては、毎年度の定期点検の結果や、公園施設長寿命化計画に基づき、老朽化等により使用禁止となっている遊具を中心に整備を行うこととしており、地元町内会等に整備内容について理解が得られた公園から順次着手することとしています。
今後も遊具を利用する子どもたちの安全を第一に考え、施設の利用状況や危険度などを総合的に判断し、優先順位を定め、着実に遊具の更新を進めていきたいと考えています。
メンテナンスにつきましても、これまで以上に長寿命化に視点を置いて、多くの子どもたちに長年親しまれる遊具を残していけるよう努めていきたいと考えています。【土木部長】
(2)北海道日本ハムファイターズ2軍本拠地の移転
質問
日ハムの2軍本拠地を北海道に移転する構想が進められており、旭川市も手を挙げるチャンスはあると思います。現在策定中の花咲スポーツ公園再整備基本計画において、スタルヒン球場を人工芝化し、日ハム2軍本拠地を誘致することが難しくても、日ハム育成選手や準本拠地として誘致したり、様々な野外イベントを誘致するなど、観光、スポーツ振興の活性化が期待できると思いますが、今後の本市が向かう道筋と本市が持つ可能性について市長の見解を聞かせてください。
回答
日ハムの2軍本拠地の誘致につきましては、市民がスポーツに親しみ、子どもたちが夢を育むことができるようになるほか、地域経済の振興など幅広い効果も期待できるものと考えています。
一方で、球場などは自治体による建設が求められているほか、北広島市からの距離が重視されているとの報道もありますが、今後は本市の強みを十分にPRしながら、花咲スポーツ公園の再整備だけでなく、2軍本拠地の誘致につきましてもしっかりと挑戦を続けていきます。【市長】
(3)中央中学校(学生対策便廃止)の課題
質問
中学校が3校統合され中央中学校が開校となった際、亀吉地区から中央中学校に至るスクール便が運行されていましたが、令和元年以降運行されておらず、新町小を卒業した児童が非常に不便な思いをしています。
路線の復活が難しいのであれば、例えば既存路線にバス停を増やすなどの工夫をして欲しいですが、教育長の見解を聞かせてください。
回答
児童生徒が安全、安心に通学ができることは大変重要なことであると認識しています。中央中学校の通学の利便性向上につきましては、引き続き、市内路線バス事業者と、路線復活だけではなく、既存路線の延長なども含めながら、様々な可能性を探り、協議するとともに、路線バスの運行以外の様々な手法につきましても責任を持って検討をしていきます。【教育長】
(4)困難を抱える女性への支援
質問
本市では今年度、若年女性を主な対象とする居場所づくりや、LINEを利用した新たなアウトリーチ型相談支援事業を開始し、一定の成果があるようですが、今後は相談体制の充実のためにも、支援者の育成や知識の底上げのために研修などの実施が必要なのではと考えます。本市の困難を抱える女性への支援について市長の考えを聞かせてください。
回答
困難を抱える女性が直面する状況は、支援の方法も多様であり、解決へのアプローチは慎重かつスピード感を要することから、どこに相談したらよいか分からない女性が、独りで抱えず、自分のことを安心して話せる、小さなことでも気軽に相談できる、さらに、同様の課題を抱える友人にも教えてあげられるといった相談窓口の存在が重要です。
今後も、引き続き、庁内各部、関係機関がチーム一丸となって、支援を必要としている女性と行政や関連団体との懸け橋となるべく連携し、全ての女性が活躍できる地域社会の実現を目指すとともに、今、困難を抱える女性が問題解決につながっていくような取組をしっかりと進めていきます。【市長】
(5)市立図書館のインターネット環境の整備
質問
近年、読書離れ、図書館離れが話題になっています。利用者が勉強や作業をするのに便利なように、市立図書館においても多様な市民ニーズに応え、学びや研究をサポートするために電源設備やWi-Fi等のインターネット環境の整備を進めるべきだと考えますが、市の見解を聞かせてください。
回答
図書館は、読書のできる場所や本を貸し出す場所としてだけではなく、レファレンス※などの役割がありますが、来館される方は、図書館内で読書や調べ物をしている際に、分からない用語などを図書館内のパソコンや自分のスマートフォンなどで調べているものと考えており、図書館の基本方針の一つでもある自主的学習活動の支援を進めるためにもWi-Fi環境の整備は有効であると考えているところです。
こうしたことから、図書館で静かに読書できる環境などにも配慮しながら、Wi-Fi環境の整備に向けて要望をしっかりと受け止め、検討していきたいと考えています。【社会教育部長】
※レファレンス…図書館で利用者の疑問や相談に答える情報探しのサービス。「参考調査」、「調査相談」などとも言われる。
(6)分煙施設整備促進
質問
分煙施設の整備は、受動喫煙防止のみならず、環境美化や喫煙マナーの向上も見込まれます。先般の税制改正大綱や総務省通知でも、たばこ税を活用し、積極的に分煙施設の整備に取り組むよう示されていました。
旭川でも、札幌市のように旭川駅などで屋外分煙施設を設けるといった実証実験を行うべきではないかと思いますが、市の見解を聞かせてください。
回答
屋外の分煙施設設置につきましては、歩きたばこやポイ捨ての抑制による環境美化の促進、また、インバウンドを含めた観光客の受入れ体制の充実等の観点では効果が期待できると捉えていますが、景観への配慮や維持管理コストといった課題もあり、その必要性、優先度を検討し、判断する必要があるものと考えています。
屋外分煙施設を設ける実証実験の実施については、中心市街地や公園等での喫煙やポイ捨ての状況、市民や設置場所の管理者の意向等を関係部局で十分共有しながら、様々な視点から検討していきます。【副市長】
(7)空き家対策
質問
年々増え続ける空き家が社会問題となっています。放置されたままだと、老朽化が進み様々な問題につながるおそれがあります。行政代執行などの手段についてもよほどの危険性がなければ執行されないとのことですが、突然の災害などで取り返しのつかない事態を引き起こしかねません。
市民の安心、安全な暮らしを実現すべき市としてこれでいいのか、市の見解を聞かせてください。
回答
令和5年度に空家特措法が改正され、一定の対策強化が図られたものの、特定空家等の対応策については市としても苦慮しています。
令和5年度から、北海道市長会を通じて、一定の条件のもとで、所有権を地方公共団体に帰属させ、解体や売却などの対応を迅速にできるよう、国に対して法改正の要望を道内他10市の賛同を得た上で共同提案として提出しています。
法改正のハードルは高いものと認識していますが、引き続き現場の声を国に伝えていきたいと考えています。【建築部長】
(8)人口減少・少子化対策
質問
人口減少、少子化対策というのは部局横断的な政策です。旭川市の人口減少、少子化対策の責任者について、各部局にまたがる政策を見渡す立場として、例えば副市長の1人を担当に任命するなどは考えられないでしょうか。市長の見解を聞かせてください。
回答
人口減少対策につきましては、子育て環境の充実や地域経済の活性化、雇用環境の充実など、様々な取組を総動員していくことが大事だと思います。その上で、このまちに住み続けたい、住んでみたいと思えるような、魅力的なまちづくりを進めることが何よりも大切だと考えています。
そのためには、関係部局が連携して横断的な取組を進める必要があると私も考えていますが、担当の副市長を置くよりも、3名の副市長が心を一つにしっかりと人口減少問題に取り組んでいくことが大切であり、部局を横断してしっかりと市役所全体で取り組んでいきたいと考えています。【市長】
(9)旭川市に子どもの命は守れるのか
質問
旭川市いじめ問題再調査委員会からの調査報告書が公表されました。報告書には様々な要因が記載されていましたが、いじめ被害に焦点を当てて事件の幕引きを図ることは適当なのでしょうか、見解を聞かせてください。
回答
この度の再調査報告書では、事案発生当時の教育委員会において、法に基づく専門的知見が欠如しており、適切な対応がされなかったことや、学校における組織的な対応がなされなかったことなどについて、改めてご指摘をいただきました。今後、再発防止策の提言を踏まえ、早急にこれまでの取組を検証したうえで、実効性のある具体的な対策を取りまとめ、全ての児童生徒が安心して生活し、学ぶことができる社会の実現に向けて、学校、教育委員会、市長部局が一体となったいじめ防止対策を推進していきたいと考えています。【教育長】
(10)地域建設業界の役割と建設業を取り巻く諸課題
質問
建設業界においては新規就労者の減少、技術者の高齢化が進んでいます。今後、さらに人材不足が懸念され、建設業は成り立たない時代になりかねません。そうなると、市民生活や経済活動が停滞し、更には、人口減少などに重大な影響を及ぼすことが危惧されます。
こうしたことに対処するためにも、ICT施工など近代化による職場環境の改善などの働き方改革や、地域や地元企業の魅力発信など、官民一体となった取組が必要と考えていますが、市の見解を聞かせてください。
回答
建設業の担い手の確保に向け、国や北海道、地元建設業界と本市で構成する「北のけんせつ担い手」育成会議において、小学生や高校生を対象とした現場見学会の開催や、旭川冬まつりへの出展など、官民一体で建設業の仕事や地元企業の魅力発信に取り組んでいます。
また、働き方改革への対応については、ICT施工や事務の効率化など、いわゆる建設DXを推進していくために、本市が主体となって建設業の方々と意見交換を行う会議を新たに設ける準備を進めているところです。
今後も、こうした取組を通じ、官民で連携しながら建設業界における働きやすい環境づくりに積極的に取り組んでまいります。【土木部長】
(11)保育について
質問
就学前児童数は急激に減少しています。旭川市も、年齢に関係なく同一世帯の子どもの第2子以降の無償化に踏み切る時期に来ていると思いますが、3歳未満児の保育料の無償化について、市長の見解を聞かせてください。
回答
少子化や人口減少が急速に進む本市におきまして、子育て施策は最重要施策であると考えており、子どもの健やかな成長を図るとともに、子どもを産み育てることを前向きに捉えてもらえるよう、ライフステージに応じて切れ目ない支援をすることが必要であるとの認識のもと、これまでも中学生までの医療費無償化や大学生等への奨学金の創設などを行ってきました。
こうした観点からも、保育料の多子軽減策を含めた子育て世帯の経済的な負担軽減策につきましては、財政状況も踏まえながら総合的に検討していきたいと考えています。【市長】
(12)エネルギー安全保障とGX※施策等における本市の可能性
質問
北海道大停電から6年が経ちます。現在、旭川市を含む道北地域は再生可能エネルギー王国になるであろうと言われていますが、道内の送電インフラが道外と比較して極めてぜい弱な状況です。送電網の整備は基礎自治体としての立場を超え、国に対し、未来を見据えた働きかけを行うことも肝要であると考えますが、市の見解を聞かせてください。
回答
我が国におけるエネルギーの安全保障やエネルギーの地産地消などにつきましては、国策としての要素が強いものですが、道内で創出される再生可能エネルギーを最大限活用し、その効率的消費を図りながら、本市においてGX・DX産業の集積を進め、地域の振興や経済活性化を図るためには、送電網の増強が非常に大きな課題の一つであると認識しています。
そのため、本市としても、北海道などとも密接に連携しながら、経済産業省に北海道内における送電網の増強を要望したところであり、今後も、引き続き、本市において再生可能エネルギーの可能性を最大限活用できるよう、国にしっかりと働きかけていきます。【環境部長】
※GX…グリーントランスフォーメーションの略。温室効果ガスの排出削減と経済成長の両立を図る社会変革の取組。
(13)自分らしく働くこと
質問
障がいのある子どもが、保護者の手を離れて、自らの意思を持って働き出して、自分らしく生きていくために、行政としてどのような支援を行っていく必要があるのか、市の見解を聞かせてください。
回答
障がいがある方の、親亡き後を見据えた体制整備については、国の方針に基づきながら整備を進めており、本市においても短期入所の空き情報共有システムを運用するなど、自立と自律を両立して安心な生活を送ることができるよう拠点づくりを進めているところです。
障がいのある方の日常活動における環境の充実は今後更に重要となりますので、地域の実情を踏まえ効果的な施策の推進を図るとともに、必要な財源確保に向けて取り組んでいきます。【福祉保険部長】
(14)中心市街地活性化と大学等研究機関の役割
質問
現在千歳市に半導体工場を建設中のラピダスが、同社発展に寄与し得る資源があれば、これを積極的に活用したいため、旭川市などの他地域においても、積極的に売り込んできてほしい旨の話がありました。旭川市も産学官金連携拠点や大学コンソーシアム※を武器として積極的に売り込んでいく意思があるのか、市の見解を聞かせてください。
回答
ラピダスも含めた最先端技術産業が地域の活性化につながる可能性がありますことから、本市としても、人材の輩出や高度な研究等を行う高等教育機関を有する、かつ優れた技能、技術を持ったエリアであることを、大学など関係機関とも連携し、広く発信していきます。【総合政策部長】
※大学コンソーシアム…個別に取り組むと手間や費用のかかる事業を共同で行うため、近隣の大学などが集まった組織。
(15)地域力の向上にむけて
質問
近年の町内会の加入率の低下や、地区割りの不整合、旭川市の部局間の連携の悪さなど、課題は山積していますが、地域力の向上にむけた考え方について、市の見解を聞かせてください。
回答
今後は市民生活部が中心となり、各部局が持つ情報を集約するとともに、町内会の実態の把握を改めて行った上で、既存の様々な組織の地区割りの整理、また、地域に対し、行政がどう関わっていくのかという視点から、地域自治推進会議の活用も含めて、庁内で地域に関わる課題を共有し、横断的に議論を進めていきたいと考えています。【副市長】
(16)選挙時の移動期日前投票所について
質問
選挙権の行使は、基本的人権の中でも最も重要な権利であり、民主主義の根幹をなす事項の一つです。移動期日前投票所は、知的障がい者や認知症の方、障がいのある方が投票しやすいようなシステムであるべきだと考えますが、市の見解を聞かせてください。
回答
移動期日前投票所は、移動が困難な障がい者や高齢者などにとってより利便性が高まるものと考えられますが、こうした方々の居住実態としては、市営住宅のほか、マンションや施設に入所されている方、一般住宅で暮らす方など、実態は様々であり、こうした方々の状況に応えるためには相当数の設置が必要となります。また、仮に設置数を限定するとした場合も、市内全域において巡回地点の基準をどのように設定するかなど、実施する上での課題は大きいものと考えています。
移動期日前投票所については、試験的に実施しながら、利用状況や運用方法などを検証し、より有効な活用方法を検討していきます。【選挙管理委員会事務局長】