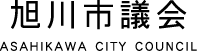あさひかわ市議会だより第116号-2
一般質問
一般質問は、定例会で議案に関係なく、市政の諸問題や将来の見通しなどについて市の考えを聞くものです。
第2回定例会では、6月18日、19日及び20日の3日間にわたり16人の議員が質問しました。その中から主な質問と答弁をお知らせします。
- 今定例会の質問者(発言順)
- (1)旭川市の水道水における有機フッ素化合物汚染の状況
- (2)稼ぐ農業
- (3)地域公共交通
- (4)大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部改正
- (5)本市最大の集客施設「旭山動物園」の魅力
- (6)(仮称)新文化ホールのコンセプト
- (7)女性と防災
- (8)介護保険制度
- (9)行財政改革推進プログラム2024
- (10)こども家庭センター
- (11)愛育センターにおける療育支援の充実
- (12)小中学校のスキー授業を巡る課題
- (13)ユネスコ創造都市ネットワークサブネットワーク会議
- (14)介護認定審査会のDX化
- (15)木質バイオマスを活用した循環型暖房エネルギー
- (16)精神障がい者のバス運賃割引
今定例会の質問者(発言順)
(1)金谷 美奈子(無党派G)
- 旭山公園夜桜まつりについて
- 市民活動交流センターCoCoDeの運営とカフェコーナーについて
- 学校給食の課題について
- 東光スポーツ公園のパークゴルフ場について
- 旭川市の水道水におけるPFAS(有機フッ素化合物)汚染の状況について
(2)えびな 安信(自民党・市民会議)
- 稼ぐ農業について
- ふるさと納税について
- 総合計画について
(3)植木 だいすけ(旭川市民連合)
- フードロスについて
- 地域公共交通について
(4)塩尻 英明(旭川市民連合)
- 就労系障がい福祉サービス等について
- 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部改正について
(5)駒木 おさみ(公明党)
- 地域を豊かにし、人を呼び込むための新たな酒と醸造文化の魅力について
- 本市最大の集客施設「旭山動物園」の魅力について
- 中心市街地の活性化について
(6)菅原 範明(自民党・市民会議)
- 事業継続計画(BCP)について
- (仮称)新文化ホールのコンセプトについて
- 旭川市常磐公園の再整備について
- ヒグマ対策について
(7) あべ なお(自民党・市民会議)
- 女性と防災
- 下水汚泥堆肥と農業
- 観光と経済
(8) まじま 隆英(日本共産党)
- 地方自治の在り方について
- 市長の海外出張について
- 介護保険制度について
- 子どもへの支援について
(9)石 川 厚 子(日本共産党)
- 行財政改革推進プログラム2024について
- 自衛隊への個人情報提供について
- 後援名義の使用承認について
- 市長の政治姿勢について
(10)沼 﨑 雅 之(自民党・市民会議)
- こども家庭センターについて
- 女性のためのLINE相談「あしたば相談」について
- 新生児聴覚検査について
- 給食の安全について
- 中心市街地活性化について
(11) 笠 井 まなみ(自民党・市民会議)
- ふるさと旭川市の特徴を活かした教育の充実
- 愛育センターにおける療育支援の充実
- ごみ処理の方向性について
(12)横 山 啓 一(無所属)
- 小中学校のスキー授業を巡る課題について
- 行財政改革推進プログラム2024と大規模事業等について
- 政教分離原則と市長の政治姿勢について
(13)江 川 あ や(民主・市民連合)
- ユネスコ創造都市ネットワークサブネットワーク会議について
- 会計年度任用職員の待遇改善について
(14) 石 川 まさゆき(自民党・市民会議)
- 子どもの貧困防止~生活困窮者の子どもの健全育成について
- 介護認定審査会のDX化について
- カムイスキーリンクスの市民利用の活性化に向けて
(15)皆 川 ゆきたけ(公明党)
- 連携協定と市政アドバイザーについて
- GXへの取組と新たな企業誘致の可能性について
- 木質バイオマスを活用した循環型暖房エネルギーについて
(16)中 村 みなこ(日本共産党)
- 精神障害者のバス運賃割引について
- ケアラー支援について
- 子どもの権利条約と包括的性教育について
(1)旭川市の水道水における有機フッ素化合物汚染の状況
質問
昨今、水道水のPFAS(有機フッ素化合物)汚染が全国的に取り沙汰されています。汚染濃度が高い地域では腎臓病やすい臓がん、流産が多くなっていると言われ、不安が広がっていますが、旭川市の状況はどうなっているのか聞かせてください。
回答
旭川市には石狩川浄水場と忠別川浄水場の2か所の浄水場があります。国の水質管理における暫定目標値は1リットル当たり50ナノグラムですが、令和5年度の数値として、石狩川浄水場では0.3ナノグラム、忠別川浄水場では1.2ナノグラムと、目標値を大きく下回っています。
旭川市水道局は、日本水道協会が認定する水道水質検査優良試験所規範を取得しておりますが、今後とも正確かつ精度の高い水質検査を行うことで、信頼性の高い飲料水の供給に努めていきます。【上下水道部長】
(2)稼ぐ農業
質問
旭川市の野菜生産量はここ10年ほどで30%も減少しています。農業従事者の高齢化による担い手不足、農業生産資材の高騰など、原因は様々ありますが、農業は経済的な側面のほかにも、生物多様性の保全や治水による洪水防止など、多面的な役割を果たしています。食料安全保障の観点からも、これから旭川市が担う役割は大きくなっていくと考えていますが、その振興について今後どのように考えているか市長の見解を聞かせてください。
回答
これまで、農地の基盤整備、スマート農業の推進、暑熱対策、物価高騰対策など、直接的な支援のほか、色々な方にご協力いただきながら、旭川の農産物の魅力を発信してきました。食を有機的にデザイン思考で結び付けるフードフォレスト構想もスタートしたところです。
今後も農業者が稼ぎ、安心して営農を継続できるようしっかりと支援し、旭川農業の発展に努めるとともに、国の掲げる食料安全保障にも貢献していきたいと思います。【市長】
(3)地域公共交通
質問
全国的にバスの運転手不足などが問題とされており、地域の公共交通の維持は重要な課題とされています。本市においても、バスの運転手の減少が課題となっており、バスの運行本数は令和元年度から比べると8割程度に減少しているなど、地域の足に影響が生じています。
地域公共交通の維持は、民間事業者の努力では限界があり、市町村が主体的、中心的に関与していくべきと考えますが、今後の取組をどのように考えているのか聞かせてください。
回答
これまで市内バス事業者2社のICカード共通化や、運行情報アプリの導入支援、公共交通マップの配布、市内2地区におけるデマンド型交通の導入などに取り組んできました。また、現在旭川市とバス事業者等による検討組織を立ち上げ、路線運行の効率化に向けた取組の検討を行っているところです。
今後とも、市民に公共交通の必要性を認識していただき、利用の機運を高めるとともに、関係機関とともに、存続に向けた取組について検討していきます。【地域振興部長】
(4)大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部改正
質問
大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法が一部改正されました。昨今、大麻草を巡る情勢は様々に変化しているところですが、今後旭川市で産業用大麻の産地化に取り組むことは難しいのでしょうか。市の見解を聞かせてください。
回答
今回の法改正により、法的ルールが明確になることで、国内においても栽培が容易になると考えられますが、産地化のためには種子の確保、栽培技術の確立や収益性の検討、出荷先の開拓など、様々な課題があります。
しかし、産業用大麻は製品原料として活用の幅が広く、土壌改良の効果が期待され、バイオマス資源としての活用の可能性もあることから、今後とも調査研究を続けていきたいと考えています。【農政部長】
(5)本市最大の集客施設「旭山動物園」の魅力
質問
本市最大の集客施設である「旭山動物園」については、現在Universal MaaSの実証実験の対象にもなっておりますが、今後さらに安心して利用できる施設にしようとしていく努力が必要になると思います。電動車椅子や、障がいの有無にかかわらず、全ての子どもたちが思う存分遊べるような、インクルーシブ遊具を設置してはどうでしょうか。
また、これからの施設整備に係る経費を捻出するために、海外からの観光客向けの入場料を別途設定するなど、持続可能な入園料の見直しをしてはいかがでしょうか。
回答
現在旭山動物園には手動式の車椅子20台、電動アシスト車椅子1台、電動カート3台が設置されています。今後はUniversal MaaSの実証実験の結果等も踏まえつつ、急な傾斜地に立地している旭山動物園の特性にふさわしい機種を選定した上で、更なる配置に向け、検討を進めてまいります。
また、園内の遊具施設については老朽化のために平成19年に全て廃止をしておりましたが、今年度実施設計を予定しておりますので、インクルーシブの視点も取り入れた遊具の設置を検討してまいります。
様々なコストの発生や、物価高騰の中で施設を運営していくためには、支出の抑制だけではなく、収入の確保も必要となります。入園料の見直しにおいては、魅力やサービス向上など、来園者に納得してもらえることも必要なため、慎重かつ総合的に検討を重ねていきます。【経済部長】
(6)(仮称)新文化ホールのコンセプト
質問
5月28日に第1回目の市民文化会館整備基本計画の検討会が開催されたと聞いております。2025年度までに話をまとめるとのことですが、新文化ホールの計画の進捗状況と、そのコンセプトについて聞かせてください。
回答
現在の進捗については、昨年度に学識経験者や利用団体関係者などで構成した検討会を開催するとともに、パブリックコメントを行いながら、市民文化会館整備基本構想を策定したところです。今年度は基本計画の策定に係る検討会を開催し、その取組を進めているところです。
施設整備に係るコンセプトについてですが、新たな文化ホールが、次世代へつなげる文化交流活動の拠点として、市民の誇りと愛着を育む道北のランドマークとなることを目指すとした基本理念を定めました。【文化ホール整備担当部長】
(7)女性と防災
質問
災害発生時、災害対応や避難所運営などでは女性の視点を取り入れていくことが必要ですが、防災担当部局には女性職員が配置されていません。
避難生活が長期化した場合は公的機関のみではなく、避難所運営に自主防災組織を中心とした地域住民の協力が不可欠となります。女性が避難所生活で不安を抱くことがないよう、女性が避難所運営に積極的に参加できるように、女性リーダーの育成に取り組むなど、本市の計画を定めるべきと考えますが、市の見解を聞かせてください。
回答
避難所運営に当たっては、女性特有のニーズに対応するため、女性職員も関わることが重要と考えています。
本市で実施する避難所開設訓練においては、参加予定職員113名のうち43名が女性職員となっており、男女問わず避難所運営に関わる体制づくりを進めています。
また、本市の避難所開設・運営マニュアルにおいては、避難所運営が長期化する場合、町内会や自主防災組織などが避難所運営委員会を設置することとしており、当該委員会への女性の参画について支援をしていきたいと考えております。【防災安全部長】
(8)介護保険制度
質問
2024年度の介護報酬改定では、訪問介護ヘルパーの報酬が引き下げられました。この改定によりどのような影響があると考えられますか。また、市内の介護事業所では訪問介護員が不足していますが、市としてはどのような対応を考えていますか。
回答
今回の改正により、訪問介護の基本報酬が減額となったことから、関係団体からは、人材の確保や事業継続が困難になるとの懸念が示されており、特に訪問介護事業所には影響が大きいものと思われます。
市として、令和6年度には訪問介護員として就労するために必要な資格である介護職員初任者研修を市内で開催することで研修の機会を確保するほか、研修の受講後、市内の訪問介護事業所に6か月以上勤務した場合に研修費用の一部を助成する制度を新設するなど、人材を養成し、市内事業所への就労につなげてまいりたいと考えています。【保険制度担当部長】
(9)行財政改革推進プログラム2024
質問
令和6年度から令和9年度までで、累計89億円の財政収支不足が見込まれています。行革プログラム2024では、第8次総合計画施策の着実な推進とその裏付けとなる財政面の補完をうたっていますが、やろうとしていることは人件費の削減とふるさと納税の推進による収入の確保ではないでしょうか。同プログラムの総体的な認識を伺います
回答
同プログラムは、職員の働きがい改革や人材育成などに取り組む「マネジメント」、健全な財政運営のための歳入確保や持続可能な行政サービスに向けた歳出削減に取り組む「財政健全化」、多様な主体との連携に取り組む「連携・協働」の3つの視点から行財政改革を進めようとするものです。
特に、人口減少が進む中、高い資質と意欲を有する人材を育成、確保し、一人一人がのその能力を存分に発揮できることが今後の行政運営にとって重要であることから、時間外勤務の削減などの働きがい改革は差し迫った課題です。また、持続可能な財政運営のためには、あらゆる手段を講じながら収支不足解消に努めなければならないことから、同プログラムに基づく取組を着実に推進しなければならないと考えています。【副市長】
(10)こども家庭センター
質問
今年度から施行された改正児童福祉法に対応し、全ての妊産婦、子育て世帯、子どもたちへの相談支援を一体的に行う機能を有するこども家庭センターが設置されました。本市では、母子保健機能を担う子育て世代包括支援センターが駅前に、児童福祉機能を担う子ども総合相談センターが10条通11丁目に存在しているため、両施設の連携を担うセンター長と統括支援員が担う役割が非常に重要になると考えられます。旭川市において、母子保健と児童福祉の一体的運用をどのように図っていくのか、また、その中でセンター長及び統括支援員が果たす役割について聞かせてください。
回答
本市のこども家庭センターでは、母子保健機能を担うおやこ応援課と児童福祉機能を担う子ども総合相談センターが双方の専門性を生かした支援を行っていますが、両課の設置場所が分かれていることから、情報や支援方針に食い違いが生じないよう、毎週、両課で合同会議を開催するなど、一体的な運用を図っております。
また、センター全体のマネジメントを行うセンター長及び母子保健機能と児童福祉機能における双方の業務や専門性について知識を持つ統括支援員は、合同会議を開催する中で、調整役として両機能の専門性、考え方を引き出しながら一層の協働、連携の下に支援が図られるよう、必要な指導助言を行っているところです。【子育て支援部長】
(11)愛育センターにおける療育支援の充実
質問
本市の愛育センターは設置から43年が経過しており、施設全体の老朽化が見てとれます。必要な療育を安心、安全に行っていく上で、環境整備は重要であると考えますが、園庭の抜本的な整備やインクルーシブ遊具の設置など、今後のセンター全体の整備について見解を伺います。
回答
愛育センターは、身近な地域で支援を受けられる施設として多くのお子さんを受け入れてきており、地域における中核的な療育支援施設である児童発達支援センターとしての役割を踏まえると、その機能をしっかり維持していく必要があり、施設の修繕や改修などを計画的に行っていかなければならないと考えております。ご指摘のような遊具の導入については、他の類似施設、今年度設置予定のインクルーシブ遊具を有する忠和公園の利用状況も踏まえながら、遊具の選定、財源確保の状況、施設整備における優先順位などを含めて検討していきます。【副市長】
(12)小中学校のスキー授業を巡る課題
質問
スキー授業の実施に際しては、観光客増により貸切バスを確保することが難しくなっているほか、バス料金や、スキースクール経費の増加、リフト代や用具代など、保護者の負担が増加しております。このままではスキー授業の継続が困難になってしまうのではないかと思いますが、市として緊急に何らかの負担軽減策を講ずる必要性があるのではないでしょうか。市教委の見解を伺います。
回答
学校教育に関わる保護者の負担については、スキー授業だけではなく、様々なものがあり、これまでも国の制度の活用のほか、就学援助制度の充実などにより軽減策を講じてきております。
緊急的な対策については、新たな財源が伴うことであり、また、スキー授業を実施していない学校との公平性の整理など検討する項目はありますが、学校の意向等も確認する中で整理、検討していきます。【学校教育部長】
(13)ユネスコ創造都市ネットワークサブネットワーク会議
質問
今年の10月に本市でユネスコ創造都市ネットワークのサブネットワーク会議が開催されます。7つの分野ごとに都市間の協力を促進し、先進事例の共有や意見交換、交流を通じて都市間の連携強化を図るための重要な会議ですが、旭川市として今回のサブネットワーク会議をどのように位置付けて取り組んでいますか。また、今後の交流に関しての市の見解と意気込みを聞かせてください。
回答
本市での会議の開催は、デザイン都市旭川を世界にPRするとともに、各創造都市との交流を深める絶好の機会であり、各都市の先進事例を共有することで、お互いの都市のコミュニティーの発展や創造性を生かした新たな取組にもつながるものと考えております。また、デザインのみならず、幅広い分野での連携の可能性や官民一体となった取組により、市民のデザインに関する理解促進や意識の向上、国際会議の開催によるシビックプライドの醸成にもつながると考えます。
本地域が有する自然と都市の融合、食の豊かさや環境に配慮したものづくり産業など、多様なまちの姿を参加者に体感していただくとともに、官民が一体となっておもてなしをすることで、ユネスコ創造都市ネットワークの目的であります都市間の交流が促進、発展していくことが期待されますので、参加者が旭川に好印象を持って本市の魅力を広くPRしていただけるよう、しっかりと準備を進めていきます。【経済部長】
(14)介護認定審査会のDX化
質問
本市の介護申請から認定までの所要日数は全国、全道の平均よりも遅延しがちです。網走市では介護認定審査会をペーパーレス化して、職員の負担軽減、オンライン化による審査員の出席率の向上を果たしています。9年後にはデジタル行政日本一を目指している本市でも、オンライン化等を検討するべきではないでしょうか。
回答
介護認定審査会につきましては、現状では会議を滞らせることなく開催できており、また、導入経費を考えると直ちにオンライン会議を導入することには課題がありますが、災害等の不測の事態を考慮すると、本市においても、今後導入に取り組んでいく必要性があるものと認識しております。
今後も、国の支援や他の自治体の動向などを注視しながら、認定審査会のオンライン開催について検討していきます。【保険制度担当部長】
(15)木質バイオマスを活用した循環型暖房エネルギー
質問
本市が目指すゼロカーボンシティの実現のために、旭川市周辺の豊富な森林資源を活用し、木質バイオマス燃料の活用を推進するという観点から、今後、新たな公共施設建設の際や、重油ボイラー、ストーブなど設備更新の際には、環境に配慮した木質ペレットボイラーを積極的に導入していくべきと考えますが、本市の見解を聞かせてください。
回答
ペレットボイラーの導入につきましては、地域の強みを生かした地域経済にも益する温室効果ガス排出量の削減手法であること、重油などの価格上昇も予期されることなどから、国の交付金なども活用し公共施設への導入を積極的に協議してまいります。
また、ペレットバーナーについても、重油ボイラーを少ない費用でペレットボイラーに転換できるなど、今後の普及促進に向けた様々な展開が期待できますことから、その導入可能性についても調査、検討を進めてまいります。【環境部長】
(16)精神障がい者のバス運賃割引
質問
身体障がい者、知的障がい者の方はICカードでの支払い時に割引を受けることができますが、精神障がい者の方は、運転手に障がい手帳を示さないと割引を受けられません。精神障がい者の方もICカードでの支払時に割引を受けられるようにするべきではないでしょうか。
回答
身体障がい者、知的障がい者の方の割引はバス事業者が実施する割引制度であるのに対し、精神障がい者の方の割引は市の補助事業による割引制度です。ICカード支払い時の割引を利用するには、市へ補助金を請求するためのシステム改修が必要となり、また、精神障がいの手帳には有効期限があるため、カード発行に係る窓口業務の見直しも必要となります。バス事業者に対しては運賃割引制度の拡大について理解と協力を求めていくとともに、財政的な支援に関しても国への要望を含め検討していきます。【福祉保険部長】