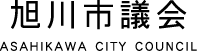あさひかわ市議会だより第95号-2
一般質問
一般質問は、定例会で議案に関係なく、市政の諸問題や将来の見通しなどについて市の考えを聞くものです。第3回定例会では、9月18日から20日までの3日間にわたり13名の議員が質問しました。その中から主な質問と答弁をお知らせします。
- 今定例会の質問者(発言順)
- (1)今シーズンの除排雪
- (2)民生・児童委員の活動への支援
- (3)新学習指導要領への対応
- (4)成人式の対象年齢
- (5)農繁期の臨時雇用対策
- (6)自殺予防対策
- (7)緑が丘地域活動センター内の図書コーナー
- (8)マイナンバーカードの普及の取組
- (9)終活への支援
- (10)次期清掃工場の水没の危険性
- (11)日韓問題における本市への影響
- (12)JRの利用促進
- (13)認知症サポーター養成講座
今定例会の質問者(発言順)
(1)えびな 信幸(自民党・市民会議)
- 人口減少問題と今後の地域社会の在り方について
- 災害対策及び雪対策について
- 行財政改革について
(2)能登谷 繁(日本共産党)
- 幼児教育・保育の無償化について
- 民生委員・児童委員の役割と活動について
- 文化芸術ゾーンの形成と常磐公園周辺の施設整備について
(3) ひぐま としお(無党派G)
- 除排雪について
- スノーダクト等の汚水管への誤接続の検査等について
- 新学習指導要領への対応等について
(4) 高花 えいこ(公明党)
- 成人式の開催について
- 期日前投票について
- 教育問題について
- 子育て支援について
- 除排雪について
(5) 高見 一典(民主・市民連合)
- 農林業政策について
- スポーツ振興について
(6) まじま 隆英(日本共産党)
- 優佳良織工芸館等について
- 福祉のまちづくりと旭川市の自殺対策について
- 第7期旭川市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画について
(7) 江川 あや(民主・市民連合)
- 図書館の選書等について
- 公園の管理等について
(8) 上村 ゆうじ(自民党・市民会議)
- 中心市街地活性化
- 住民票等のコンビニ交付
- 市民アンケート調査
- 市立病院の分娩休止の影響
(9) 林 祐作(自民党・市民会議)
- 中央図書館の在り方について
- 終活について
- 高齢者福祉の新たな展開に向けて
- 今後の公共交通の在り方について
(10) 佐藤 さだお(無所属)
- 本市の国際親善事業について
- 本市の拉致問題に対する取組について
- 新清掃工場について
- 本市のプールについて
- 本市の小学校における水泳教育について
(11) 室井 安雄(公明党)
- 旭川大学の市立化について
- 新庁舎建設のスケジュール変更による影響について
- 投票率向上のための施策について
- 市有文化施設の利活用について
- 日韓問題における本市への影響について
(12) 金谷 美奈子(無党派G)
- 旭川ハーフマラソンについて
- JRの利用促進について
- 大成市民センターについて
- 公園の明るさについて
- 旭山公園夜桜まつりについて
(13) 横山 啓一(無所属)
- 新旭川市史の編集について
- 若年性認知症の支援について
(1)今シーズンの除排雪
質問
市では、毎年11月頃に市民を交えた除雪の協議会を開催していますが、今年はそれとは別に7月下旬に各地区の除雪連絡協議会の臨時会を開催しました。その中で、どのような意見があり、また、今シーズンにどのように生かしていくのか、聞かせてください。
回答
参加者からは、交差点の見通し確保やバス路線などの幹線道路の幅員確保のほか、除雪センターの丁寧な対応、地域除雪活動の推進、除排雪状況の情報発信など、様々なご意見を頂きました。
臨時会で頂いたご意見や、現在実施している雪対策基本計画の取組に対する評価、市民ニーズの変化などを検証するアンケート調査の結果等を参考に、全地区全体での応援体制の強化やバス路線の幅員確保など、今シーズンから改善できることは少しでも早く取り組み、冬期間の道路環境が良好に保たれるよう努めていきたいと考えています。【土木部長】
(2)民生・児童委員の活動への支援
質問
民生・児童委員の皆さんがその役割を十分に発揮できるような仕組みづくり、様々なご苦労の中でも活動を継続できるような支援体制、そして、担い手を広げるための魅力の発信など、市が積極的に役割を果たす必要があると思いますが、どのように考えていますか。
回答
民生・児童委員がより円滑に活動できるよう、一斉改選ごとに定数の増員を行ってきたほか、適時、担当地区の再編などにも取り組んでいます。また、担い手を増やすための魅力の発信としては、今年の市民広報で、民生・児童委員の記事を複数回掲載したほか、市職員には、退職後も積極的に地域で活動してもらえるように要請しています。
少子高齢化や単身世帯の増加、地域コミュニティの希薄化などが進む中で、民生・児童委員を始め、地域に関わる様々な団体や組織との連携協力は不可欠であり、今後もそれらの団体が活動しやすい環境づくりに取り組んでいきます。【市長】
(3)新学習指導要領への対応
質問
新学習指導要領は、小学校では来年度から、中学校では令和3年度から開始されますが、障害のある子どもたちへの対応はどのように示されているのか、また、市はどのように取り組むのか、聞かせてください。
回答
新学習指導要領では、特別支援学級はもとより、通常の学級においても、教育上、特別の支援を必要とする児童生徒に対して、個々の障害の状態等に応じて組織的に支援、指導を行うことが必要であると示されています。
本市としては、児童生徒の自立と社会参加を見据え、多様な観点から一人一人のニーズに応じた教育機会を提供するため、児童生徒の実態に応じた支援を行う必要な人員を確保するとともに、今後も、教員の専門性の向上を図る研修会を実施するなど、各学校における特別支援教育の充実に努めていきます。【学校教育部長】
(4)成人式の対象年齢
質問
成人式の対象年齢については、本市アンケート結果や他都市の状況では、民法改正により成人年齢が18歳に引き下げられた後も20歳とする回答が多いようです。市民の方々の準備もあることから早期に周知すべきと考えますが、見解を聞かせてください。
回答
アンケート結果では、対象年齢を現行のまま20歳とすべきとの回答が多く、また、日本きもの連盟からも20歳の成人式の継承に関する要望が、市と教育委員会に提出されるなど、現行どおりの成人式を望む声が多いものと認識しています。また、数は少ないものの20歳で実施することを決めた自治体があるなど、少しずつ動きが出てきています。
現在、国において成人式の在り方の検討も実施されており、本市としては、その動向を注視しつつ、それぞれの家庭における準備等もあることから、アンケートの回答や要望などを尊重し、教育委員会委員や社会教育委員などの意見を聞きながら早急に検討を行い、可能であれば来年中には対象年齢の結論を出せるように取り組みたいと考えています。【教育長】
(5)農繁期の臨時雇用対策
質問
現在の農業は、機械化されているとはいえ、稲作の田植え時期は人手が必要で、労働力確保が難しい状況です。農繁期の雇用確保対策について今後どのように進めていくのか、市の考えを聞かせてください。
回答
平成27年度から農業団体が無料職業紹介所として許可を取得し、農家に農業ヘルパーを紹介するなどの取組を行っていますが、労働力不足の解消には至っていないものと認識しています。このため、今後においては、農業現場の労働力として大いに期待できる主婦層や学生などの働き手の労働環境や雇用条件、農業に対するイメージなどの意識調査を行うほか、改めて、需要側である受入れ農家の作業内容や時期、求める人材などの実態を把握し、各事業所や農業団体と課題や情報を共有しながら労働力不足の解消に努めたいと考えています。【農政部長】
(6)自殺予防対策
質問
自殺者はその前段階で鬱病などの精神疾患を発症しているため、他都市では、内科のかかりつけ医と精神科医が連携し、鬱病に対する早期発見、早期治療につなげている事例があります。
本市は医療機関が集積していることから、その優位性を生かした取組ができると思いますが、見解を聞かせてください。
回答
保健所では、市民からの心の相談に日々対応していますが、その中で、専門医への受診を望むものの、初診までの期間が長いことによる不安の声を聞くことがあります。ご指摘があった他都市の事例も参考にしながら、本市における医療機関相互の連携がどのように行われているのか現状について確認していきます。
その上で、鬱病の早期発見、早期治療、更には自殺予防に効果のある医療機関連携の在り方を検討していくため、関係機関との協議を経て課題を整理し、本市の実情に合った仕組みを検討したいと考えています。【保健所長】
(7)緑が丘地域活動センター内の図書コーナー
質問
緑が丘図書コーナーは寄贈図書の本棚と自動車文庫の二つの要素で構成され、地域ボランティアによる運営となりますが、教育委員会としては、どのような課題を想定し、バックアップするのか聞かせてください。
回答
オープンしてから当分の間は、図書館職員が主体となって図書コーナーの運営を行い、地域ボランティアの方には、主に子ども向けのイベント等に協力いただくことを想定しています。
緑が丘図書コーナーの運営を安定的な軌道に乗せることを優先しつつ、運営を行う中で様々なご意見を頂きながら、課題があった際には課題解決の手法について図書館としてもできる限りのバックアップを行い、さらに、魅力あるイベントの実施等も含めた運営の在り方を検討したいと考えています。【社会教育部長】
(8)マイナンバーカードの普及の取組
質問
本年6月から住民票等のコンビニ交付が始まり、一方では9月末で自動交付機が廃止となります。マイナンバーカードの交付割合は10%台となっていますが、普及に向けた取組状況について、聞かせてください。
回答
コンビニ交付が円滑に運用されることを通して、マイナンバーカードが安全で便利なものと市民に実感していただくことが大事だと考えています。
マイナンバーカードの普及に向けては、令和3年3月から予定されている健康保険証としての利用等を広報するポスターなどが、今後、国から配布されるほか、幅広い世代に向けて多様な広報が実施されることになっています。
本市としても、国の広報を活用するとともに、カードの機能に関するこれまでの広報活動を継続するほか、本人確認書類として使えるなどの利点について本市の配布文書等に広く掲載することなどを検討して普及に取り組み、市民の利便性向上に努めます。【行政改革担当部長】
(9)終活*への支援
質問
亡くなられた方に相続人がいなかったり、相続放棄などで放置される土地や建物の問題は、空き家の増加や環境悪化にもつながります。このような事態を少なくするため、生前から意識的に考えてもらうための啓発や、いわゆる終活と呼ばれる活動を支援する取組を強化していくべきと考えますが、市の見解を聞かせてください。
*就活:葬儀や墓など人生の終焉に向けての事前準備のほか、自分を見つめ今をよりよく、自分らしく生きる活動のこと。
回答
平素から、いざというときへの準備や心構えの意識を高め、自分の希望を形にしておくことは、家族や周囲の方々の負担軽減につながるとともに、財産を含め、病気治療や介護の面においても、今後の人生を自分らしく生きていくことにつながるものと認識しています。
終活への支援については、今後、どのような取組が適切であり、具体的に何ができるのか、他都市の事例等も参考にしながら、優先度や財源等も含め検討するほか、財産の問題だけではなく、広く、自分らしい暮らしを人生の最期まで送ることができる取組を進めたいと考えています。【保険制度担当部長】
(10)次期清掃工場の水没の危険性
質問
次期清掃工場の建設予定地となっている地域は、旭川市洪水ハザードマップでは、家屋倒壊等氾濫想定区域に指定されています。最近の温暖化による豪雨や台風による大雨で、洪水が発生し水没する危険性をどのように想定して決定したのでしょうか。
回答
次期清掃工場については、現在の清掃工場と同じ敷地内で整備することを基本としています。旭川市洪水ハザードマップでは、おおむね1千年に1回起こる大雨により河川が氾濫した場合には、水深3メートル以上5メートル未満の浸水が想定されている地域に区分されており、また、北海道開発局の調査でも最大水深が4.85メートルと予測されています。
このことを踏まえ、清掃工場整備基本構想では、災害時にも安定したごみの処理を維持するために、電気室やごみを投入するプラットホームなどを最大水深より上に配置し、防水扉を設置するなど、施設の浸水対策を図ることで対応することにしています。【環境部長】
(11)日韓問題における本市への影響
質問
本年に開催が予定されていた水原市との姉妹都市提携30周年記念事業は、一部を除き、大半が中止になりました。韓国との関係性をどのように是正するのか、国に対する要望など、声を上げるとしたらどのようなことが考えられるのか、市の見解を伺います。
回答
現在、日韓両国には困難な課題があり、本市を含め、全国的に地域間交流に様々な影響を与えている状況にあると認識しています。
水原市との交流については、水原市側の事情により行われていない事業も幾つかありますが、常々、国同士の関係と自治体や市民の交流とは別であると考えており、これからも両市、両市民にとって有益な未来志向で互いに関係性を築いていくことが大切だと考えています。
今後は、韓国や水原市から多くの方に旭川に来ていただけるよう、国や道、自治体国際化協会などの関係機関との連携を更に図り、水原市に対しては、市民レベル、民間レベルでの相互の信頼に基づく交流の大切さを伝えながら、交流を継続していきます。【市長】
(12)JRの利用促進
質問
JR北海道で策定したアクションプランの具体的取組として駅舎内及び駅前広場のイベント活用による賑わいの創出があります。例えば旭川駅舎内でフリーマーケットを開催するなど市民が集まれるイベントを開催してほしいと考えますが、JRとの協議は行っていますか。
回答
7月7日から16日まで、旭川駅構内で自由に演奏できる駅ピアノあさひかわを試験的に実施しました。このような駅に来てもらう目的づくりを重ねることで、市民の鉄道への関心を高め、鉄道利用のきっかけになるものと考えています。
広い空間を持つ旭川駅舎は、様々なイベントが開催可能と考えており、アクションプランに基づく利用促進の取組として、市民が直接参加し、主役となるようなイベントが開催できるよう、現在、JR北海道と協議を進めています。【地域振興部長】
(13)認知症サポーター養成講座
質問
現在、要請があった場合に団体を対象に認知症サポーター養成講座を実施しているようですが、若年性認知症について市民の方に多く知ってもらうためにも、個人を対象とした講座を開設することはできませんか。
回答
平成28年度までは、個人でも参加できる認知症サポーター養成講座を年1回程度開催していましたが、会社、学校、地域の団体等からの講座開催要請が多くあることや、講座の講師役となるキャラバンメイトへの負担などを考慮し、近年は団体を対象に開催してきました。
団体に所属していない市民からの要請もあるため、今後は、個人でも受講可能な形式の認知症サポーター養成講座の実施について検討していきます。【保険制度担当部長】