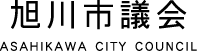令和6年度市民と議会の意見交換会報告書-5
旭川市の救急医療体制について~持続可能な救急医療体制について~ (総務班)
意見交換の主な内容
市民
私の孫が重度障害者で、以前に何度か救急車にお世話になったことがあります。
毎回同じ救急車の方が来るわけではないので、来るたびに孫の状態を事細かく説明しなくてはなりませんでした。
時間がとても無駄になるのではないか、いち早く運んでいただきたいという思いがあるのですが、情報共有を毎回しなくてはならないということなので、個人情報の問題など様々あるかとは思いますが、重度障害者の場合は情報をデータ化して、こういう子がいるということを把握して来てもらったらスムーズにいくのではないかと感じました。
議員
私も先日、救急車で運ばれた方が市立病院に情報があるはずなのにもう1回同じことを聞かれたというような話を聞いたことがあります。
名前や年齢などは、患者の取り違いがないように、電話だとか口頭で確認しなければならないと思いますが、今、マイナンバーカードが保険証の代わりになってきています。
医療機関で読み取れば、その患者さんの情報がすぐに出てくるような状況にもなっていると思います。
今後、その情報管理が進んでくると、救急車でどれだけ扱えるかというハードルはあるかと思いますが、こういった利用者がいるということを把握しやすくすることはできていくのではないかと思っています。
旭川の医療体制の中で、救急車にマイナンバーカードの読取装置を配備するだとか、ここでお約束はできないのですが、おっしゃったように、よく利用される方の情報伝達をしっかりした方がいいのではないかということで、受け止めさせていただきます。
市民
救急車の情報管理ということだと思いますが、この関係でマイナンバーカードが搭載されれば情報が早く行くというのは良いと思います。
同じように過去にあったのですが、どこの病院に行っていますかとか、どこで対応していますかとかを救急隊にまた説明しなくてはならないということもありますし、私の妻の母が認知症なのですが、病院がたらい回しになったことがあったので、認知症の対応については病院の方が大変なのか、医者が必要なのか、人員不足ということがあるのかもしれないですが、市としてはどのようにバックアップしていくのか、医療体制の先生方の増員や救急班の増員など、そういうことの展望としてどのようなお考えがあるのでしょうか。
議員
意見交換会でそのような御意見をたくさん承ることが多いのですが、我々は今回委員会のメンバーとして参加しており、市としてこうしますということは、この場で申し上げることはできませんので、それを踏まえた回答ということで受け取っていただきたいと思います。
議員
私たちは議員であり、その道の専門ではないので、なかなか明確な答えはないのですが、救急隊の方は応急処置ということで動いておられて、本来、医師の医療活動ということとはまた別に考えていかなければならないのだと思います。
かかりつけ医の情報と、急きょ駆けつけた救急隊員の間での連絡のやりとりということについては、先ほど話があったように、マイナンバーカードがこれから活用されていくのだと思いますが、どこまで個人情報が救急隊に流れるのかということは非常に難しい問題であると思います。
その辺りは議会としても一つの課題として、市の対応と個人の情報とがどこまで近くなるのか、今後協議していかなければならないと思います。
何度か救急車を呼んだことがありますが、なかなか病院が決まらない、質問がとても長くなる、救急車が動き出し病院へ向かうまでの時間が非常に長いと私自身も感じていますので、今後所管の部署と協議しながら、市としてできることにはどんなことがあるのかということを検討していきたいと考えています。
議員
だんだんと様々なものがICT化されており、地域によっては、実験的にAIを使ってどこの病院に行けるのかという実証実験を行っているところがあったりします。旭川市議会の中でも本会議や委員会でそういうものを活用して、たらい回しにならないようにということの議論は出てきているので、今後少しずつ最先端の技術を取り入れながら、変わっていくのではないかと思っています。
市民
高齢者福祉の現場で働いている者ですが、先ほど認知症という話もありましたが、高齢者の方が、不安や認知症の中で、119番や110番されるという事例を現場ではかなり目にします。
それが本当に必要な出動かどうかというと、かなり疑問であり、それが繰り返されることで、自宅での生活ができなくて、施設入所を考えるきっかけになるというようなことも見られています。
そういった高齢者をどう地域で守っていくか、担当のケアマネジャーを含め、地域包括ケアの中でどう見守っていくか、このひっ迫した救急体制に影響を与えないようにどう取り組んでいくのかということが今後必要になってくるのではないかと思います。現場の報告みたいな形になってしまうのですが、今後に期待したいと思います。
議員
超がつく高齢化社会が来ている段階だと思いますが、認知症の方も増えている中で、救急隊の対応が必要なものかどうかはなかなか分かりません。
搬送されて、医師の診断を受けて、そのときに軽症だったり重症だったりという判断がつくと思いますが、軽症事例を減らしていくことが今後求められていくのだと思います。
独居の高齢者がかなり多くなっている中で、先ほど地域の見守りという話が出ましたが、これが一つのキーワードなのではないかと思いますし、そこで救急体制を疲弊させない取組が必要だと思います。
見守り体制を強化していくことも一つの方法だと思いますが、プライバシーのことなども関係してくるので、なかなか明日からこうしますというように簡単にもいかないことなので、協議をしながらどこまで進めていけるのか、検討が必要だと思いました。
市民
ニュースの記事で、今年の6月1日から三重県の松阪市で、救急車で運ばれても入院に至らなかった場合には、費用を支払ってもらうという記事が出ていたと思います。
記事の最後は、普段と様子が違うときにはためらわずに119番通報をしてほしいとなっていたのですが、救急出動が重なることで、救急車が早期に患者のもとへ到着できないということで、助かるはずの命が助からなくて、早期治療ができなくなるといったことも考えられるようで、救急車の適正利用が必要と救急に携わっている方がおっしゃっているようなのですが、旭川市でも有料化するなどの議論はされているのでしょうか。
議員
この会の準備に当たって理事者と意見交換をする中で、実際にそのような自治体も出てきているという状況は把握していました。
しかし、おっしゃったとおり、お金がかかるからということで救急車を呼ぶのをためらわれて、その結果命が失われるということはあってはいけないと思います。なので、その辺も慎重に議論していかなければなりません。今、旭川市の中で有料化していこうという動きは特段出ていません。
今回、我々はなぜこのような意見交換会をやっているのかというと、やはり自助・共助・公助の中で、持続可能な医療体制を確立していかなければならないと思っており、今回の配付資料でも、こんな場合は呼びましょう、というように、細かく示せるものがあります。
普段から、こういうときは救急車を呼んだらいいということは知識として身につけていただいて、御自身が呼ぶか呼ばないかという判断をする際の参考にしていただいても構いませんし、この場に出てこられた方は、医療に対する探求心や勉強する気持ちを持っていらっしゃる方なので、是非周りの方にこういう場合は呼ぶべきだということを伝えていただければと、逆に我々のほうからもお願いさせていただきたいと思います。
議員
茨城県の方でもこういった事例があったようです。
救急車を呼んだら最も高い病院で1万3,000円ぐらい取られたということで、軽度な切り傷で呼んだ場合や虫刺されとか、そんなに症状がないような状況の場合でお金を取るということがあったということでした。もしかしたら少しずつ全国的に増えてきている状況ではあるのかと思いますが、まだ旭川市としてはそこまで至っていません。
市民
旭川市ではまだそんなにひっ迫していないという話ですが、実際は救急車の出動件数が平成元年から令和5年にかけて3倍に増えているという上昇原因は分析されているのでしょうか。
それに関わる財政の支出が増えていることの追及はどうされているのでしょうか。
議員
コンビニ受診も増えてきたところ、コロナ禍で受診控えがあって、一旦、谷間が来たけれどまた伸びてきているというところですが、今日のテーマでは、持続可能な救急医療体制を構築して、そのまま続けていくにはどうするのかというところがあります。
配付資料にあった鷹栖町や上川町は、救急医療体制を連携してやっているところでありますが、令和3年度から旭川大雪圏域連携中枢都市圏というものを、周辺8町とともに続けています。
このように鷹栖町や上川町だけではなく、周辺8町にも広げた上で、大きくなっている需要に応えていく。また、先ほど話があった、救急車を呼んだらお金を取られるというようなことがないように、大雪圏域でしっかりと連携しながら医療体制を構築していこうということも、急性期医療に関して周辺8町と連携を結んで融通し合おうというようなことができてきていますので、高いから救急車を呼ばないでおこう、灯油が高いから暖房を使わないでおこうというようなことになってはなりませんので、市議会としても、持続可能な医療体制の構築に向けてしっかりと議論を深めていかなければならないと思います。
先ほど話があった認知症の方であれば、例えば福井県の福井市では、かかりつけ医や投薬などの情報を集約するような救急医療情報キットを年配の方々にお配りして、これを救急隊が見れば情報共有できるということを行っています。
キットに記述するという作業を民生委員が行ったり、役所の方が行ったりということもあるのですが、自助努力で何としても命を守る救急体制を守っていかなければならないというのが議員全員の共通の認識だと思いますし、旭川市単独では難しいところは、周辺8町で融通し合いながらというところもあると思います。
是非皆さんとともに手を携えて、しっかりとこの先を考えていきたいです。
議員
平成元年から令和にかけて、3倍に増えるまでにその間30年ぐらい経過しています。
当然、その間に国の世代構成が変わってきており、高齢化率が高まり、超高齢化社会になっているということが、一つ要因にあるのと、先ほど話があったコンビニ受診といいますか、それほど症状が重くないのに何となく救急車を使ってしまうということが広まってしまっているという状況もあるかと思います。
実際に、令和2年の消防庁の統計では、救急搬送された半数が軽傷だったという統計もありますので、そこの意識をもう少し国や旭川市で市民の方と共有することがまずは大事なのではないかと思います。
その上で、それによって、本当に受診すべき人が控えてしまっては元も子もないので、我々も今回初めて知ったことがたくさんありますが、市としてもっと啓発・啓もうしていくことが大事だと思います。
消防の方々も必死で動いていますし、救急車の到着時間を見ると、この雪国の中で旭川市は全国と比べて早い年が何年もあります。
とても頑張っていらっしゃる方々がいるのに救急隊や警察の方がコンビニで御飯を買っていたらクレームが入るみたいな世の中ですから、許容できる部分、理解できる部分を増やしていかなければならないと思いました。
議員
3倍ぐらいに増えているということは、統計上見て分かることだと思います。
配付資料に、入電時間別搬送人員がありますが、8時から18時までの時間帯の搬送人員が多いということが書かれています。8時から18時は基本的に医療機関に受診をする時間と重なっていますので、自分の足で行けないという状況が背景にあると思います。
救急車を使うような場合もあるとは思いますが、そうではない方が自らの足で受診に行ける、例えば公共交通の充実などの部分も必要になってくると思います。
夜中に急に不安になったとかで、受診したいということもあるかと思いますが、まずは医療機関がやっているときに足を運べるような環境をつくっていくことが、救急搬送を減らしていく一つの方法ではないかと思いました。
議員
私もここ10年以内に4回か5回ぐらい救急車を呼んでいますが、市民の方は呼んだらすぐに救急車が来ると思っている方が多いです。
目の前で自転車と車がぶつかって、歩行者の方が先に電話してくれたので良かったのですが、そこで救急車がすぐに来ないことに困っており、「いや、そんなにすぐ来ないですよ」という話で、自転車の方の対応などをしましたが、結構知らない方が多いです。
救急医療体制とか、救急車がどういう流れで来るとか、そういうことも今後様々な形で市民の方に伝えていくことも私たち議員の責務の一つだと思いますし、市の方でもしっかりと市民の方に伝えていくことも、仕事であると思いますので、今後様々な議論を踏まえながら様々な方に知っていただくことにも努めていきたいと思っています。
市民
こういった場もすごく有意義に感じているのですが、救急の現場で困っていることなども市民に教えていただければ、私たちが生活していく中で何に気をつけたらいいのか、路上駐車も大変だと思いますが、現場がどういうことに困っているのか、我々がどういうことを求めているのかを意見交換できると、更に充実するのではないかと思いました。
議員
今後市民として協力できることは何かということの一つとして、昨日、市民委員会の交通部長になっているので、パトライトで交差点に立って交通指導したのですが、その間に救急車が2台通り過ぎました。その際の車の動きを見ると、昔は救急車が来たときには一斉に隊列を端のほうに寄せるマナーで進んでいたと思いますが、見ている限りスムーズにいかず、救急車がなかなか抜けていけないというような状況が見られました。
市民として、命に関わることであるという意識を持って、どのようにして救急車を通そうかということを、それぞれ考えていかなければならないと思いました。
議員
救急車を呼んだことや乗ったことがあるという方は結構いらっしゃいますね。
私たちも、これから市民サービスとしてこうやってほしいとか、何か問題点や課題点があれば、市の方に伝えて直してもらったり、取り組んでもらいたいということを伝えていくので、皆さんが救急車に乗ったり呼んだりしたときに、こういう不具合だとか、もっとこうだったらよかったのにという御意見があればお聞きできればと思うのですが、何かそういった経験で感じたことはございませんか。
市民
救急車は早く来ていただいたのですが、搬送先が見つからないことがありました。
私の母なのですが、救急車に乗って1時間、年末ということでたくさん重なっていたところがあったと思いますが、時間がかかり過ぎ、母がトイレに行きたいということで1回家に戻って、それから搬送されたという経緯がありました。
消防隊の方々は雪の中早急に駆けつけてくださる中で、受入先の準備等が足りなくて、その時は外科だったのですが、内科の当番医でようやく受け入れていただいて、すぐけい椎骨折だったと分かって手術になったのですが、本人も心配ですし、我々家族も非常に心配なところがあったので、そこをスムーズにいく形にしていただきたい。
搬送先への時間については、救急車がとまっていると他の案件に影響があると思うので、うまくやっていただけるような、指示センターの統一や病院との連携ということができれば良いと思いました。
市民
旭川にはドクターヘリがあると思います。
先日、旭川赤十字病院に行ってドクターヘリを見てきたのですが、すごく良いことだと思うので、財政面では結構費用もかかると伺ったのですが、命がかかっていることなので、是非とも続けていただきたいと思いました。
議員
ドクターヘリは、車だと数時間かかるようなところで、旭川でなければ診療を受けられないような事例でも、10分とか20分ぐらいで到着するということです。
旭川は旭川市だけの医療ではなく、上川中部や北部など道北に行くと医療機関が少なく総合病院や大きな病院がない中での役割があります。日本の人口減少社会において医療機関の問題もある中で、救える命という部分に対してしっかりとドクターヘリで対応できるような体制が必要だと思いました。
国の在り方の部分にも関わって、ドクターヘリについて我々もしっかりと勉強していかなければならないと思いました。
議員
興部町の山あいの酪農家をやっているところの方が農業用機械に挟まれてしまい、ドクターヘリで旭川へ運ばれたことがありました。1分1秒争う生死に関わる状態のときに、速やかに医療機関に届けられるのがドクターヘリです。ドクターヘリがなかったらその人は助からなかったのだろうと思っています。
今、我々の旭川にある当たり前の医療体制というのは、オホーツクや宗谷でいうと全然当たり前ではなくて、斜里町では子どもが産めないのです。出産で網走まで1時間ぐらい車を走らせなければいけないので、予定より早く破水すると緊急で隣町どころではなく遠くまで走っていかなければなりません。オホーツクでは北見市が医療の中核都市ということで、そこまでどれだけ救急車を早く走らせられるかということで、高規格道路の予算がついたりしています。
旭川も道北や道東、オホーツクの医療体制を担う中で、中核機関の砦としての機能も備えながらも、医療体制はひっ迫しています。夜間の診療体制や当番の体制を整えるだけでも、医者と看護師にその時間まで残ってもらわなければならず、給料も払わなければいけない。その中でどれぐらいの人が夜間診療に来てくれたか。夜間診療は診療報酬が少し高いのですが、1人、2人しか来ないのにみんなのために病院を空けている。担い手にも大変負担があり、医療体制も人が少なくなってくる中、決して明るいとは言えません。
だからこそ、我々も救急医療の使い方や救急車の呼び方などをしっかりと考えていかなければいけないと思います。
議員
議員になってから3回救急車で運ばれています。低血糖症で血糖値が下がると目の前が真っ暗になって倒れてしまうのです。あめ玉でもなめるとすぐに回復するのですが、周りの人たちがびっくりして、救急車を呼んでしまうのです。運ばれたときに救急隊の人が、私が議員だということを分かっていて、要は私に「新しいのに変えてくださいよ」というような雰囲気で、「あまり乗り心地よくないでしょう」と言ってくるので、お世話になった後、消防長に「どれぐらいの年数なの」と聞くと「もう納車後13年が経過して更新時期に来ているのですけどまだ使っています」と言われました。
夏場で普通に運転していても乗り心地が悪いので、冬道だったらもっと患者さんが不便というか気持ち悪い思いをするのではないかなと思い、消防長に「すぐ予算つけて交換してあげてください」と言ったら、次の年から交換されたという報告を受けましたので、議会としてできる形の一つの例をお話しさせていただきました。
ドクターヘリに関しては、旭川赤十字病院から発進しますが、格納庫は旭川医科大学にあり、年間400件以上の出動要請があります。最初は北海道の案件で釧路市に1機置く予定だったのですが、十数年前に旭川市と釧路市に配備してもらい、遠くの場合は途中で給油して、稚内や紋別、網走方面に対応できるようなシステムになっています。
本当に急を要する、大けがや生死に関わるときに利用するのがドクターヘリということですが、今はドクターカーというものもあり、救急体制の中でこれから取りそろえていくのではないかと思っています。
議員
私も救急車に乗った経験が3回ありますが、やはり冬道で乗ったときには、こんなに乗り心地が悪いのかと思いました。母親の付添いで乗ったのですが、横の席に乗っていても頭が天井にぶつかるくらい揺れて、これは患者さんも大変だなと感じました。
今、議員が話したことについても、議員としてやれることの一つなのだということは勉強になりました。
今日は救急のことなので、救急車とか救急隊の話がメインになってきましたが、救急車が来てから病院に行くまでの間の時間が長くなっている傾向は、医師や医療関係の事情もあるのではないかと思います。当番医を受ける病院が少なくなってきていることや、医師の高齢化、医師の働き方等が大きな問題となって、なかなか受入先が見つからないということが一つの原因であると思います。
そのような中で、私たち議員はなかなか力が発揮できないところではあるのですが、課題を旭川市医師会とも共有する機会を持ちながら、旭川市にとって何ができるのか、救急の方と医療体制の方ともう少しコミュニケーションを取りながら進めていくべきだと今日の意見交換会を通じて感じました。
まとめ
総務常任委員会の委員で構成する総務班では「旭川市の救急医療体制について~持続可能な救急医療体制に向けて~」をテーマに市民と議会の意見交換会を開催し、皆様から貴重な御意見を頂戴いたしました。
総務常任委員会としては、旭川市消防本部管轄の救急業務が所管ですが、救急車の搬送先や、一次、二次、三次救急、夜間対応などにも範囲が及ぶということで、旭川市医師会や保健所の協力も得て勉強会を行い、委員会としても更に理解を深めることができました。
当日は参加者より、救急車を呼んだ時に持病や障害について説明する手間を省くために救急隊員と病院で患者情報を共有してほしいということや、搬送先が見つからないときにたらい回しにしないよう市でもバックアップしてほしいということ、高齢者が不安や認知症で119番通報し、周囲に影響を与えてしまうことについて地域でも見守り体制を構築する必要があるのではないか等の御意見を頂戴いたしました。
持続可能な医療体制を構築していくため、頂いた御意見を参考にしながら、今後の議論を行ってまいります。

(会場の様子)