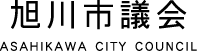アンケート集計結果
自由記載欄は、一部抜粋・要約をしている場合があります。
1 あなたの性別
あなたの性別
| 性別 |
経済建設班 |
子育て文教班 |
総務班 |
民生班 |
合計 |
| 男性 |
6 |
4 |
5 |
8 |
23 |
| 女性 |
2 |
5 |
7 |
10 |
24 |
| 未回答 |
0 |
1 |
0 |
2 |
3 |
2 あなたの年齢
あなたの年齢
| 年齢 |
経済建設班 |
子育て文教班 |
総務班 |
民生班 |
合計 |
| 10代 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
| 20代 |
0 |
2 |
0 |
3 |
5 |
| 30代 |
0 |
1 |
1 |
2 |
4 |
| 40代 |
0 |
1 |
1 |
5 |
7 |
| 50代 |
2 |
1 |
3 |
4 |
10 |
| 60代 |
3 |
3 |
6 |
2 |
14 |
| 70代 |
1 |
1 |
0 |
4 |
6 |
| 80代 |
1 |
0 |
1 |
0 |
2 |
| 90代以上 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 未回答 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
3 意見交換会の開催を、何を通じて知りましたか。
意見交換会の開催を、何を通じて知りましたか。
| 認知方法 |
経済建設班 |
子育て文教班 |
総務班 |
民生班 |
合計 |
| 市議会だより |
1 |
2 |
2 |
0 |
3 |
| こうほう旭川市民 |
3 |
1 |
5 |
3 |
12 |
| ホームページ |
1 |
0 |
1 |
0 |
2 |
| まなびネット |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| チラシ・ポスター |
2 |
1 |
3 |
5 |
11 |
| 新聞・雑誌 |
0 |
1 |
1 |
2 |
4 |
| 市民委員会・町内会 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| テーマ関連団体 |
2 |
5 |
0 |
3 |
10 |
| フェイスブック等 |
0 |
1 |
2 |
1 |
4 |
| その他 |
2 |
3 |
4 |
11 |
20 |
4 本日開催した場所はいかがでしたか。
本日開催した場所はいかがでしたか。
| 会場の感想 |
経済建設班 |
子育て文教班 |
総務班 |
民生班 |
合計 |
| 大変良かった |
2 |
5 |
4 |
4 |
15 |
| 良かった |
6 |
4 |
5 |
13 |
28 |
| 良くなかった |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| まったく良くなかった |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
| どちらともいえない |
0 |
1 |
1 |
2 |
4 |
| 未回答 |
0 |
0 |
2 |
0 |
2 |
会場について特に意見等がありましたらお書きください。(主な意見)
市役所議場
(意見無し)
市役所第1委員会室
- 場所は市役所で良い!バスで来られるため。
- 議場がある本庁がよかった。
- 緊張しやすい場所だったが、「市民と議会…」ということで仕方ないと思いました。
- 対面形式だと戦っている雰囲気がある。意見交換会ということでは円形の座席が良いのではないか。
- 普段は入れない場所なので、貴重な経験になりました。
- 駐車場代をもっと安くしてください!
旭川市障害者福祉センター(おぴった)
- 場所は良いと思いましたが空間作りに改善の余地はあると思いました。議員と市民の垣根を超えた活発な意見交換を狙うなら、議員vs市民の構図のような配置ではなく、例えば小グループをいくつか作ったり全体を円のように配置するなどの工夫があるともっと話しやすいと思いました。
- 福祉センターで行ったため福祉の話が多かった気がします。もう少しいろいろな角度からの回答が聞ければよかったとおもいます。
- おぴったは障がい者福祉のための施設。「インクルーシブ」という広いテーマを取り扱う今回は、市役所の方がよかったのではないか。チラシに車いす利用者のイラストが使用されている点も気になった。
- 場所は問題ありませんが、施設の音響設備は更新した方が良いと思います。
5 本日は議員と意見交換することができましたか。
本日は議員と意見交換することができましたか。
| 議員との意見交換 |
経済建設班 |
子育て文教班 |
総務班 |
民生班 |
合計 |
| 十分できたと思う |
0 |
0 |
1 |
1 |
2 |
| できた方だと思う |
2 |
5 |
7 |
8 |
22 |
| あまりできなかった |
2 |
3 |
1 |
3 |
9 |
| 発言する機会がなかった |
1 |
1 |
1 |
4 |
7 |
| その他 |
2 |
1 |
1 |
1 |
5 |
| 未回答 |
1 |
0 |
1/td> |
3/td> |
5 |
6 次回の意見交換会も参加してみたいですか。
次回の意見交換会も参加してみたいですか。
| 次回の参加 |
経済建設班 |
子育て文教班 |
総務班 |
民生班 |
合計 |
| ぜひ参加したい |
0 |
4 |
3 |
4 |
11 |
| 機会があれば参加したい |
6 |
5 |
8 |
12 |
31 |
| あまり参加したくない |
1 |
0 |
0 |
2 |
3 |
| 参加したくない |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| どちらともいえない |
1 |
1 |
1 |
2 |
5 |
| 未回答 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 今後設定してほしいテーマや、本日の意見交換会に対する意見や感想などを、お書きください。(主な意見:各テーマ別)
経済建設班(11月1日)
主な意見
- 冬の時期に毎年旭川市で発生する雪の問題があります。前の冬の除雪の状況を経験し、車を運転する者も歩く者も辛いものがありました。住み良い旭川市であります様、協力したいです。
- 中心市街地活性化が大事。新文化会館だけでは活性化は難しい。
- 市政に反映させるためにも、今回話し合ったことを1回限りにせず、今後も継続して内容を深めていく努力を議員に求めていきたい。
- もっと参加者が多い方が様々な意見があると思います。
意見を求めるのなら、SNSでも参加できる仕組みがあれば良い。
広報あさひばしの有効活用やライナー等の活用も。
今後設定してほしいテーマ
(記載なし)
子育て文教班(11月7日)
主な意見
- もっと多くの方が参加して1日も早く改善されるのを期待します。
- 参加者の皆様からの意見がとても良かったです。できることをすぐやっていきたいですね。
- 地域づくりについて考え意見を交換していきたいと思います。
- 言いっぱなしになるのかな? 子どもたちの切羽つまったSOSを聞いてほしい。子ども総合相談センターの機能はゼロですか?
- 議員の皆様からも市へ働きかけをお願いしたいことがたくさんあります。市職員、行政、市政を動かせる、働きかけられるのは、市民の代表である市議さんなのですから。
- 意見交換というより発表会みたいでしたが、自分たちの他の団体の話など聞けて良かったです。
- 市議会議員の皆様とお話しすることがないので、大変貴重な時間になりました。また学生にも関わらずお心遣いいただきました。
提案ですが、小中学生と高校生、大学生の交流の場を団体主体だけでなく、行政主体でも行って欲しいです。学生団体では費用や責任の面から学生だけでできることはとても限られているいるので、行政がそのような企画を推進していただけると良いです。
中学生と高校生など年齢の近いもの同士で交流をすることで、大人に言えない様な子どもの悩みを学生が引き出せるのではないかと思いました。活動を市内・市外にも発信するべく旭川市の公式YouTubeチャンネルやSNSを駆使したデジタル戦略を進めていく必要があります。
交流機会を増やしても、根本的にヤングケアラーなどの子供達を守らなければ負のサイクルが続いていくだけなので、まずは子供の身体的・精神的な負担が減るようなシステムを構築していくことを第一に、子ども食堂やプレーパークなどの子供たちが生活しやすい環境づくりを進めていくべきだと思います。
- 旭川の子供たちがより健全に成長する為に、行政がすべき事は何か。子供・若者の貧困、非行関連問題について、市を挙げて対策を計画し、実行しよう会〜自分達は何が出来て、賛同者、協力者をいかに増やすか、既成組織には何を求め、何時までにどう実現させられるのかを考え、行動しましょう会〜を即刻開催してください!
今後設定してほしいテーマ
総務班(11月14日)
主な意見
- 子育て文教班のような教育の在り方について、経済的な観点からいかがでしょうか。
- 超高齢化社会で、独居の人が暮らしやすい様に。
- 改めて、消防の救急活動を知る事ができました。市民、若い世代にも活動内容を伝えてほしいと思いました。また、今後の救急医療体制DXも期待します。応援しています。
- 出席している市議の態度が気になりました。背もたれによしかかり、目をつむっている方が居ました。
今後設定してほしいテーマ
- 高齢者による多頭飼育崩壊について
- 野良猫、保護猫の現状について
- 重度障がい者の緊急預かり支援について
- 総合体育館~陸上競技場 再開発
- 買物公園通の古いビル開発の今後
- 認知症の対応(予防)・健康寿命・健幸アプリの対応と展望
民生班(11月15日)
主な意見
- 質問させていただいたら4名の市議さんが一生懸命答えてくださいました。
- 要約筆記はパワーポイントで作成した大まかな下地資料があった方が見やすいのでは。
発言できませんでしたが、様々な支援や相談窓口があっても、それをどこで知れるか、情報を受け取れるかが大事だと思いました。わかりやすく告知されてること、窓口に行きやすいことの対策があると嬉しい。
- テーマが多く深掘りは嬉しいが、一問一答は物足りなさも感じました。ただこうした機会を真摯に設けている議会に敬意を表します。
- 議員の方と参加者がもう少し話せる時間がほしい。
- 要約者がいるのに早く話したりすることもあって、市議の方は伝える為の工夫をしてほしいです。盲ろう者介助員制度の話をしたかったのですが残念です。
- 障がいを持っている方の働く場をもっと増やしてほしい。
- 意見交換という狙いなのであれば、一問一答形式というよりも、市民と議員が小グループをいくつか作って、テーマに対してみんなで話すような形式でも良いのではと思います。
- 市民の声を直接伝えられる機会はとても良いと思いました。しかし回答が長すぎると感じた場面もあり、市民の意見を聞くことが一番重要であるので、長さや簡潔さに気をつけて発言して欲しかったです。
- 議員の話す時間が長すぎる。市民の声を聞くことに注力すべき。直接電話が来た件など稀な事例を紹介していたが、公的な場で市民の意見を直接聞く機会をもっと大事にした方がよい。市民は、無難な回答ではなく政策での応答を求めている。
また、議員の発言機会は平等にすべき。若手や女性議員の発言回数が少なかったと思われる。誰に何の話を振るのか決めておくべき。テーマに関して回答の技量のない議員が目立った。市民はそれぞれ当事者性があるので、同じ熱量で答えることは難しくても、よく勉強してほしい。
意見交換会のテーマのサイズ感が異なることも気になった。他の班と比べて「インクルーシブ」は急に広範なテーマで、議論の焦点が定まらない。その中でも何について話すのかを決めることが望ましい。インクルーシブだけで4回開催してもよかったように思う。
旭川市規模で約40名の参加者は少ない。広報に力を入れた方がよい。
仕事を持っている人は日中や平日夜の参加は困難。開催日時についても再度検討してもらいたい。
-
- 冒頭に一人3分でという案内がされていたが、守らない議員がおり、進行役も注意しなかった。何度も発言していたため市民が話す時間に影響を与えている。
- 虐待加害者となった女性がマイクを渡されたとき、「名乗らなければなりませんか?」との問いにマイクを渡した方が「できればお願いします」と言い、実名であの内容を話していた。最初に発言のルールをアナウンスし、特にプライバシーにかかわる話については名乗らなくてもよいと伝えておくべきと考える。また、進行役もその人の名前を何度も繰り返したのも問題であったし、本人が望んで名乗ってもいないのに「名乗っていただき勇気があると思います」といった的外れのコメントをする議員もおり問題を感じた。
- 今回の会場形式は意見交換の場として適切かどうか一考していただきたい。議員と市民が対峙するような形で、しかも名前を名乗らせて発言をさせるような形は、強い動機付けがないと発言できない雰囲気を作り出しているし、発言時間も制限される。今回の会場は活発な議論がされていたが、ほかの会場はなかなかひどい状況であった。ワールドカフェ形式や、議員がいくつかのグループに分かれるなどして広く意見を聞く場として活用してほしい。
- 3に関連して、旭川市の人口に対し4回の会場参加のみの意見交換会は、「市民と議会の意見交換会」として実質的な機能を果たしているのかも考えてもらいたい。オンラインでの参加や回数設定なども検討すべきことだと思う。
- インクルーシブな小学校を始めたいと思っているという議員さんの言葉が嬉しかったです。一緒にいることが何より大切だということが身に染みています。一緒にいたら、障害を持っている子どもと過ごすことはお金も人もさほど必要ではないということがわかります。工夫すれば良いだけです。予算がない、人がいないと言っても何も始まりません。一緒に過ごしてみてほしいです。障害をお持ちのお子さんの保護者が「中学校の3年間一緒に過ごさせてもらった」とおっしゃいました。当たり前のことなのに。
- 教育、福祉分野の意見が多数を占めました。中でも教育にアプローチした質問、意見が多岐にわたり、課題の整理の必要性を感じました。インクルーシブな視点で現状の課題をいかに解決していくか。それと同じ視点で未来をどう創るか。
高校を卒業した方々のお話を聞くと、校則や学校文化、学校スタンダードの様な、“謎ルール”の中で生活し「できる」ことを強要され、できなければ『ごみキャラ』として措置され、排除される可能性を前提とした環境にあったことを語っていました。昨今旭川で起こっている子どもに関わる事件の数々も、教育の関わりの中にしっかりと課題がある事を認識し、先送りしないことが喫緊の課題であるように感じました。
教育の当事者は子どもたち。市政における各分野においても、専門家だけではなく当事者の意見を聞き、発言しやすい構造に調整すること、反映させることが必要です。教育は子どもに上から目線の制度設計になってしまいがちです。子どもという時代を生きる立派な権利の主体。対等な関係性の中で声を拾う仕組みの構築が急がれているように思えてなりません。事情を知ろうとする態度を大人が身につけ、子どもたちには障害の有無や他のマイノリティ性に関係なく、ごちゃまぜの中で生きることを体験するフルインクルーシブな教育環境を提供すること。「インクルーシブなまちづくり」の第一歩はここにあるように思いました。
今後のテーマ設定として「旭川らしいインクルーシブな教育づくり」の意見交換をしたいと思いました。
- ◇テーマについて
テーマは非常に良かったと思います。意見が活発に交わされ、認識を深めることができました。議論をもっと続けたいとも感じました。一方でテーマが限定されていると、テクニカルな話に終始し、知識がなければ議論に参加するハードルが高くなる場合があります。
日常生活は行政区分に縛られないため、特定の分野に限定すると議論の広がりや深みが損なわれる恐れがあります。以前の意見交換会ではその傾向を強く感じました。テクニカルな話題は業界団体や専門的な場で議論し、市民との意見交換では多様な意見を引き出せるテーマ設定が重要だと思います。
◇テーマの説明について
冒頭で議員の方がテーマ説明をされましたが、不十分だったと感じます。「ここに来ている人には説明は不要かと思います」といった発言があり、参加者を限定しすぎた態度に映り、「興味を持って来てみた」方には排他的に感じられたのではないでしょうか。
議員の方々から理解不足が見受けられる発言も多く、テーマの共有にはもっと時間をかけるべきだったと思います。
例1:夜間中学はインクルーシブの範囲ではない、との発言
説明の必要がないほどの理解不足。事前にインクルーシブについて基本的な説明を徹底するべきだったと考えます。また、「長年議員を務めてきたが、夜間中学について聞いたことがない」との発言もあり、事前に十分な勉強をして臨む必要があったと感じました。
例2:女性の相談窓口がないので議員に直接言ってほしい、との発言
「インクルーシブなまちづくり」を否定する態度だと感じました。現状を変えるための意見や取り組みを考えるべきであり、個別に議員に頼るのは限界があります。34人の議員でどれだけ個別相談を裁けるかを考えれば、そのやり方が持続可能でないことは明らかです。状況を改善するための議論が必要だったにもかかわらず、得意げに議員に頼むことをアドバイスしていた点に、インクルーシブへの理解不足を感じました。「議員が入らなければ適切な行政の行動が行われない」という点に、もっと意識を向ける必要があるのにそれを疑問に思わなかったのでしょうか。それ自体がインクルーシブなまちになっていないことを表しています。
◇運営について
冒頭で「1人3分程度」とのルールが示されましたが、議員自身がこれを守らない場面が目立ちました。また、進行役が十分に機能しておらず、特定の発言者が長時間発言することをコントロール出来ず、もっと多くの意見が出たはずなのにそれが進行のせいでうまく行われなかったように思います。
運営役は2人いたようですが、役職に関係なく適切な進行ができる人を選ぶべきだと感じました。全体の議論を円滑に進めるためにも、進行役の選定や運営方法について見直しが必要だと思います。
- 市議の皆さんがインクルーシブについて、どれだけ知識があり理解が有るのかを知りたくて参加しました。
率直に申し上げますと少し残念でした。夜間中学の存在を知らないのには驚きましたし、障害のある当事者の困り事や生活のしづらさを考えて頂いていたら、質問に対する市議の方々の返答がもう少しマシになったと思いました。
私は時々ですが車イスを使用していて様々な場面で不自由を感じています。手話の勉強中で聞こえない人達の長年の苦労話を聞いています。
旭川市は障害者には優しくない街だと他府県に旅行に行くと感じます。
もう少し寄り添った法案や条例の制定をお願いしたいと思います。
- インクルーシブ社会の実現のためには、他者への理解が欠かせないと感じており、私もそのためにはまず排除について気づくことが重要だと考え、このような機会を設けていただけることに感謝いたします。
一方で、相反する意見が述べにくい雰囲気もあります。マイノリティとは一般的に少数派という観点で言われますが、社会的弱者という意味もあり、障害者が暮らしやすいまちを作ることを善とした場合、相反する意見を唱えることは「悪=マイノリティ」になるということです。
インクルーシブ教育を具体例にとると、障害を持つ生徒が普通学級で学ぶことを善とする意見ばかりがクローズアップされ、不安や懸念する声が聴かれないという現状があります。
小学生の頃、障害がある生徒と同じ教室で学びましたが、事例にあったような良い関係は築けませんでしたし、障害との共存という考えは育まれなかったと思います。環境が整っていない中でのインクルーシブ教育の実施には反対です。
現在の小学校の学級をみると、昔よりハンディキャップを抱えた生徒が多いのに、支援員の数は不足し、先生方もデジタル化やいじめへの対応、非常識な保護者への対応に追われ困難度は高いと感じます。
学力低下も不安です。道内生徒の学力は内地と大きく乖離し、昔に比べ授業カリキュラムは前倒しされ、今以上に配慮が求められる生徒が増えると、授業について行けない生徒が増えます。高校、大学進学を機に道外へ出たときのライバルは全国区となります。
学校の勉強では足りず、中学へ上がると多くの学生が進学塾に通っています。経済的に余裕がある家庭は問題ありませんが、授業料は高く、格差は広がるばかりで、結局しわ寄せの場所が変わっただけのように見て取れます。
部活動の地域移行についても、子どもたちがプロフェッショナルな意識を持ってスポーツに取り組んでいるのではなく、共働き家庭では練習会場への送迎すらできず、道具を一式揃えてあげられる家庭も一握りで、地域移行による課題が多く、対応がされていません。
意見交換会のような場で声を挙げることができる方は社会的に少数かも知れませんが、マイノリティなのか、また、そのような意見だけをもって政策決定することが善なのかを改めて考えていただきたいです。検討では広い視野を持って、ディベートのような形で議論し進めていただきたいと願っております。
- 学校教育に関して
障がいがあっても普通学級で過ごすために補助の人員を配置できるように(人材、財源)
小さい時から障がいのある人が身近にいる事で理解が深まると思う。差別やいじめが起こらない様な支援も必要。
障がいがあって地域に暮らすためには理解してもらうことが必要で大切だと思っています。
本人が安心して外出できるまちづくりを目指すために当事者の現状を聞いて欲しい。
今後設定してほしいテーマ
- ノーマライゼーションな社会をテーマにしてくれると嬉しいです。
- 旭川街おこし企画会議
アンケート用紙<参考>
アンケート用紙