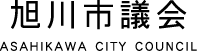令和6年度市民と議会の意見交換会報告書-6
インクルーシブなまちづくり(民生班)
意見交換の主な内容
市民
私は、障害のある当事者の活動や交流の場などで、ボランティア活動が活発にできたら良いと思っています。
当事者活動でも、私は、年に1度、地域のごみ拾いの活動をしておりますが、障害のある当事者が活動できる場がもっと盛んになることを期待しております。
議員
ボランティア、交流の場もそうなのですが、まちの中で障害者が当たり前に生きている、活動できるようにしていくというのがとても重要だと思うので、御意見をしっかりと受け止めたいと思います。
市民
私は障害児童の分離教育について非常に気になっております。
子どもはとても柔軟性を持っています。子ども時代、学生時代に、障害に限らず様々な特徴を持つ子ども同士が一緒になって過ごすことで、どんな人とも一緒に生きていくという価値観を身につけていくと思います。
私の息子は重度知的障害かつ自閉症ですが、普通学級で中学時代の3年間を過ごさせてもらいました。その中で友達や大人と関わり、一緒に過ごしていくのだというまなざしで、一緒に生きていくことを当たり前にします。どうやったら一緒に過ごしていけるのかという工夫やアイデアを、みんなで考えていけるのです。
合理的配慮といいますが、そんな言葉を知らなくても自然にそのような形をつくっていっている子どもたちを目の当たりにしてきました。
今、支援学校・支援学級と子どもが分離された場所に行くことが当たり前になっていますが、自分と違う性質を持っている人は別の場所に行くのだという価値観の植付けになるのではないかと思います。
どこから手をつけて良いのかということは難しいことですが、学校の在り方、普通学級をどうしていくかということ。また、みんなと一緒に過ごしたい、地域の学校で過ごしたい、普通学級で過ごしたいと希望を持つ本人、保護者の意見をしっかり聞いていくことが今できることだと思います。
私は相談を受ける立場として、残念ながら、そのような体制はできていないと感じています。
議員
よく分かります。大人になっていきなりみんな一緒に暮らしましょう、障害を持つ方も地域で一緒にという国の方針が示されたとしても、学校時代、幼少期の頃から分けられていますから、様々な方がいるという経験がないのだと思います。
分からないが故に、様々な不安を覚えるということもあると思いますので、どこから手をつけて良いか分からない、大変大きな問題です。
私は一つ一つのニーズを掘り起こして対応していく必要があると思っています。
入学前後の時点で、普通学級で学校生活を送るという意思をお持ちの保護者とお子様への対応を、議員としてしっかり見ていかなければなりません。それを学校教育のほうにも、要望していかなければいけないと感じました。
議員
入学するときに特別支援学級が前提になっているということがありますよね。
本人や家族が選び取っていく、権利としてどうしたいかを決められることがインクルーシブ教育だと思いますが、実際はなかなかそうなっていないと思います。
最終的には地域で暮らしますので、地域の中での多様性の中で暮らしていくことになります。学校だけ違うということがなかなか受け入れられない状況ではないかと思います。残念ながら、体制がまだとれていないのが実態です。
国のほうは中教審でインクルーシブ教育を進めますと言ってはいますが、それに見合う体制、特に教員の配置やお金は特につけていません。
そこを突破することが必要だと思いますし、国はもちろん、地域や自治体の中でもそういう声をしっかり上げながら、変えていくという努力を私たちも一緒に続けなければならないと思います。
市民
35年ぐらい通常学級で教諭をしています。3年間障害児の担任をさせていただきましたが、とても楽しかったです。入学前は絶対無理だとか、いじめられるとか、1人になってしまうのではないかとか、様々なマイナスイメージや意見がありましたが、3年間過ごした中で、毎日がとても充実していました。
心配されるようなことはなく、逆に良いことばかりがありました。今問題になっているいじめとか不登校の問題も、そういう子がクラスにいると、きっと解決されていくだろうと思っています。
一緒に育った生徒たちも、みんな優しくなり、彼も一緒に過ごす中で、1人の中学生だという意識になりました。最初は重度知的障害と言われていて、検査では3歳程度とされているのですが全然そんなこともなく、修学旅行も同じように参加しました。
もう少しで20歳になるのですが、仲間たちも本当にいっぱいいます。
今までのクラスも立派でしたが、障害のある子と関わる姿を見て、あの子も優しいのだなと理解して、それぞれの生徒が生き生きとしたクラスになりました。
市民
私は中学校まで障害を持っている子と一緒に過ごしていましたが、周りは彼について、やってもいないのにできないと言うことが多かったです。でもできることはいっぱいあって、一緒に学校生活を送っていて気づくことがいっぱいありました。
日常生活、学校生活自体が楽しかったです。イベントがなくても日常生活が楽しくて、受験シーズンとかぴりぴりした空気を和ませてくれました。彼は誰かの手助けがあって当たり前といった感じなのですが、私たちも誰かの助けはないとやっていけません。そのとき、誰かに助けてと素直に言える環境をつくってくれたと思っています。
市民
一緒にいることで様々なことに気がついて、私のクラスの子たちは、卒業する頃には、彼が障害者という意識は全くありませんでした。1回作文で彼をどう思うか書いてもらったことあるのですが、みんなが、「彼は彼じゃん」みたいな形で答えて、40人いたクラス全員が良いことばかりだったみたいなことを書いていました。
できないことはもちろんあるのですが、障害特性から来ることにはみんなとても優しく手伝ったりしますが、社会的に許されないことについては同じように注意しています。
結論としては小さい頃から一緒にいることで、当たり前になっていく。それが本当にインクルーシブなまちをつくっていく元だと思います。
ただ現実では障害がある方が学校に入ってくると、例えば車椅子一つにしても、大変だという話になります。
あちこちでお話ししても、お金もかかるし人も必要だと、最初に言われるのですが、そんなことばかりではないと思います。僕らも全くの素人でしたが、目の前に彼がいて、毎日一緒に過ごしていると様々なアイデアも生まれ、楽しい3年間でした。
議員
障害者でも活躍できる活動の場が、もっと必要だと、つくってほしいというお話がありました。また、分離をしない教育をしっかりと進めていくべきだというようなお話もありました。どれも大事なお話だと思います。
特に、このインクルーシブなまちづくりを進めていくためには、1人でも多くの市民がインクルーシブに対して、しっかりと理解を深めていくことが必要だと思います。
そういった意味では、様々な障害を持っている方や、LGBTといった性的なところに関してもしっかりと理解を進めていくということがと重要だと思います。また、若い年齢の方だけではなく、高齢化率35%を超える旭川市においては、高齢者にも住みやすいまちといったこともインクルーシブなまちづくりになっていると思っています。今日のような意見交換は非常に重要で、今この空間がインクルーシブな印象を受けました。
具体的に教育の場面は重要だと思っております。平成26年に、学力日本一と言われている秋田県東成瀬村に行政視察に行きました。人口2,500人ぐらいですが、幼稚園と小学校連携、一貫教育をやっており、小・中学校についても、一貫教育をやっていました。障害を持つ子どもたちも普通教室で一緒に学んでいる姿を実際に視察しました。
普通の教員のほかに、障害者を補助する先生も教室に入っているのですが、障害者から普通の子どもが学ぶことも多いというのを勉強させていただきましたし、障害を持っている方についても健常者から学ぶことも多く、お互い学びがある空間が東成瀬村の小・中学校にあったというのを思い返していました。
私たちも毎年、市長に対して予算や政策要望をしていますが、まずはこのインクルーシブ教育をモデル校1校から始めるのも大きな一歩ではないかと思っています。
こういった取組を地道にやりながら差別・排除されない、健常者も障害者も一緒に学んで高め合っていくモデル的な学校の取組が旭川市でも、まずは1校目を達成できれば良いと思います。微力ながら、取組を今後も続けていきたいと考えています。
市民
役所の受付などで、手話や筆記での対応をお願いしたときに、何となく面倒くさいような態度をされたことがあります。
福祉部局に行けば要約筆記も手話もしてくれるのですが、例えば公共施設に行ったときに、受入れがスムーズにいかないということがあるので、その辺りあたりをもう少し考えていただきたいと思います。
また、文化会館の建て替えのお話がありますが、私の母が一度文化会館に車椅子で行った時、車椅子のスペースはあるのですが、それが端の方なのです。
建て替えの際には、もう少し見晴らしの良い一角を、車椅子の人でも見られるようにしてほしいです。また、今は盲導犬と一緒に入れるような施設が少ないのではないかと思うので、きちんと考えることが必要だと思います。
もう一つ、エレベーターを設置するとした場合の話ですが、我々のように耳の聞こえない人が事故に遭ったときに連絡ができるよう、窓があるドアにしていただくなど、その辺のところも考えていただければと思います。
市民が一番関心を持っているのは、除雪の問題だと思います。健常者の人たちからの目線ではなく、障害者の目線というのも大事にしてほしいです。業者によっては結構ばらつきがあるという話も聞くので、除雪期間が終わった後に各町内からの意見をまとめて、検討するような催しがあっても良いのではないかと思います。
除雪についての討論会や説明会があるということは知っていますが、そういう場では、良いことも悪いこともなかなか言えないので、町内会単位でも、あるいは市民委員会単位でもやってもらえれば良いと思います。
私は、福祉というものは、地道にやっていくものなのだと思います。今できることをどうしたら良いかということから考えた場合に、例えば福祉日本一のまち旭川を目指すということをもっと宣伝して、身近なことをみんなやっていこうというような雰囲気をつくってほしいと思います。
議員
市役所の窓口の件も、エレベーターや盲導犬の件もそうですが、当事者の声をしっかり拾い上げていく仕組みが、これまで以上に重要になってきていると思います。
特に中途失聴者の皆様に関しては、例えばコロナのときに窓口にアクリル板ができたほか、皆さんマスクをしていて表情が読み取りにくいというところから、様々な御苦労もあったと聞いておりますし、悪意はないけれども、知られていなかったみたいなところではないかと思っているところです。
聴覚障害といっても聞こえる、聞こえないだけではなく、聞こえにくいという方もいることは、知られていないのではないかと、私も難聴対策関係のことをやっている中で、感じるところがありました。
当事者の皆さんの意見をしっかり汲み上げる仕組みというのが大事だと思います。頂いた御意見、ここにいる議員がこれからの活動に活かしていただきたいと思います。
除雪に関して障害者の目線ということでしたが、具体的に何かあれば教えていただいてもよろしいでしょうか。
市民
耳が聞こえないので、後ろから車が来ても分からないときがあります。
まして道は車1台分しか除雪されないので、車道と歩道が一緒です。
少しでも広くしてほしいというのが願望ですけれど、予算と言われたらもうそれでおしまいです。そういうことも頭に入れてほしいということです。
最後に、町内によってばらつきがあるのだとしたら、業者の人にきちんと言えば良いと思うのです。
そのためにも住民の意見を吸い上げる必要があるし、我々はそれをなかなか話せないから、市民委員会、市議会を通してでも、意見があったらまとめるというようなシステムを作ってほしいです。その意見をもとに次の年に検証や要望をするというようなことも良いのではないかと思います。
議員
しっかり受け止めさせていただきます。
市民
私は夜間中学の公立化を目指しているのですが、一番弱い人の立場に立って生きるということは全ての人が対等に大事にされる世界だと思っています。夜間中学のぬくもりは、年齢や国籍による差別は一切ない、発達障害の子どもが入ってきたら、おじいさんおばあさんのぬくもりの中で学べますから、全く差別やいじめが起こらない。おじいさんおばあさんが、人生経験が豊富だから、先生がたしなめられることもあって、すごく温かい世界です。
札幌にはようやく公立の夜間中学ができたのですが、2番目は旭川市だと思っています。教育委員会とお話をしたほか、公開講座などをして、様々な形で公立化を目指して市長にもお願いしているのですが、なかなか前進しないのはどうしてなのかと思っています。教育委員会に言っても聞いてはくれますけれども、具体的に一緒に動きましょうとはなりません。
市議会議員の方々に、夜間中学のことをどのように考えておられるのかということをお聞きしたいです。
市議会議員は旭川市民の模範であると思いますけれど、時々市議会を傍聴すると、足の引っ張り合いの言動が見えたりとか、後輩をいじめたりというところが見えてきて、襟を正さなければならないのではと思っています。
差別やいじめのない世界のために、いじめ防止条例を制定し旭川で取り組まれていますけれども、その前に、大人の差別いじめ防止条例を制定するほうが先なのではないかと思います。
大人がやっている陰湿な言動を見て、子どもに差別やいじめといったものがすり込まれて行動に出てきているだけで、子どものいじめ防止条例を作る前に大人の差別いじめ防止条例を制定していただきたいと思い、そのことも皆さんにお聞きしたいと思います。
議員
夜間中学校の対象者は何歳ぐらいですか。
市民
年齢は一切関係なく、80歳、90歳の人もいます。
戦後の混乱期の中で、文字や漢字すら書けないおじいさんおばあさんがおります。
そういう人たちが何度でもやり直せる、何度でも入りなおせるというところがあり、年齢差別は一切ないです。
議員
旭川の夜間中学の取組、当事者として学んでいる方も知っていますし、教師をやっている方もいらっしゃって、画期的な取組だと思いますので、応援していかなければならないと思っています。
今おっしゃったように戦後の混乱期で十分に学べなかったという人もいれば、30代の人で、当時いじめ等様々なことで学校に行けなかったという人、十分に理解して学ぶことができなかった人たちが通っているし、卒業しても何度も通い直す人がいます。
ずっとチャレンジし続けている姿が周りの人たちを変えていくような取組になっていますので、そういうことは応援していかなければなりません。
学校現場だけではなく、大人も含めて差別やいじめのない社会を作っていかなければいけないと思います。議会は議員同士足を引っ張り合っているのではないかという御指摘がありましたが、議会は議論の場であり、様々なことが起きますが、足の引っ張り合いやいじめのためにやっているわけではありません。市政に対し政策的な提言など、様々なものを反映させたいと思って頑張っていますので、これからも、多少侃々諤々(かんかんがくがく)やるかもしれませんが、頑張っていきたいと思います。
議員
私は正直、夜間中学というものは存じ上げておりません。
市議となって20年以上経つのですが、そのような声を聞いたのは今日が初めてで、驚きました。
札幌でようやくという話でしたが、どのぐらいの人数の方が、どんな学びをされているのかから勉強させていただいて、2番目は旭川市で実現できるか考えたいと思います。議員の中には分かっている方もいますので、私も続いていきたいと思います。
大人のいじめについては、議会で言えば、ハラスメントに対する仕組みをつくっていこうという動きもあります。
議員
私も夜間中学の札幌での取組は注目しておりました。
令和4年4月に北海道で初めてとなる公立の夜間中学校が設立されました。
様々な課題を超えて開学にこぎつけた札幌市議会の動きも活発でしたし、教育委員会の前向きな考え方もあったと思っております。
札幌の夜間中学校では、何らかの理由で中学校を卒業できなかった方が対象です。
外国籍で中学校を卒業していない、戦時中ということもあろうかと思いますが、年齢層は札幌でも様々なようです。いじめや不登校などによって学校に行けなかった、中学校を卒業できず、学び直したいと通われている若い方もいると聞いています。インクルーシブなまちづくりを進めていくためにも、学ぶべき年齢のときに学べなかった方に学ぶ機会を与える政策だと思っています。
一方で人材不足、財源といった現実的な課題もあります。課題があってなかなか前に進めない事情もあろうかと思っています。
普通学級の教員確保が困難な時代ですので、課題を含め、どれぐらいの規模、財源が必要なのかというところから調査をする必要があると思います。インクルーシブ教育のモデル的な取組から始めていくといった一歩をスムーズに出すのも、旭川市としての取組の事例になるかと思っていますので、積極的に検討していきたいと思います。
ハラスメントのお話がありましたが、議会ハラスメントについては、現在議会基本条例に追加しようという取組を進めております。
条文は、各会派一致の状態になっていますし、具体的なハラスメント防止の要綱につきましても、各規定が整理されており、防止要綱案が既に整っているところです。 仮に、事案が発生した場合、議長への申立てがあれば調査委員会を設置して、それがハラスメントになりうる事案なのか、実態を調査します。
事案がハラスメントと認定された場合、加害者となった議員に対して、制裁や氏名の公表なども可能にしていくような要綱を検討しているところです。
第4回定例会で全会一致に持っていきたいと考えているところですが、様々な意見があるので、応援のメッセージを送っていただきたいと思っています。
一足飛びに完璧な仕組みをつくって運用していくということは理想ではありますが、理想に到達するためには幾つかのハードルがありますので、できるところからやっていくのが私たちにできる方法だと思います。
ハラスメントのない議会をつくるためにも、引き続き、尽力していきたいと思います。
議員
公立の夜間中学の件ですが、私も今までそういったものがあるということを知りませんでした。札幌で前例があるということでしたので、どういった経緯でつくられて、どういった方々のニーズを満たしていくのか、どういう役割を担っていくのかということについてしっかり勉強しないといけないと感じたところです。
大人のいじめ。市議会のハラスメント防止の取組について説明がありましたが、一般論として「いじめ」という言葉の中には様々なものが含まれます。子どもの場合は悪いと思わずやっているような事例もあり、教育の枠組みの中で対応していかなければいけないと思いますが、大人のいじめに関しては厳しく、法に触れるようなことがあったらすぐにしかるべき機関が動くことも重要だと思います。
子どものいじめとは違って、大人はある程度悪いと分かっていて、バレないようにやる陰湿なケースもあり、職場や近所のいじめとか様々あると思います。
法的手続や、職場では労働基準監督署に相談しやすい環境、ブラック企業の問題になっている中で、徹底していかなければいけないと思います。
議員
夜間中学の話ですが、私はとても重要な話だと思いました。
不登校の子の学び直しや、戦後に学ぶことができなかった方が通われることもあって、教育からの排除の問題だと思ったからです。
学校や教育から排除されてしまった人たちの学ぶ権利を保障するという意味で、夜間中学校というのは大事であると思いますし、今後取組を進めるべきだと思っています。
財源や人材など課題があると思うのですが、市としてどこを大事にして優先していくかという優先順位の問題だと思っています。
学びの権利を保障するために、議会として何ができるのかということをきちんと考えていきたいと思います。
いじめやハラスメントは、学ぶことが重要だと思います。資料にも差別の背景として偏見、無理解、慣行、制度、背景、コミュニケーション不足などありますが、自分は絶対にいじめやハラスメントをしないとか、この人たちは絶対にしないだろうという思い込みも問題だと思います。自分がしてしまうかもしれないし、自分の発言も常に見直し、不断の努力を続けていかないと、なくせないものだと思っています。それが起きる背景や構造というものをきちんと学ぶこと。大人でも学び直しできることだと思いますし、子どもに対しても人権教育をもっと進めていくべきだと思います。
旭川市でそういった取組が先進的にできると良いと思います。
議員
夜間中学について勉強不足でまだ分からない部分が多かったです。
高齢者の方のデイサービスにも関わっていまして、通われている高齢者も勉強好きな方が結構多いのです。
デイサービスの中でも、脳トレ問題、数学の問題、漢字、パズル、英語などを積極的に学びたいという声が多いというのは、常に感じております。
インクルーシブともつながってくるのですが、職員の子どももそこに参加し、高齢者の方が子どもに積極的に教えてくれたり、関わってくれたりして、子どもが理解すると、高齢者も喜ぶのです。
インクルーシブという視点で考えたときには、そういう環境がすごく良いと強く認識しています。積極的に検討できるように努めてまいりたいと思います。
大人のいじめについてですが、旭川市もいじめの問題、更に最近暗いニュースもありましたので、大人が子どもの模範となることが必要だと思っています。
具体的に今すぐこうということは言えないのですが、社会として、市議会の立場として、大人として、積極的にそういう旭川市をつくっていきたいと思います。
議員
夜間中学校という言葉は知っていますが、公立化のイメージは持っていませんでした。
インクルーシブなまちをつくっていくためには、みんなで共有し合うということが一つだと思っています。知らなかった議員も知ることができて、そこに向き合うことができました。
また、夜間中学校をつくろうとしている方がいるということを知るだけでも、広がりになると思います。その声をどんどん大きくしていくことによって、空気を変えていくもとになってくると思います。
また、大人のいじめ防止条例のほうを制定するべきだというのはその通りだと思います。いじめをなくす条例を作ったからといっていじめがなくなるということはありません。道路交通法があっても交通事故がなくなるわけではありません。
なぜいじめが起きるのかを考える必要があると思います。教育現場では、いじめは世の中的には認められないからダメだと、「いじめちゃダメ」と言っているだけです。
だから大人でもいじめは起きる。それが今度ハラスメントだとかにも変わって、もっと言えば、あおり運転だとか自分本位の勝手な行動になっているのですが、もっと根本的なことをしっかりと考えていくことも重要だと思います。
夜間中学校というのは正にそのような学びの場にもなると思いますので、積極的に進めていく方向で考えていきたいと思います。
市民
子どもの貧困対策についてお話ししたいと思います。
私自身の経験なのですが、小学生のときに親が病気で働けず、いわゆるお金がない家庭の中で育ちました。その中で、周りの子どもと同じものが買えなくて、いじめられたこともあります。当時は家のことは恥ずかしくてなかなか助けを求められないという中で苦労をしておりました。
今、令和6年、こども家庭庁によると6人に1人の家庭が貧困状態にあるという調査結果もある状況です。貧困家庭の子どもということで、大学に行けない、チャンスをつかむことができないといった格差も実際にあると思います。
子どもの貧困の裏側には例えばネグレクト、DV、ハラスメントの問題など、様々な問題が潜んでいると思っています。
対策の一歩としてですが、沖縄県では子どもの貧困対策の推進に関する法律に基づいて貧困対策の調査を行っています。今後旭川市でも、生活の実態調査を行って、調査に基づく実態に即した対応・対策が必要だと思います。
貧困を家庭の中だけでどうにかしようということではなくて、関連機関が連携して支援ができるまちづくりが必要だと思います。様々な家庭が少しでも、親の経済力の影響をなるべく受けない、インクルーシブなまちになれば良いと思います。
議員
実態調査についてお話がありました。旭川市でも平成26年頃に教育委員会が主体となって、全小中学生とその保護者の2万人を超える範囲で子どもの実態調査を行ったことがあり、この中で様々な状況が見えてきました。
それから10年間くらい経過していますので、近年の物価高騰や燃油の高騰など、様々な情勢が変化してきている中で、再び調査をしていくことが求められると思います。
ヤングケアラーについても全国で問題視されているところですが、旭川市ではヤングケアラーの実態調査もまだやっていません。今年度、ヤングケアラーに対する支援事業を実施したのですが、事業費の執行率が2%程度という非常に残念な結果になりました。
何が課題だったのか、今回の議会で質疑をさせていただきました。ヤングケアラーについてもまず順序立てて、支援事業をいきなり予算化し、構築するのではなく、まず実態調査を行った上で、適切な事業構築を行う。今回は飛び越えて実施してしまったことが問題だったと思います。
子どもの生活に関わる実態調査と併せてヤングケアラーに関する実態調査をやることによって、様々な状況が見えてくるかと思いますので、10年前と同じ調査ではなくもう一歩踏み込んだ調査の中で、どこまで子どもの貧困の状態を酌み取ることができるのか。このようなことを市として挑戦していくべきだと思っておりますし、定例会の子育て支援部長の答弁からも、次年度に向けて、そのような調査の実施に向けた検討をしていきたいという答弁もありましたので、しっかりと推移を見守っていきたいと思います。
また、平成30年度から、非課税世帯を中心に高等教育の無償化が始まっています。まだまだ対象となる範囲が狭いのは承知していますが、高等教育の部分まで旭川市が財源確保するというのはかなりハードルの高い話だと思っていますので、旭川市独自の政策として進めていくというよりは、市民の声を私たちがしっかりと受け止めて国に届けていくという、運動が重要になってくると思います。
議員
子どもの生活実態調査ですが、平成29年7月ですので、7年前です。回答が1万4500件ほどあったので、なかなかの調査だったと思います。
小学2年生と5年生と中学2年生、その保護者にそれぞれ聞いて、詳しい状況が分かった状態だと思います。
その後、具体的な支援にどうつなげるかが肝腎なところだと思いますが、7年の中で実態は大きく変わっていると思いますので、今の時点でどうなのかということを知る必要がありますし、様々な支援につなげるということが大事だと思います。
議員
子どもの健全育成事業というのも旭川市はやっております。
生活保護受給世帯とか、就学援助制度を利用している家庭の中学生を対象とした事業ですが、市内数か所で拠点を設けてやっております。
実際見学させていただいたこともあるのですが、来るべき方がなかなか来られていないというのが実態で、定員を満たしていません。
以前一般質問で、子どもの健全育成事業について質問させていただいたことがありますが、基本的には拠点に来ていただいて、貧困の問題でほかの子どもたちと同じような経験をすることができない子どもたちに、勉強以外にもいろいろ経験してもらうというところなのですが、今後はなるべく予算を増やし、広報も行い、そういう方を見つけて来ていただくというようなことも、議員としても訴えていきたいと思います。
中学生に限らず、小学校高学年とか、少し年齢層を幅広にして早い段階からの関わりも必要ではないかと認識しておりますので、これを引き続き訴えていきたいと思います。
市民
ひとり親で高校1年生の男子を育てているのですが、子どもはADHDと自閉症の当事者で、小学1年生のときから普通学級と支援学級を行ったりしていました。
当事者の親なのですが、子どもには児童相談所もあるし、児童デイサービスもあるし、学校に行けば支援学級の先生がいたりして、相談に乗ってくれる場所や支援があるのですが、当事者の親が相談できる場所がないと思っています。
子どもが小学校の頃に本当に手に負えなくなって虐待をしてしまって、子どもが児童相談所に保護された過去があります。そのときに、誰に相談して良いのか分からなくて、民間の支援団体とつながりました。また、子どもが小学校のときには、学校のスクールカウンセラーで一緒にカウンセリングを受けたりして大変お世話になりました。
中学校に入ってもなお支援学級と普通学級を行き来していたのですが、何か問題があったときに、誰に相談して良いのか分かりませんでした。中学校にスクールカウンセラーをお願いして、小学校の時に担当だったカウンセラーさんの名前を言ったのですが、その方は派遣できないと言われました。今の学校の担当カウンセラーに相談するように言われましたが、そうなるとまた最初から説明しなければいけないので困りました。
今、高校生になりましたが、思春期や反抗期もあって結構困ることがあります。極力暴力をしないようにはしているのですが、子どもも親に悪いことしてバレたとなった時に、自分で児童相談所に保護してもらいに行ったりします。
私もどうして良いのか、誰に相談したら良いのか分からなくて、せめてカウンセラーを選べる、そういう制度を整えてほしいと思いました。
子どもは児童相談所とかが守ってくれるのですが、親は誰が守ってくれるのでしょうか。誰に相談するのかも選べないし、どうにかしてくれないかと思っています。
議員
小学校のときのスクールカウンセラーさんが、とても親身に御相談に乗ってくださったのだろうと思います。
スクールカウンセラーのことは私たちも議会でよく、取り上げている点です。一般的な取決めとしては、その学校でスクールカウンセラーの配置をしています。スクールカウンセラーの人数が少なくて負担が大きいということは課題ですが、特別なケースにおいて、指名制を含む相談体制の構築が本当にできないのかというお話を受け止めさせていただいて、市側にそういったケースに対応できないのかということを、確認しながらやっていきたいと思います。
また、親として、お子さんのことを中心に相談したいということですが、市には女性相談窓口もあります。窓口にいきなりお話ししに行くのは敷居が高いと感じるかもしれませんし、お話しして解決に向かうかどうかは、内容や相談員の方の能力もあるかと思いますが、これからお子さんが思春期を迎えられてますます大変だと思いますので、少しでも自分が生活しやすくなるよう、まず御相談をしてみていただけたらと思います。
窓口や支援を利用していただきながら、内容がまだまだ足らないということでしたら、また御意見を頂戴したいと思います。
議員
女性相談、親子一緒の相談、子ども総合相談センターという子どもの総合窓口、児童相談所など、各種縦割りの相談機関はあるのですが、相談に行ってもたらい回しにされてしまうというのが率直な実感です。
私に相談が来た時には、障害、保健所、教育、福祉の専門家をみんな呼んで、会議のように対応をしたことがあります。そのときはたまたまそういうことができたのですが、普通にどこかの窓口に行ってそれができるかというと難しいと思います。
親のことも子どものことも大変で、複合的な問題を抱えているような難しい事例においてはそのような会議が必要なのだと思っています。
1か所で様々なことが分かる、分からなければみんなで集まってやるといった体制を市としても考えなければならないと思っています。
本当はワンストップ窓口が理想で、旭川市も新庁舎になるときに、ワンストップになるよう同じ庁舎に係を集めたつもりではあります。具体的な体制という次の段階を考えなければなりませんが、率直に言って今すぐ解決できることではないので、私もほかの議員も個別に言ってもらえば対応すると思いますので、今のところは個別対応で何とかするしかないと思います。
議員
大変難しい事例だと思います。ここに相談をしたら全て、受け止めていただけるというところはないかもしれません。
ここ数か月間の中で、高齢者虐待を防止してほしい、施設で監視機能を高めてほしいといった問合せがあって、私が対応した事例がありました。
市民から相談を受けた問題の解決に当たるのは職務上当然のことだと思っておりますので、議員の個別の連絡先が分からなければ議会事務局を通していただくなど、そういった形で活用していただければと思います。
私もどうやって子育てをしていったら良いのかと悩んでいる親の1人でありますが、発達障害児の子育てということで私の何十倍も大変な思いをされていると思います。
子育てに関する相談窓口が旭川市子ども総合相談センターの中にあります。子ども家庭相談係というところでやっているのですが、一つの窓口として、子ども当事者ではなくて、親が相談できる窓口があります。
是非、そのような窓口で、悩んでいることについて具体的に絞って相談するというのも方法の一つかもしれません。私も様々な方から相談を受けるのですが、箇条書きで項目をつくってもらって、これを何とかしてくださいと具体的に言われたほうが解決策を考えられるので、相談のテクニックややり方としてそういう方法も検討していただきながら、また議会にも御相談いただければと思います。
議員
子育てで悩んでいるというより、自分がどうしたら良いかということで追い詰められているのではないかと思います。
以前同じような場で、「相談窓口があっても行かない」という言葉を聞きました。同じ境遇とか同じ人たち同士の中で、解決策を話し合ったりする、そういう受皿のようなものがあるということを聞きました。
子育てではありませんが、先日、介護で大変な思いをしている人同士が集まって悩みなどを話し合う場があって、最後は泣きながら共感していたり、話し合う中で新たな視点や解決策が出てきたりしていました。
先ほど民間団体のお話もありましたが、その民間団体はネットワークがとても広いです。行政や公的な相談窓口だけではなく、関わっている民間団体だけではなく、そこに関わっている人たちの中に同じような悩みを持っている人がいるかもしれませんし、そのような人たちと出会ったりできたら良いと私は思いました。
また本日来られている人たちの中には、様々な活動をしている人たちがいるので、声をかけてあげられるような人がいれば、ここからでもつながれば助かると思います。
市民
インクルーシブなまちづくりというテーマを聞いてお伺いしたいなと思ったのが、このまちがどう若者に目を向けているのか、どういった課題を皆さんが感じられているのかということです。
私も旭川市で育っていますが、若者は10代から20代ぐらいの子どもとも大人とも言えない移行期であるからこそ、様々な権利保障や機会保障という観点で不遇な環境にさらされやすいという特性があると思います。若者の中にも様々いますが、旭川市政を見ていても、目を向けている感じがしません。例えば余暇の場をとってみても、若者が余暇を過ごせるような場が確保されていなかったりします。
この間の神居古潭の事件もありましたし、駅裏の界わいの話もあり、問題要因として目を向けられる若者の話題はよく出てきますが、若者が社会参加する場をどう取り戻していくのかという話とか、その一つとして余暇の権利保障という話もあると思うのですが、その辺りの話が旭川市では全く出てこないと思います。
議会でも、旭川にユースセンターを作りませんかと質問されても、今は考えていませんという一言で終わらせられてしまったことがあったと思うのですが、札幌だと逆にユースセンターが市内5か所にありますし、札幌のユースセンターを運営している団体さんから、大通にたむろしているラッパーやスケボーで遊んでいる子どもたちにアウトリーチ型のユースワークをしているという事例も聞いたことがあります。
旭川市は若者にどう目を向けているのか、若者関連の旭川市の課題を皆さんがどう感じているのか意見をお伺いしたいです。
市民
職場がLGBTQに寛容なお店で、私個人も授業として高校生の前でLGBTQについてお話しすることがあるのですが、生徒さんはとても自由主義的な考えで、「そういう人が友達にいるのだけれど」とか、「どうしたら傷つけないでしょうか」とか、若い人のほうがとても配慮していると思います。むしろ、そういう概念や教育を受けていない大人のほうに差別意識が残っているのではないかと思います。知識とか理解がないと差別につながっていくと思います。
先ほどの質問者の本を読ませていただいたのですが、先生がすばらしくて、生徒さんが受け入れていて、子どものときから様々な人、自分と似ている人や違う人と一緒に過ごすことで多様性や柔軟性、おもてなしといったものが育つのではないかと思いました。
性的マイノリティの法律婚等の関係が資料にありました。今年から旭川市でもパートナーシップ制度が導入されたのですが、旭川市として、この問題について取り組んでいることがあったらお聞きしたいと思います。
市民
私は昨年度まで旭川市の社会福祉審議会審議委員をしておりました。
先ほど中途失聴者の方のお話の中で、当事者の意見をしっかり反映させてほしいということがありましたが、審議会に行くと専門家しかおらず当事者の方がいません。
これはどういうことなのかと審議会のほうで話したことがあるのですが、審議会の中での審議になってしまい、その声は反映されないと思ったので、この場をお借りして少しお伝えしたいと思いました。
また、先ほどの議員の方の御発言の中にあった、ハラスメントは自分もしてしまうかもしれないということ、このことに思いをはせること、それが相手の事情を知ろうとする態度であり、インクルーシブな社会をつくるためのこれからの大人の基本的な所作になってくると思いました。とても良いお話だと思いました。
最後に、私はインクルーシブ教育を推進するために、市教委や市長に対し要請書を出したりしてきました。
今日はっきりお伝えしないといけないと思ったのは、先ほど夜間中学のお話がありましたが、現状をどうするかということと、未来をどうつくっていくかということを二つに分けて考えなければいけないということです。
夜間中学校は、当然現状にアプローチしていくことが必要になりますが、その上で未来をどうつくるのか、将来的には夜間中学校がなくなるような社会をつくっていかなければならないのではないかと思っています。
そのためには、普通学校及び学級をどう改革していくのか、ここが肝になる部分だと思います。共通の認識として持っていただければ、大変有り難いと思います。
議員
若者へのまなざしということで、私も今まで若者への支援視点というのが、旭川市に限らず国全体としても欠けていたのではないのかと考えていました。以前議員秘書をやっていて、こども家庭庁の創設にも携わってきたのですが、その中で、例えば子どもの貧困であるとか、あるいは就職氷河期世代がどういう状況なのかとか、なかなか御理解いただけてないようなところもあったと思います。
様々な予算配分でも、「若くて元気だから放っておいても大丈夫でしょう」といった意見が出ることもあって、そう言っている高齢の方とかは全然悪意がないのですが、なかなか分かっていないと思いました。
子どもの貧困調査の話もありましたが、そういうことをしっかりデータでも出していきながら、もっとこどもや若者に光を当てていかなければと思っていますし、具体的に貧困問題や奨学金という名の借金を背負っている若者が多いとか、そういう問題に我が国全体でもっと取り組んでいかなければならないなと思います。
そういう機運が見えないというのはごもっともだと思いますが、少しずつ出てきているとは考えています。まだまだ頑張りますので御指導よろしくお願いします。
知識がないと偏見につながるのは正にそのとおりだと思います。有名な話で皆さんも知っているかもしれませんが、元明石市長の泉房穂さんの弟さんに障害があって、普通学級に通うのに、兄として自分が連れて行ったというエピソードがあります。日中は普通学級で、健常者ばかりだから弟がマイノリティだけれど、放課後に弟と一緒に障害者団体の場所に行くと、そこは障害者ばかりで逆に健常者の自分がマイノリティで、一体どちらが本当の世界なのかと思ったという話があります。社会は様々な人がいての社会だということを前提にしていかないといけないと思います。
ここはこういう人の世界だと分けてしまうと、お互い理解がないから、意図せぬ偏見とか差別につながると思いますので、今日のテーマであるインクルーシブを少しずつでも着実にやっていくことが大事だという印象を持ちました。
また、当事者の意見をもっと取り入れるべきだというのはごもっとも思いますし、現状と未来を分けて考えて政策を立案していくというのはとても大事な視点だと思って聞かせていただきました。
まとめ
民生班では、すべての市民が、年齢や性別、人種や国籍、障害の有無、性的指向や性自認等によって差別・排除されることのないまちにする「インクルーシブなまちづくり」をテーマに意見交換会を行いました。
暮らしの中で感じる生きづらさや困りごと、インクルーシブなまちにするためのアイデアなど、市議会と意見交換をしませんか? と市民の皆さまに呼びかけたところ、41名の皆様が参加され、障害児の教育に関する意見、公共施設における障害者への対応、大人のいじめや差別、子どもの貧困対策、子育てに悩みを持つ親の相談場所、若者の居場所、LGBTQへの理解など様々な御意見や御提案を頂きました。また、意見交換会に対する意見や感想をも17件寄せられたほか、当日参加された方から、「インクルーシブなまちに向けてのスタート地点に立ったような気がする」といった言葉も頂き、大変貴重な時間であったと感じました。ご参加頂いた皆様に心より感謝申し上げます。

(会場の様子)