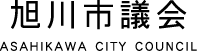令和6年度市民と議会の意見交換会報告書-4
地域における子どもの育ちを考える~体験格差の課題等について~ (子育て文教班)
意見交換の主な内容
意見交換の前に、関係団体である永山第三地区市民委員会及び旭川冒険遊びの会から、テーマに関する活動報告がありました。
永山第三地区市民委員会からは、「オタスケマン」と称した登下校の見守りなどボランティア活動等について、旭川冒険遊びの会からは、プレーパーク活動について、いずれも日々の活動の中で感じたことを交えた問題提起などについて、お話を頂きました。
市民
私は個人でトイドローンという小さいドローンを使って、週1回くらい、様々な子どもたちとイベントを行っています。今日は前向きな意見を述べたいと思います。
まず公園の使用について、ある地域のボランティア団体が子どもたちと一緒にごみ拾いをしようという企画があったので、私はその姿をトイドローンで撮影してあげたいと思いました。公園でトイドローンを飛ばすのは駄目だと言われていましたが、申請したら許可がおりました。 公園を使用するのは本来60万円くらい必要なところ今回は無料にするという使用許可でした。こうした内容では市民は萎縮してしまいます。
ボランティアの内容次第では逆に感謝状を出してもいいのではないかと思います。子どもたちも、いいことをした実感を持ち、積極的に参加するのではないかと思います。
公園では釣りやゴルフの練習を禁止していると聞きました。確かに危険なこともありますが、誰もいないときは使用しても良いのではないかと思います。何でも禁止にするのはいかがかと思います。公園は市民のものだと思うので、クレーマーみたいな人もいると思いますが、危険な状況がなければ使っていいのではないかと感じています。
また、公民館やホールなどは、5名以上でなければ借りられない制限があります。地区センターなど1人で借りられるところもありますし、使用料は1名でも10名でも料金は変わらないので、もし5名以上使う団体から申請があった場合は調整するという条件を付ければ、公民館なども別に5名という縛りは要らないのではないかと思います。
市民
私は個人で子どもの遊び場やイベントを提供しています。冒険遊びの会のスタッフもしているほか、公園やデイサービスでも活動しています。パートで様々なところで子どもたちと関わるのですが、公共施設については料金の面よりも利用の仕方、制限が多過ぎると思います。子どもたちの身体能力が落ちていることを問題視していることと矛盾しているのではないでしょうか。
クレームを恐れることはわかりますが、常設のプレーパークの話には賛成で、ケガを恐れずに遊びたい子が遊べるような場が無さ過ぎではないかと思います。
議員
公園の使用許可に関しては私も思うところがあって、子どもたちに関わることや、無償利用の際の使用許可に、必ず減免金額が書かれていて、あなたのところはこれだけ無料にしましたと主張したいように見えて、疑問に思っており、提言しながら改善していける部分ではないかと考えています。
また、子どもたちの自由な遊びによる育ちと、安全確保のための制限を、どのようにバランスを取っていくのかについて考えなければならないと思いました。
例えば先ほどの事例紹介にもありましたが、プレーパークであれば、その場の特性を前提にして遊び始めるからこそ、自由に遊べるのではないかと思います。
市民の皆さんは、例えばどの地域にこうした施設があればいいなどの御意見をお持ちか伺いたいと思います。
市民
永山地区ですが、夏場、子どもたちは一生懸命外で汗をかいていますが、冬場は外で遊ぶ機会が少なくなってしまいます。私と農家の人と連携し、雪で真っ白な農家の田んぼを解放し、自由に走ってもいいし、水性スプレーで絵を描いてもいい。そしておなかがすいたら永山のお米で作ったおにぎりを自由に食べてよいという、会を作り、SNSで告知したところ、150名も集まりました。
市民
春光台地区で団体を運営しております。子ども食堂や地域食堂等の団体として、児童センターが圧倒的に足りないということを感じています。地区ごとで考えても、遠くて子どもの足では難しい場合もあります。また、春光台の方には地区センターと公民館はありますが、雨が降ったときに遊べる場所がありません。
図書館の分室が公民館には入っていますが、長居できるような場所ではないので、子どもたちがその時間好きに行ける場所が、それぞれの子たちの徒歩圏内にあるようにできないかと常々思っています。
市民
労働者組合の事業団に所属しております。児童館の話が出ましたが、児童センター、30万以上の都市で6館しかないというのは本当に残念なことだと思います。
もっと小さな都市でも、校区に一つくらいはあって、私が住んでいた釧路地方の田舎でも、児童、留守家庭児童会などとは別に1校に一つありました。自由来館ができるところが圧倒的に少なく、飲食、ゲーム、携帯電話も禁止で利用にかなり制限があります。最近は携帯電話を小学生も持っているので許可され、暑さ対策で飲物も良いことになっています。そんな中、児童センターの職員が頑張って、出張児童館という、児童館や児童センターがないところで活動していたり、マチデコキッズといって、子どもたちが主体になって活動したりしているのですが、職員、人手が足りない、ボランティアを募ってもなかなかできないので月1回、出張児童館においては1年に1回くらいしか開催できない状態であると聞いています。
今、外で遊ぶところで、こども家庭庁から、子どもの第3の居場所を作るという推奨が出ているはずです。国からの助成と自治体の助成で、そういう場所を作るようにという状態になっていて、既に取組のある市町村があり、旭川も是非そうした取組を進めていただきたいと思います。
今日は子どもとは何歳までの定義をしていますか。公園の遊具が新しくなった話がありましたが、公園の遊具は対象年齢が12歳までとされています。子どもとは12歳までというのは違うと思います。大きい子はどこ行って遊べばいいのかと感じてしまいます。
そういう子たちが駅裏の河川敷に集まって、良いことも悪いこともやっているという話が出て、一斉に補導が入ったりしていますが、子どもの置かれている厳しい状況について、もっと実態を知っていただきたいと思います。
夏冬の休み期間中に朝食や昼食を取れない子どもたちがいるのが現状です。給食は提供されていますが、十分に食べることができないと、夜の食事がない可能性も考えられます。この問題の責任が親や家庭にあるのか、行政にあるのかは一概には言えませんが、正に体験格差が浮き彫りになっています。子どもを放置している親が全て悪いわけではなく、放置せざるを得ない状況にある方々も多く存在します。そのため、こうした状況についてもっと多くの声を聞いていただき、理解を深めていただきたいと考えています。
議員
子どもたちの現状が、把握しづらくなっているのが現実です。私は学校の教員でしたが、学校の状況も見えにくくなっています。家庭の状況にアクセスできなくなっているため、どのような子育てが行われているのかも不明です。行政に関しても、詳細な調査が難しいため、相談がなければ問題が埋もれてしまいます。したがって、地域で活動している方々から、こうした課題が存在することをもっと把握する必要があります。市民の方からもお話がありましたが、子どもたちができないことや特有の特徴についての情報を収集しなければ、旭川という街が、子どもが育つ環境としてどうなのか疑問が生じるでしょう。課題はまだまだ多く残されていると感じます。
市民
旭川においても不登校が急激に増加していると考えられます。学校に通わない、通えない理由は明確ではありませんが、行きたくない、行けない、行かないという子どもたちが増えているため、この問題について真剣に考慮する必要があると思います。
議員
不登校は旭川に限った問題ではなく、全国的に広がっている課題です。教育関係者を中心に、どのように対処すべきかが大きなテーマとなっています。一方で、学校に通えない子どもたちのために地域での居場所を作る必要性についての議論も重要です。この問題をどのように考えていくべきか、従来の学校教育の枠組みの中でのみ捉えられてきましたが、今後はその枠を超えて議論を深めることが求められると考えます。
議員
学校という場は制約が多い場所であり、その制約が増え続けているために不登校の子どもたちも増加しているのだと感じます。窮屈な状況です。子どもたちと活動を行う際も、様々な制限の中で力を育むことを見守りたいと思う一方で、時間や人手、後片付けなどの問題があり、なかなか実現できないのが現状です。しかし、教師や親としてはその思いを持っており、地域でそうした場を増やしていくことがとても重要だと考えています。学校もその方向に進むことが望ましいと強く思っていますが、そうでなければ不登校問題は改善されないでしょう。学校の変革は大きな課題であり、地域で何かを創り出す方が、必ずしも早いわけではありませんが、希望が見えるように感じています。
市民
現在、旭川市内には多くの民間のフリースクールや支援団体が存在しています。不登校支援者の会も新たに設立されてきている状況です。しかし、これらの団体に対する市の補助については、最終的には保護者からの資金提供が必要となり、現状ではどこかからの負担が生じているのではないかと考えています。この点について、市として今後より充実した支援が可能になる道があるのか、また現状についても関心があります。
議員
フリースクールに関しては、学校長や教員が正式に認めている場合、授業としての形で補助金が支給されます。しかし、報告書の作成や活動内容の報告など、教員にかかる負担は大きいのが現状です。また、補助金が親によって不正に使用され、フリースクールの手に渡らなかった事例も存在します。補助金が直接学校に振り込まれる形が望ましいとの要望もありましたが、交渉は難航し、改善には至りませんでした。
更に、学校の授業として認められていないフリースクールでは、子どもやその親にかかる負担が大きく、支援が必要であると強く感じています。フリースクールは子どもたちの居場所として重要な役割を果たしていると実感しており、今後は政策としてこの分野にもっと力を入れていきたいと考えています。
議員
不登校は学校教育の問題として捉えられてきたため、現在の状況が生じていると言えます。つまり、学校の教育課程を履修している場合には認められるが、単なる居場所としての利用では認められないという明確な区分が存在するため、このような事態が発生しています。しかし、無視できない数字が示されているため、現場からは学級に複数の不登校児童生徒が存在することが当たり前になっているとの声も聞かれ、学校側では対応が難しい状況です。このような現実に対する嘆きの声も多く、社会全体で対応していく必要があると痛感しています。
市民
私には小学3年生の息子がおります。オタスケマンの話を伺っており、日頃からお世話になっております。見守り活動にも感謝申し上げます。
この3年間で、せせらぎ通りの川に落とされたことが1回、また上級生から後頭部を押さえつけられ、顔面をアスファルトに押し付けられたことが1回ありました。これらを学校に報告した際、関係生徒や先生方との話合いで終わってしまいました。もちろん、被害や加害の事実は理解していますが、学校全体の教職員にもこの状況を把握していただきたいと考えます。また、各家庭の保護者や地域の皆様にも情報を共有し、安全に対する意識を高めていただければと思います。地域の方々が見守ってくださっている中で、情報が行き届かないのは問題だと感じます。子どもたちが安全に成長できる環境を大人たちで見守るために、情報を風通しよく共有できる仕組みが必要だと考えています。
議員
学校の問題は、地域で十分に共有されていないという点が重要です。せせらぎ通りが危険であるという情報は、多くの方々から耳にしています。危険な場所は各校区に多数存在しています。
市民
私は永山に居住しており高校の教員をしております。隣席の生徒は当校ダンス部の部長であり、私は顧問をしています。今日はこの生徒に誘われてここに来ましたが、これは子どもが主体性を発揮している良い例です。
子どもの主体性を育む社会にするには制限が多く存在し、そのような環境になっていません。大人たちは子どもを育てる際に、周囲から文句を言われないように様々な制約を設けているため、結果としてそういう状況になっています。
駅フェスについても、南高のダンス部が活動を始めたのがきっかけです。高校のネットワークを活用し、これを持続させたいと考えていますが、恐らく校長先生からはとがめを受けるでしょう。しかし、何かをしなければならないのです。こうした子どもたちを増やし続けることが重要です。小学校や中学校でそのような活動が広がれば、大体解決するのではないかと思います。
市民
その高校3年生です。主体性について先生からお話がありましたが、私自身、多くのことを感じています。学校で主体性を育てようとする中で、様々な制約があり、「これがダメ、あれがダメ」と言われることが多いです。私は道北管内の高校ダンス部のネットワークを推進しており、小中学生を対象に高校生がダンスを教える交流イベントを企画しました。しかし、その費用は高校生の実費負担となり、責任も学校側から学生に求められています。これが主体性を育む上で本当に正しいのか、疑問に思います。
そのためには、行政と学校が連携し、先ほどの事例にあったプレーパークやオタスケマンのような方々とのつながりを大切にしていくことが重要です。旭川のイメージが低下している今こそ、学生が主体となり地域に貢献することで、より良いまちづくりが進み、地域の体験格差が解消されるのではないかと考えています。
私は5歳からダンスを習い始めましたが、続けるのが苦手で、長続きしない方です。しかし、幼い頃からその楽しさを理解することができ、続けてこられたのだと思います。また、ダンスを通じて旭川を更に盛り上げるために、私たちが何をできるのかを考えるきっかけにもなりました。
議員
先日市議会でもダンスを盛り上げるための意見が出されました。子どもたちや児童生徒が主体的にまちおこしに関わることはとても重要であり、今後ますます求められると実感しています。教師や親が子どもたちに寄り添い、共感することで、主体性が育まれると感じています。子育てを通じて、その重要性を強く感じています。
先ほどせせらぎ通りの話がありました。実際、真夏になると、児童や生徒たちはせせらぎ通りで裸足になったり、靴を履いたまま水に入って帰ってくることがよくあります。
浅瀬であり、大きな川ではなくて、学校の通学路の一部に沿って流れているため、私の息子もその場所に入っていました。気がついたときには、ずぶ濡れになって帰宅しました。このような体験はプレーパークにおいてはとても良いことかもしれませんが、けがや衝突といった問題も考慮しなければなりません。先ほど少し残酷に感じる話もありましたが、学校が主体となって情報を共有することも重要だと感じています。
息子が通っている学校は、地域の情報共有のための「マチコミメール」というシステムがあります。地域と警察などが連携し、保護者に重要な情報を提供する機能を持っています。特定のケースでは、情報が伏せられ、後になってから明らかになることもありますが、このような情報の共有は非常に重要であると感じています。また、せせらぎ通りの安全についても、児童や生徒の安全を見守る「オタスケマン」の活動が行われていますので見守っていただきたいと思います。
議員
現在の学校教育が主体性を奪っているのではないかと、私は学校現場での経験から常に感じていました。子どもたちが「先生、決めてください」と言う姿を見て、改めて考えさせられました。彼らは「どうしたらいいですか」と尋ねますが、それは本来彼ら自身が決めるべきことです。子育ての中で、決定権を与えていなかったのかもしれません。
このような経験から、私が担当した学年やクラスでは、子どもたちに多くの決定をさせる機会を提供することが重要だと考えていました。私のクラスでは、子どもたちが自分の席や班を決めることにしていました。私のクラスだけ異なっていました。
このような方法に対しては多くの批判もありましたが、子どもを信じて任せることができない大人が増えているのではないかと感じています。現在、学校や地域のそれぞれの役割について、皆が真剣に考える必要があると思います。
市民
旭川で自立援助ホームを運営しています。現在、男女合わせて6名の入所者がいます。その中で5名はヤングケアラーで、2名は高校を中退して働いています。1人の女子は中学生の頃からアルバイトを強いられ、その収入では足りずにパパ活を行っていました。その影響がなかなか抜けず、旭川の駅裏で他の子どもたちや高校生とともにパパ活を続けており、何度も警察に補導されています。
私は旭川にも多くのヤングケアラーが存在し、学校を辞めざるを得ない子どもたちがいることを議員や市民の皆様に理解していただきたくて本日参加しました。入所している子どもたちは、生活費をアルバイトで賄っているため、お金が非常に重要です。家事をこなしながら、アルバイトの収入を全て親に渡し、自分の小遣いや学費を自分で賄うことができない状況です。
かつ上げや犯罪に関与していた子どもたちが多くいますが、今はホームで生活を賄っているため、乱暴な行動は減少しています。しかし、旭川駅前や駅裏には、毎日のように多くの高校生が集まっています。その中には、19歳のいわゆる半グレと呼ばれる男性がいて、女子高生からパパ活で得たお金を巻き上げています。何度も警察に補導されていますが、彼らは賢いため、なかなか補導に至らないのが現状です。
ホームで生活している6人の子どもたちは、ヤングケアラーと呼ばれていた日々を振り返り、現在は幸せであると語っています。しかし、旭川には同様の境遇にある子どもたちが多く存在することを知っていただきたいと思います。彼らをどのように支援し、救い出すことができるのかを議会でも考慮していただきたいと願っています。
議員
ヤングケアラーの問題は、議会において何度も取り上げられています。しかし、実態がなかなか明らかにならないという現状があります。表面化すれば理解できることも多いのですが、そこに至らない子どもたちが多数存在するという事実は、私にとってもとても深刻な問題です。恐らく、学校や家庭の状況が見えにくいため、子どもたちの様子を把握することが難しいのです。彼らがサインを出している場合でも、それに気づかないことがあるという問題も考えられます。
議員
私は5人兄弟で、兄弟姉妹で大きな年齢差があります。小学2・3年生の頃から、8、9年間、両親が自宅にいない状況が続きました。子どもたちの面倒を見るのは私の役割でしたが、地域の人々に助けを求めることができませんでした。私たちの家は町内会や子ども会に参加していなかったのです。
通学中にいつも同じ服を着ていたり、言動に異変が見られる子どもたちに、地域の方々が目を向けてくれることが重要です。旭川には子ども総合支援センターがあり、何か変だと感じた際には相談や通報を行うことが大切です。これにより、家庭への支援や、子どもたちの居場所を見つける手助けが可能になります。ここにいる皆様だけでなく、更に多くの方々にもこの重要性を広めていくべきだと考えています。行政もこの連携を強化する必要があると感じています。
議員
私もヤングケアラーの子どもたちと接する機会があり、夏に羽毛のセーターを着ている姿を見かけ、近隣の方々もその状況を理解し、児童相談所などに相談を行いました。しかし、親が子どもを手放すことに抵抗を示されていました。ヤングケアラーの実態については、岐阜県などで実態を調査するために視察を行いました。ある学校では警察が介入し、会議が開催されるなどの取組もありましたが、旭川市においてはようやく実態把握が始まったところです。実際にこの施設で関わっている方々の意見は、私たちにとってとても重要です。ただし、私たちが知らない、意外な場所に、もっと多くの子どもたちがいるかもしれません。
近隣の方々だけでなく、学校や病院など様々な視点から、子どもたちの置かれた状況に対して、目が向けられていると感じます。どのように支援していくかが重要であり、市も予算を確保しながら実態調査を進め、ケアマネージャーのように個々に寄り添った支援を行う意向を市長が示していますので、その点では動き出していると考えます。
「ヤングケアラー」という言葉を多くの人が知るようになり、市民の皆さんも意識を持って取り組んでいることを実感しています。私は駅裏と呼ばれている神楽に住んでいますが、実態を目の当たりにすると心が痛み、何とか助けたい思いが常にあります。
ヤングケアラーについて声を上げていただき、感謝申し上げます。今後、行政としてこの問題に対して、私たちが議会で更に声を上げていく必要があると強く感じました。
市民
私は以前は札幌に居住しており、旭川に転勤してから4年が経過しました。まず一つ目の点として、児童会館などの施設が少ないと感じています。私自身、小学1年生の時に親ががんにかかり、10歳で親を亡くしました。地域の方々や友人、知人、児童会館のような場所で遊ぶ機会が多くありました。そういった施設があったおかげで、言い方は難しいですが、道を外れずに済んだ部分もあります。また、地域の子ども会に参加していたことで、様々な大人とのつながりや地域イベントを通じて多くの体験をさせていただきました。現在は少し難しい時代かもしれませんが、町内会の機能や児童会館のような施設がもう少し活発に活動できればと願っています。児童会館を新たに建設するのは難しいかもしれませんが、地域に居場所があることは重要です。学区内に、小さな家のような場所でも構いませんので、子どもたちが集まり遊べるようなスペースがあれば良いと考えています。
もう一つは経済格差や体験格差に加えて、情報格差も存在するのではないかという点です。私も5歳の子どもがいる親として、遊び場を探す際に積極的に情報を収集しようとしていますが、意外にもそのような情報をまとめて発信している場所が少ないと感じています。公園や様々な施設、プレーパーク、大人食堂や子ども食堂など、多くの選択肢があると思いますが、あさひばしの記事を見ても、必要な情報が明確に示されていないことが多いです。また、旭川市の公式LINEに登録していますが、情報を得るのが難しいと感じることもあります。SNSを通じて、もっと市民が知識を得る手段があっても良いのではないかと思います。
もちろん、マンパワーが必要であることは理解していますが、情報が届いていない家庭や親がいるのも事実です。今回の意見交換会も、知人に誘われるまで存在すら知らなかったため、このような機会がもっと市民に広まるべきだと考えます。意見交換を通じて、地域がより良くなるための取組が増えることを期待しています。
市民
子どもたちが私たちのところに来ているほかにも、他の子どもたちの相談業務も行っているため、電話がかかってくることがあります。私たちのところに電話がかかる前に、子ども総合相談センターに相談をしているようなのですが、児童相談所につなげてくれない上に、子ども総合相談センターの方でも記録を取っていないのです。この相談内容について、何とか改善できないでしょうか。
子どもたちが知る相談先は子ども総合相談センターだけです。センターに7回も電話をかけたという子もいますが、その7回分の記録は残っていません。親からの虐待を訴え、「助けて」と言っているのに、児童相談所につなげてもらえないのです。今回、いじめの問題を契機に、センターから児童相談所への道ができたはずです。それは、子どもにとって本当に大きな勇気が必要なことです。電話をかけるという行為は、単に「どうしたいですか」や「我慢できますか」といった質問を受けるためではありません。にもかかわらず、児童相談所にもつなげてもらえないのです。
議員
これは私たちの方で現状を調査させていただきたいと思います。
市民
私は、ヤングケアラー、駅裏の問題、パパ活などの問題に対しては、すぐに着手すべきだし、迅速に対応する必要があると思っています。高校生、中学生に関わる課題は、予算をつけて調査を行っているうちに、彼らが卒業してしまうので、早急に解決しなければなりません。市には率先して責任を持って取り組んでほしいと思います。
「そのうち」ではなく、即座に取り組んでほしい課題です。これらの問題を解決しなければ恥ずかしい思いをするのではないでしょうか。旭川の大人としての自覚を持ち、みんなが行動すべきで、具体的に、年内や3月までに目標を設定して実態調査や組織作りを進めるべきだと思います。このまま何もしなければ、更に問題が起きるのではないかと強く懸念しています。
切迫した課題であり、最初に解決すべき問題であるはずです。できるだけ早く対応してほしいのです。なぜそれができないのか、あるいはしようとしないのか。先ほど述べた責任感に関わります。問題解決に率先して取り組むことが市の役割だと考えています。
やらなければならないことは非常に大きく、大人や親が責任を放棄したり、自分勝手な行動をとっている現状があります。この状況を変えなければならないのです。時間がありません。よろしくお願いします。
議員
重く受け止めさせていただきます。
市民
プレーパークはプレーワークというジャンルに属し、延長線上に中高生や若者のための活動の場を提供することを目的としたユースワークがあります。私が大学に通っていた札幌には「ユースプラス」という若者活動支援センターがあり、札幌市が定めた34歳以下の若者が自由に利用できるスペースが提供されています。低額で、誰でも気軽に利用できる環境が整っています。朝9時から夜10時まで開館し、旭川市の地区センターや体育館に相当する規模の施設もあります。駅直結の場所もあり、常にスタッフが常駐し、遊びに来たり相談で訪れた子どもたちのサポートを行っています。体育館を利用して自由に遊んだり、勉強をしたり、キッチンを使って料理を楽しむことも可能です。旭川市でもユースワークの必要性を感じていますが、場所の不足が課題です。
買物公園は、多くの建物が空いています。空き店舗をイベント時だけでなくロビーワークとして活用することが重要です。卓球台を1台設置することで、市の職員でなくても、教育に関心のある大学生や若者を配置し、行政と連携を図ることができます。若者からの相談を行政に伝える役割を果たし、適切なサポートを提供するユースワークの形を構築することが求められます。地域で活動したい若者や子どもたちが集まり、自分の興味を追求できる場を提供することで、同じ立場のユースワークのスタッフに気軽に相談できる環境を整えるべきだと考えます。旭川市においても、このようなユースワークの仕組みを構築することが必要だと思います。
議員
旭川市にもユースワークセンターのような施設があれば良いと考えています。具体的には、買物公園、永山、東光など、人口が比較的多い地域にそれぞれ1か所ずつ設置する形が理想です。大規模な施設ではなく、テナント1つでもいいし、廃校舎などの利用可能な場所が市内には多く存在しています。人々が集まることで再生可能な建物も多くあると考えられますので、市としてはこれらの施設をより有効に活用し、子どもや若者が地域で活躍できる居場所を創出していくことが望ましいと思います。
議員
地域における子どもたちの活動の拠点について考えると、観点は異なるかもしれませんが、子ども食堂を運営されている方々がいらっしゃると思います。私自身も子ども食堂を運営していますが、その発想の根本には給食費の問題があると考えています。近年、給食費を無償化する自治体が増加している中で、本市においても給食費の無償化は重要な課題であると感じています。特に北海道では、地産地消の観点から優れた食材が豊富にありますので、これらをできる限り子どもたちに提供することが行政の責務ではないかと考えています。私自身の課題でもありますが、もし子ども食堂を運営されている方がいらっしゃれば、是非御意見を伺いたいと思います。
市民
子ども食堂の副代表を務めています。私自身、チャチャチャワールドという活動を行っており、Instagramを通じて子どもの非認知能力を育むための情報発信も行っています。個別相談等の活動も展開しており、街中の「おきしぺたるむ」という場所を借りて、親子が遊べるスペースを提供していますが、多くのお母さんたちが誰に相談すればよいのか分からず、助けを求めて訪れてくれています。
市役所に相談しない理由として、相手がどのような人物であるか分からず、情報がどのように扱われるかも不明であるため、信頼できない人に対して話すのは難しいと口にしていました。私自身も幼少期に手を上げられる経験をしており、とても恐怖を感じていましたが誰にも話せませんでした。何度も学校から持ち帰った番号に電話をかけようと思ったこともありましたが、「自分の話を誰かに話すのだろうか」「親に連絡が行くのでは」と考えると恐怖心が勝り、高校生になっても電話ができませんでした。
私たちが準備をしていても、来なければ何の解決にもなりません。機能していないのであれば意味がないと感じます。相談に来る親たちは「市は何をしているのか、何にお金を使っているのか、市議になって教えてほしい」と言われます。私はとても制約が多いと感じているので市議にはならず、情報を知った上で周りにお知らせしたいと考えています。議員の方も含めて様々な方々と関わりながら活動している中で、同じ目標を持つ人々が多くいることを知りました。しかし、進展のスピードが遅すぎると怒りを覚え始め、個人事業主になった方が早いのではないかと思い、活動を始めました。
現在、3年目を迎えていますが、「おきしぺたるむ」で活動している他の団体が多く、様々な分野で自分の得意を活かして取り組んでいます。民間の方々は非常に熱心に、迅速に行動しており、旭川ではいじめや自殺の問題が深刻で、学校に行けない子どもたちが多数存在しています。皆がこの状況を理解している中で、積極的に動いているのは民間の人々であると感じています。私もその一員として、問題の深刻さを認識しており、期限を設けて行動することが重要だと考えています。この会が終わった後も、また同じメンバーで集まって進捗を確認するなど、予算の使い方や今後の方針について話し合う必要があると思います。市や市議会もそれぞれの役割を果たした上で、民間の人々に協力を求めるべきです。そうでなければ、私自身も行動に移せないと感じています。非認知能力の検定を受けた経験から言えることですが、出会う教師たちに非認知能力の重要性を問うと、ほとんどの人が答えられません。
また、自主的な子どもを育てるための授業内容についても、具体的な答えが得られないことが多いです。保育士たちも、古い教育方法に固執しているように思えます。公開保育や研修を行っているにもかかわらず、子どもたちの生きる力や非認知能力を育む取組が不足しています。 4月から新たにプレーパークの常設のような居場所を作る計画を進めており、現在仲間を募集中です。しかし、「おきしぺたるむ」に関しては、家賃や光熱費が毎月約10万円かかり、みんなで分担しています。資金が不足している中で多くの人が活動したいと思っているのに実現できない状況について、旭川市の見解を伺わなければ私たちは納得できません。その内容を何月何日に発表するのか、今日いるメンバーに知らせていただきたいと思います。これが私の要望の要約です。
まとめ
意見交換会の当日は、永山第三地区市民委員会会長及び旭川冒険遊びの会代表の方より活動内容を発表していただきました。また、子どもたちの居場所づくりなどに関わる多くの団体の方に御参加いただき、日頃から子どもたちが生き生きと遊ぶために工夫されている内容など貴重な御意見を沢山いただきました。
なかでも旭川市は子どもの居場所が少ないという御意見があり、不登校支援、中高生の居場所づくり、旭川市内の大学などとのコラボなど旭川市全体で子どもたちの遊び環境や体験づくりをしていきたいなどの希望あるお話もありました。さらに複合的な居場所づくりを目指す内容の御意見や札幌市の若者ユースセンターなどのお話があり、常任委員会として若者支援総合センターの視察を予定しております。
当日は、子どもたちとの関わりについて貴重なお話をお聞きすることができ、心より感謝申し上げます。大変ありがとうございました。

(会場の様子)