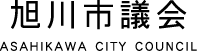令和5年度市民と議会の意見交換会報告書-4
旭川市民文化会館の建て替え~文化活動の広がりを目指して~ (子育て文教班)
意見交換の主な内容
意見交換の前に、関係団体であるまちなかぶんか小屋から、テーマに関する活動報告がありました。日々の活動の中で感じたことや市民文化会館を中心とした旭川市の文化振興についての問題提起などについてお話しいただきました。
市民
「文化はまちを元気にする。」旭川市教育委員会社会教育部にある言葉ですが、正に適切な言葉だと思います。本会では、ギャラリーを作ってほしいということを言い続けてきましたが、実現していません。市民文化会館の展示室と、市民ギャラリーとの関わりは、重大なことだと思っています。大量生産、大量消費の時代は終わり、市民の多くは、質のいい時間、質のいい空間を求めている、そういう時代に入ってきていると思います。特に日本の中では、「共生を大切にしよう」という良い流れもできていますし、国は、文化芸術基本法を作る、旭川市もそれに呼応して条例などを作って推進しようとしています。
旭川大学をベースにして、新しい公立の大学、地域創造学部といったものが開設されると聞いています。創造と、もう一つ大切なことに「鑑賞」があります。創造と鑑賞は、中学校の美術の中でも習ったと思いますが、表裏一体で、それを繰り返しながら向上していくのだと思います。そういう観点からも、使いやすい市民ギャラリーが必要です。
現在、旭川市市民文化会館整備基本構想検討会が開催されています。その中では「複合施設をつくろう」という方向に向いているかのようにマスコミから聞いています。その根本になっているのは、恐らく新聞に掲載された市民文化会館に関する市民アンケートの中で、「機能面は現状で満足」という回答が多いということだと思います。
しかし、私たちは地下の展示室をギャラリーとは言っていません。展示室を借りている立場からすると、これほど不備な展示室はありません。48年前の建物ですから仕方がないですが、エレベーターで作品をギリギリ入れて、天井や床をこすりながら地下まで作品を運んでいくということを繰り返す。これは大変な作業です。
美術関係の領域で言っても、今は作品の大きさも規模も、画材や表現方法も、30年前では予想のつかないものになっています。これから先50年ぐらいも、大変な進歩をすると思います。液体や気体を使う作品が出てきています。コンピューターを使う、また、動く彫刻なども、どこにでもあります。そういうものが展示できるスペースにしなければならないというハードの面があります。
もう一つ大切なことは、ソフトの面です。市民の要望に応え、意見を吸い上げる。市民を育てるという管理をする。そうしたソフトの部分が人です。そういう人の配置はどうしても必要になっています。
特に検討会では、ハードの面しか検討していないのではないかと思います。ソフトの面も大切にしていただきたいと考えているところです。そういう意味で、建て替える、あるいは移転をするときには、ギャラリーを独立させなければ駄目だと考えています。
私たちは、札幌で北海道の展示会に出します。でも、それを旭川に持ち帰って管理することができません。管理をして、市民の人に見ていただく。そしてまた、取組が行われるということの繰り返しなのですが、それが不十分な状態になっています。
札幌では、高校生中心の発表する場を設けています。残念なことに、市内のある高校は、240人程入学した今年の1年生から美術の教科がなくなりました。全生徒は700人ぐらいですが、教員がいなくなり選択できなくなりました。例年、その高校から美術大学や美術の領域を学べる大学に進む生徒がいます。これからも出てくるだろうと思いますが、どのように勉強するのでしょうか。その高校を批判するつもりはありません。恐らく慎重な審議をした上でのことでしょうが、そういうことを私たちは考えなければいけないと思います。
議員
今、お話の出た高校も含めて、別のお子さんからも美術がなくなったという現状を聞いています。今回、北海道の展示会に出して入賞したような作品を、環境がないため旭川ではなかなか見られない、戻ってきた作品を市民の皆さんに還元することができないというのは、大きな課題だと受け止めさせていただいたところです。
市民
市内で小さいギャラリーをさせていただいています。このキーワードマップを今ざっと眺めたところ、先ほどの方もおっしゃったようにソフト面の議論が不足しているのではないかと思います。
伝えるとか、増やすとか、建物が勝手にやることではないと思います。建物なので手続は重要ですが、それを回す人、そこに窓口になるような専門的な人材がいないと十分機能しないと思います。
私は以前、文化庁でやっているアーツカウンシル(※1)の取組で、浜松町の立ち上げに携わりましたが、そのアーツカウンシルみたいな機能、専門の人とつなぐ、調整をする窓口みたいな人が、行政から少し距離を置いた形で必要なのではないかと思いました。
もう一つ気になったのが、市で取り組んでいる「デザイン都市・あさひかわ」(※2)の取組がこの中に見られないことです。目的とするところはかなり重複しているのに、それらに対してばらばらに税金を使っています。せっかくハードを整備するのに、それが盛り込まれていないのはどうなのかという点です。
※1 アーツカウンシル ~「芸術評議会」と訳され、文化芸術に対する助成を基軸に、政府・行政組織と一定の距離を保ちながら、文化政策の執行を担う専門機関のこと。
※2 デザイン都市・あさひかわ ~「あさひかわ創造都市推進協議会」がユネスコ創造都市ネットワーク(※3)を生かし、国立公園である大雪山を含めた地域が持つ大自然や豊富な地域資源をデザインの力で価値を高め、自然や人を大切にした、魅力的で持続可能な地域社会の実現を目指す活動のこと。
※3 ユネスコ創造都市ネットワーク ~異なる文明、文化、国民の相互理解を目指すユネスコ(国際連合教育科学文化機関)が平成16年に世界の創造都市の連携による創造的・文化的な産業の育成や相互交流の支援を目的に創設したもの。
議員
ユネスコ創造都市ネットワーク、デザイン都市というところの取組が入ってないというのはおっしゃるとおりだと思います。
また、行政と距離を置いたような形のコンシェルジュというのがふさわしいのかどうかわかりませんが、そういった取組ができるようなソフト面の議論が、確かに足りていませんので、これからの議論の中で生かしていけたらよいと思います。
議員
学校教育の中で美術は大切にされておらず、中学校3年生は週1時間、年間35時間しか美術の時間がありません。ですから、時間をかけて絵などは描けません。
子どもたちの感性を育てる、磨くというような時間がどんどん削られている中で、大人・市民がこの旭川でどういう文化をどう創っていくのか、大事な議論だと思います。その文化の器を作るときに、どういうふうに人を動かしていくのか、どういう人に協力していただくのかというのは、とても重要だと思います。
先日、小田原市に新しくできた市民ホールの立ち上げに携わった方のお話を聞いてまいりました。館長さんは舞台芸術が専門の方で、行政マンではない方が自治体の文化をどうしていくかということを考えて、それに行政が協力していくという仕組みをきちんと作っていました。併せて市民との対話をきちんとやっているということも分かりました。市民の声を受けて行政が建物を作りますというような従来の考え方で、今回の建て替えを進めるべきではないと思います。いろいろ御意見も頂きましたので、何が大事なのかという議論を、多くの方としていくべきだと改めて思いました。
市民
私たちは詩吟の会で、こちらの小ホールや会議室などで活動しています。使い勝手のみで申し上げますが、大ホール、小ホールのほかに、可能なら100名ほどのこぢんまりとした、気楽に使えるようなホールが一つ二つあれば有り難いです。
それから、大ホールなら扇型が取れたら、なお良いのではないかということと、各ホールにおいて、集音マイクの設備も備えてあると出演する方も、会場の職員の皆さんも助かるのではないか、ということがあります。
さらには、小ホールは非常に動線が悪く、使いにくいです。例えば、地方から初めて市民文化会館の小ホールに来られた方が、そこに入るまで道案内を置かなければなかなか到達できません。客席から舞台の方に上がることも難しいです。これらをもう少し明確にすっきりした形に整備していただければ有り難いと思っています。
先ほどお話があった展示室も、階段で降りなければいけません。小ホールは2階で受付をするようになっているので、階段を上らなければなりません。現在、会員さんも高齢化して、足が不自由で上れないということが多くなっていますので、そういうところの配慮をお願いできたらと思います。
議員
私も先ほど、この会場まで誘導しましたが、エレベーターと階段と、本当に案内しづらいと感じたところではあります。
議員
今、お話があったように、市民の皆さんの発表の場としてのホールの位置づけは非常に重要だと思います。気軽に発表会ができるようにするには、今、高齢化の問題がありますので、上ったり降りたりというのはやはり大変です。
案内も、第1楽屋、第2楽屋など、同じようなパターンでずっと表示してあるので、わかりにくいということもあります。そういう点についても十分検討すべきだと思います。
市民
まちなかぶんか小屋で映画の自主上映をしています。具体的な実践の場から提起したいことと、市民文化会館の建て替え等を絡めてお話ししたいと思います。
雑誌に、「サン・アザレア」を解体し、その機能はほかのところで代替できるだろうと、市が方向性を出したということが報告されていました。丁寧に読んでいないので、詳しくは分かりません。
しかし、サン・アザレアを使ってきた者たちの声は、誰が聞いてくれるのでしょうか。その成果や問題点は、どういうことなのでしょうか。その上で、公共施設の整備の問題が提起されていないので、私たちは知らない間に取り上げられてしまうという感じがします。
まちなかぶんか小屋で映画を上映していて困ることは、25から30ぐらいの間の座席数をやっと並べられる程度だということです。今、リノベーションの問題があって、ますます座席数が少なくなり、非常に限られた空間になってしまいます。自主上映にたくさんの人が来てもらい、それを努力しながら続けていくというときに、まちなかぶんか小屋での上映を基礎としながらも、やはりサン・アザレアは大事な施設なのです。
その大きな意味は、暗闇をつくれるということ、階段状であるということ、それから音響施設がそれなりにあるということです。これらは舞台芸術の小劇場の条件などと非常に重なると思います。
旭川では、ミニシアターや小劇場がなく、舞台・演劇のチームも、いろいろ場所を探して上演しています。自主上映も、様々な公共施設を利用しながら、映画村、アジア映画祭などを十何年もやってきています。それらを引き継いでいくためには、小劇場がどうしても必要だというのが切実な思いです。
暗闇にできること、階段状であること、音響施設に加え、プロジェクターやスクリーンなど上映用の施設は必須だと思います。市民文化会館は、箱物を作る時代の中で、各自治体で競って作り上げていった経過があります。大きいことはいいことだということであったわけですが、同時に、多様な市民の要望に応えるために、舞台劇場を中心とした小劇場的なもの、活動が小さいながらも利用できる小ホールを考えて組み込んでいけないものかというお願いです。
市民
詩吟の会から補足したいと思います。800人の会員がいたときは公会堂を中心に、その後、少なくなってからは小ホールを中心にお借りして活動しています。
これまで困ったことは、例えば、詩吟の発表会のとき、自分の出番の前に発声をしたいのですが、それができません。リハーサル室もあるのでしょうが、2階で審査会などをするとき、発声をする場所がありません。大きな声を出す場合は、2階全部を貸し切らなければならないと聞いたことがあります。そういう面も改善されれば良いと思います。
今日のような意見を聞く会を開催していただいたことに感謝します。ただ、大まかな計画が大体こんな感じだということが分かると、意見も言いやすいです。今後また開かれるのかと思いますが、その辺も含めてよろしくお願いします。
議員
市民文化会館の建て替えという課題に対して、これからどんなものが作られるのかを検討している最中です。具体的な計画がまだ明らかになっていない状態ですので、皆様がこういうものを取り入れてほしい、こういう機能を取り入れてほしい、ハード面ばかりではなくソフト面の充実を考えてほしいというようなことなど、御意見がたくさん反映されるような場が設定されたら良いと思います。
先ほど小田原市のホールについて話がありましたが、計画ができてからも、何度も何度も市民の皆様が集まる場を設けて、具体的な意見を聞き、取り入れるものは取り入れていく、できないものはなぜできないのかというようなことなども、丁寧に説明をしながら取り組んできたそうです。そういう取組をすることで、市民文化会館が自分たちの財産だと考えるようになっていくのではないかと思います。今日もそのきっかけになるのではないかと改めて思います。
市民
常磐公園で毎週土曜日に子どもの居場所づくりをしています。市民文化会館は、もっと若い世代に開かれて、意欲的にやりたいことができる場所になったら良いと思います。
いじめの問題もありますし、中学生、高校生、大学生が、新しく建て替わるであろう市民文化会館を利用して、交流や学習、ダンスやバンドの練習などができるようになればよいと思います。例えば、防音設備の付いた部屋を学生料金で借りられたり、若い人が集まるという意味では、誰でも自由に使えるWi-Fiを館内に付けておくなどすると、今の若い世代はうれしいのかなと思います。
これから旭川市を担う若い世代を育てていくという意味でも、もっと若い世代に焦点を当てた文化活動もできる、放課後などにいろいろと利用しやすい場所になってくれたらうれしいです。
議員
今、基本構想の検討会を開いていて、来年2月頃、基本構想の素案が出てきた後に、パブリックコメントがありますので、それを踏まえて、また意見を言える機会が出てくると思います。
若い方の交流、居場所がどんどんなくなっています。特に、中心市街地にあった商業施設がなくなり、フードコートでも断られたりして、市内中心部で交流だけではなく、居場所が少しずつ減ってきていると感じることがあります。
そんなときに、この市民文化会館の建て替えについて、Wi-Fi環境も含めて、学生料金の設定など、貴重な御意見を頂いたと思います。若い世代同士だけではなくて、いろいろな世代間の交流もできるような発想やお考えがあったら教えていただきたいと思います。
私も神奈川県の大和市のシリウスというところへ行きましたが、そこは図書館との複合施設でした。非常におしゃれな図書館でしたが、最新型施設を見ていろいろ勉強になりました。様々な方がリラックスして本を読んだり、また、自分たちが講師となって教室を開いたり、いろいろなことをされていました。旭川市も市民の方が講師となって活動できる場があってもよいと思います。これは建物があってできることでもありますので、考えていきたいと思います。
市民
文化芸術に特化して市民文化会館の建て替えが行われると思いながら来ましたが、皆さんのお話を聞いて、困っていることがたくさんあるということが分かりました。
私たちの団体の会員はコロナで減ってしまい 、1,000人ほどになりましたが、まちなかぶんか小屋が閉じないで何とか続けたように、私たちもやめると再起は不可能だろうと思い、ずっと続けてきました。
その中で、青少年劇場例会というのをやっています。旭川にいる中・高生で演劇を1回も見たことがないという子が多いので、年に1回ですが無料で招待しています。もう何十年もやっていて、市内の中学校と高校全てに案内をします。今年は見に来てくれた高校生が8人でした。そのため、青少年に演劇を見てもらいたいという、切なる願いがあります。
会場がどうにかなればできるということではありませんが、何か私たちでも力になれることがあるのではないか、一緒にやっていけたら良いと思っています。
演劇は年6本とも公会堂で行っています。ほかに会場がないからです。演劇専用のホールなどは旭川にないので、我慢しながら使っているという感じです。舞台が小さいです。そのため、演劇をやるにはどれぐらいの舞台の広さが必要なのかとか、お互いに話し合いながら、私たちも何か相談に乗れるのではないかと思いながら話を聞いていました。
大ホールでは大き過ぎますし、小ホールでは小さ過ぎます。今はまだ、公会堂が使える状況であることはうれしく思っていますが、決して万全なわけではないです。「新しくすてきなホールができた」、「あそこへ一度行ってみたい」と多くの市民が思ってくれるようになっていけば良いと思っています。
市民
30年くらい前に、「旭川に図書館を」という運動をされた方がいました。そのとき私は学校に勤めており、子どもたちは自分の学校にある小さな図書館に加え、移動のバスで本を持ってきてくれましたのでそこから選んでいました。
それから後も旭川市は、図書館に関しては何も変わっていないと思います。
以前、ニュージーランドに行ったことがあります。そこでは住宅街にとてもかわいい建物の図書館が何か所もありました。買物公園のようなところに、入口は狭いですが、中に入ると右側に子どもが座る小さな椅子があり、子どもたちが本を読んでいました。その反対側には大人がいて、お母さんが乳母車で本を借りに来ていたという姿が忘れらません。
まちづくりには、本を借りる場所がまちなかにもあると良いなと思っていましたので、是非御検討をお願いします。
私は美術を専攻していました。この北海道第二の都市である旭川に美術館がないのが情けないと思います。道立美術館はあっても、よそから来た作品を見る場所なので、旭川市民が使える美術館を、私も強く要望したいと思います。
市民
昭和61年と令和2年に落語の会を作りました。昭和61年に有名な落語家の方がバイクで北海道を回っていて、旭川にも寄られるということで、市民文化会館の小ホールで落語をしてもらいました。そのとき、「すごいね、ここの会場。落語のためにできた会場だよ。」と褒めていきました。ですから、この2つの会はなるべく小ホールを使うようにしています。
小ホールを予約しに行くと、結構競争倍率が高く、暖かくなってくると予約が取れなくなります。そこで小ホールが2つあったら面白いのにと勝手なことを言いにきました。そうするとくじ引きで外れた人たちが、また土日に使えるようになります。1月2日にも、市内のホテルで落語の会をやっていたのですが、最近、会場費が折り合わなくなり、やめなければならなくなりました。残念ながら、正月は市内の市有施設全部が休みです。どこか開けてくれたらうれしいと思うことを伝えさせていただきます。
市民
市内の生花団体の代表者です。市民文化会館の第2会議室や3階の大会議室で、生花の技術を更に高めるための研究会を開催しています。
この会場は少し使いづらいです。テーブルや椅子などは重過ぎて、だんだん高齢者になる女性がほとんどの団体としては、すごく大変です。お水はSK(清掃用流し)から使います。
私たちは水が命なのですが、トイレのドアの開く方向が逆なのです。外に開いてほしいのが内側に開くため、とても大変です。
先ほど若い方もおっしゃっていましたが、Wi-Fiは必要です。ときわ市民ホールや旭川市の公民館なども、Wi-Fiを使えるところがほとんどありません。これはとても重大な問題だと思っています。
この会場も、私たちは本部として様々な地方からの先生たちをお迎えするので、研究会を開催するに当たって、前の年に全部計画を練っておかなければなりません。1年間に5回までは予約できますが、それ以上はできないので、どこの会場がどうやってとれるのか戦々恐々としています。その辺をもう少し緩和してほしいです。
ときわ市民ホールを使ってもいいのですが、1か月前からしか予約がとれません。そういうことも問題だと思っています。そういうことは建て替えではなくてもできることなので、もう少し議員さんにお力添えいただ けたらとても助かります。
私たちは伝統文化生花親子教室事業というものもやっています。案内をするプリントを各学校に配らせてもらうために、教育委員会から許可をもらっています。しかし、各学校の先生たちは、今、そういうプリントを配ってくれません。忙しいというのもありますが、プリント量が多過ぎるから何でもかんでも配布しないでほしいという保護者の意見もあるそうです。では、どうやってPRをしたらよいのでしょうか。そういうことも、議員さんのお知恵で何とかなるのでしたらお願いしたいです。
先ほどお芝居を中学生、高校生たちに無料で見せたいけれど、学校に呼びかけてもなかなか返事が来ないということと同様かなと思っています。
市民
いくつかの美術団体に所属して活動しています。先ほど、この会は要望を出す場ではないとのお話がありましたが、この会の位置づけについて若干聞かせていただきたいと思います。
私のところにこの会の案内が届きましたが、その文書を書いたのは市民文化会館館長、そして主催者はそこにいらっしゃる議員と書いてあります。
今、新しい市役所で、旭川市民文化会館整備基本構想検討会も、第5回目か第6回目が行われています。
この会で話し合われたことは、この後どのように発展していくのか。会場に議長もいらっしゃいますが、議長にこの会の結果を報告するのでしょうか。市民文化会館の担当は教育委員会です。この案内は市民文化会館館長ですから、社会教育部長や教育長に報告がされるのか。それとも、今津市長に報告されるのか。この会の結果について、どこに報告されるのかを伺いたいです。これが一つ目です。
二つ目は、この会は、この後、どのように発展していくのでしょうか。先ほど議長からも若干お話がありましたが、年に何回くらい、こういうふうに開催を考えているのかなど、どのように発展して使うのか、この構想を伺いたいです。
三つ目は、この結果を、本日の参加者、また、旭川市民にどのように報告されるのでしょうか。インターネットでこういうふうに書いておくから見なさいということであればそれでも結構ですが、旭川市民にどのように報告されるのでしょうか。
何人かの学校の先生や、以前、学校の先生でいらっしゃった方の話もでましたが、学校教育も変わってきています。私が一番不安に感じていることがあります。日本の子どもたちの文化・スポーツを支える地盤を学校が作ってきたのではないでしょうか。部活動も、親と学校、そして先生方のボランティアです。それらが協力しながら作り上げてきたのが、日本の文化・スポーツの経験だと思いますが、御承知のように、学校の部活動は、市民に降ろしましょうという時代です。指導者もどんどん足りなくなってきたという時代です。その中で、市民文化会館が新たに作られるということですから、学校が支えてきた文化やスポーツをどのように支えていくのでしょうか。そういう点でも、市民文化会館のことを十分検討していただきたいと申し上げます。
議員
この会の報告書は、テーマごとに議員が作ります。4つのテーマで常任委員会ごとに開催していますので、報告書をまとめた形で1冊にして、支所や市有施設などに置かせていただきます。そして、私たちの報告書を、市の担当部局にも読んでもらいたいということがあれば、担当部局に渡すこともできます。
市民と議会の意見交換会は、年に1回開催していますので、今年度は今回限りとなります。それはどこのテーマもそうなります。皆さんの発言、それに対して議員がどうお答えしたか、要約ですけれども、まとめの報告書はきちんと毎回、作成しています。
この会の議論がどのように発展していくのかということについては、貴重な皆様からの御意見ですので、今後、議員が質疑等の機会に、こういうお声があったということで代弁させていただきたいと思っています。
議員
今後、議論に触れたこのメンバーが、その基本計画に関しての報告であったり、パブリックコメントなどの報告を委員会で受けた際に、この会での皆様の御意見、それ以外にも個別にいろいろと受けることもあると思いますので、そういった場をそれぞれが設けながら、皆様の声を反映し、議論に生かしていくというような会議の位置づけになっています。
先ほどの2点目、Wi-Fiのお話が出ていましたが、市民の皆さんが活動で使っている市有施設などのWi-Fi環境に関しては、ずっと議論されています。市民の方から御意見を頂いて、どうにかして、Wi-Fiを使える環境を確保できないだろうかという議論が、現在議会でも行われています。
また、発言されているときに会場費が高いというところの皆さんのうなずき方も見ていましたので、その点なども今後の議論に生かしていきたいと思っています。
それから、小ホールの競争倍率の話なども出ましたが、自分の会の活動に対して、適切な会場の大きさ、所要人数というところが、市民活動には重要だと受け止めています。議員視察で、2つの班とも新しいホールを見てきていますので、更に皆さんから発言ができるような場をどのように設けていくのかいうことも、議論をしていきたいと思います。
市民
大学で芸術の教員をしていました。
冒頭のお話の資料の中で、文化芸術振興基本計画は、第8次旭川市総合計画を上位計画としていると書いてあります。その総合計画の中に、施設が古くなって、作り変える、廃止するというときに、これまでのように壊して建て直すということを今後はやめて、現在ある建物に適切な改修を施した上で、建物の長寿命化を図るということが書かれています。
ところが、今日のお話の大体は、現状の市民文化会館を取り壊して、場所は分かりませんがどこかに新しく建て直すというのが前提のような話が多かったように思います。
資料の8ページ目に、旭川市民文化会館建替え(大規模改修)についてとタイトルにありますが、この大規模改修をして、建物を使い続けるという選択肢も取り上げてほしいと思います。
市民
文化芸術の中で、美術の力が皆さんにあまり知れ渡っていないということで、肩身の狭い思いをしています。文科系自体、だんだん活動が鈍くなってきている中で、その中でも、技術、絵画、彫刻、工芸、写真など非常に肩身の狭い位置に置かれているような気がします。
旭川は美術のまちと言ってもいいほどのまちだと思います。私たちの会は戦後すぐに設立されました。もう一つほかに美術団体もありますが、その二つの公募展がどちらも今年、78回目を行っています。それほど多くの市民が、美術に携わっており、また各公民館には美術サークルがあり、そこで皆さん、切磋琢磨しながら、年に1度、市民文化会館で作品展を開いています。
この美術のまち旭川にきちんとしたギャラリーがありません。貧弱なと言ったら失礼ですが、肩身が狭いです。
全国的にもこれだけ大きな団体が二つ、切磋琢磨しながら活動しているところはないと思います。
それから、私たちの団体には、道北の稚内市から名寄市近郊、オホーツクの方からも出品しています。旭川は道北の文化の中心ということで、私たちも奮闘していますが、議員の皆さん方にも、美術のまち旭川という意識で、美術に対してもっと認識を深くしていただきたいです。
そういうことで、複合施設としてもきちんと作る、そういう施設にしていただきたいと思います。
議員
市内には、例えば喫茶店の中のギャラリーなども数多くあり、宮下の倉庫を利用した「市民ギャラリー」もあります。
駅の構内にも、小さいスペースがありますが、大型の公募展には適しません。それは市民文化会館の中に、しっかりとしたものを作るべきだとは思いますが、小さなそういうところも文化を育む良い取組だと思います。大きな建物、しっかりとした建物を作ることと同時に、地域にたくさんそういう施設があると、住宅街からも歩いていけるところで作品が見られる、そういうことを大事にしていかなければならないと思います。
先ほどお話がありましたが、子ども劇場という活動をしている団体の方もいて、小さな頃からそういう文化に親しむという取組がされています。
また、昔遊びをやるなど、市民の手作り、手弁当でいろいろな活動をされている方たちの取組があって、この旭川の文化活動が根づいてきたということを改めて感じました。
市民
クラシックバレエを指導しています。この市民文化会館ができたときから、こけら落としも参加していますし、2年に一度、大ホールを使用させていただいています。コロナ禍も休まずに発表してきました。
大ホールのステージは、大きさや客席数はとても満足のいくものですが、小ホール同様に大変導線が悪く、楽屋から客席の廊下に出る通路がありません。舞台から花道を通って客席に、というのが本番中だとできません。
私は、若い頃東京のバレエ団に所属しており、文化庁の芸術祭や、子ども芸術祭で、日本国中の劇場を回りましたが、こんなところはありませんでした。
建て替える、あるいは改修されるのであれば、是非そこを直していただきたいです。それから楽屋のトイレが少な過ぎて困っています。日本中に様々な劇場ができていますので、たくさん視察に行っていただき、様々な文化芸術に対応できる劇場を目指していただきたいと思います。
議員
本日はお忙しい中、このように多くの皆様に御参加頂きまして、大変にありがとうございました。感謝申し上げます。
どのような意見交換会になるのか、人が集まるのか、私ども議員は本当に不安の中で、本日を迎えましたが、このように皆様と積極的に意見交換をさせていただくことができ、大変有意義な時間を過ごさせていただいたと思っています。
これもひとえに、お集まりになってくださいました、旭川をより良くしたいという皆様の思いがあるからこそ、本日、開催できたと思います。また、貴重な御意見を頂けたというふうに思っています。
この後、本市議会一丸となって、皆様から頂いた貴重な御意見を市民の福祉の向上のためにも一生懸命取り組んでまいります。
本日は大変にありがとうございました。
まとめ
当日は多くの文化団体の皆さまが参加されるなか、まちなか文化小屋様より日頃の様々な文化活動について発表して頂きました。
意見交換会では、ギャラリーの設置などのハード面だけではなく、デザイン創造都市にふさわしいソフト面での意見もたくさん頂きました。皆さまから頂いた貴重な御意見・御提案の実現のためにしっかり取り組んで参りたいと思います。最後に、御多忙の中、御参加いただいた市民・関係団体の皆さまに心より感謝申しあげます。

(会場の様子)