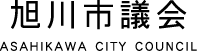令和5年度市民と議会の意見交換会報告書-3
ゼロカーボンシティの実現に向けた今後の取り組みを考える~家庭ごみ等の減量化など、小さなことからでも出来る地球温暖化対策について~ (民生班)
意見交換の主な内容
市民
私は転勤で故郷旭川に戻って来ました。今回のテーマは、旭川のまちづくりに非常に密接したものだと思います。旭川市がどのようにゼロカーボンシティ(※1)へ変わっていくのかということは、未来を担う子どもたち、旭川に住む子どもたちのためにも、残さなければいけない道しるべだと思います。旭川市内の子どもたちが、環境問題やゼロカーボンシティについて、授業を受けたり学習をしたり、副読本で読んだりする機会があるのか、お聞かせいただきたいと思います。旭川は、買物公園もごみ一つないきれいなまちです。山の方には若干ごみがありますが、市内についてこれほどきれいなまちはありません。私は転勤族で、いろいろなまちを見ていますが、未来の子どもたちのために残すまちづくり、孫や子どもに素晴らしい旭川を残すという意味でも、是非ゼロカーボンシティの取組を進めていただきたいと思います。
※1 ゼロカーボンシティ ~脱炭素社会に向けて、2050年までに二酸化炭素の排出量を実質ゼロにすることを目指す地方自治体のことを指し、旭川市では、令和3年10月22日の本会議における市長の所信表明の中で、これを表明しています。
議員
私もある中学校でPTA会長を務めており、旭川市PTA連合会の役員も務めています。その中で、学校の先生や保護者、そして子どもたちとお話をする機会が多くあり、これから地球温暖化が進んでいく中で、今と同じ環境を私たち大人が未来の子どもたちに残していけるのかということが、学校の先生として非常に不安に思うというお話も伺ったことがあります。
そういった中、行政が取り組む以外で、私たちが生活の中でどのような努力や工夫をして、二酸化炭素や温室効果ガスなどの排出を抑制していくのかが求められると思います。
子どもたちに今の環境問題をしっかりと伝えるためにも、環境部では、学校等の依頼に応じて出前講座を行っています。今後も、取組を能動的にしっかりと進めていく必要があると考えており、今日の御意見を踏まえて、更なる取組を検討していきたいと思っています。
議員
今、言われたように、出前講座の依頼があった学校で子どもたちに授業を行っており、また、小学校で配布される社会科の副読本の中で、地球温暖化などについて触れられています。私は出前講座を食品ロス対策としても広げていけないかと考えており、環境部に話しました。先ほど、旭川はまちなかがすごくきれいだと言っていただきましたが、旭川駅の裏の方が開発されて、緑や自然を残したままで造り上げています。そこに今、神楽岡公園まで桜の木をつなげるという計画があり、それも温暖化対策として進めていくという状況です。
市民
二酸化炭素の吸収量が多いのは森です。行政にも林業の担当課があると思いますが、皆さんは、林業、森林の維持、あるいは育成ということに関して何か施策をお持ちでしょうか。
議員
旭川市議会森林・林業・林産業活性化推進議員連盟(林活議連)として、森林の保護や環境問題にも取り組んできました。おっしゃるとおり、二酸化炭素の吸収源となるのは森林です。間伐を含めて森林環境をしっかりと維持していく、活発化していく取組が求められると思います。また、森林は、水源を維持するような役割も果たしています。温暖化が進み、既に今年度も、新潟県や秋田県で貯水池や川の水が干上がった、水不足だという報道がありましたが、このようなことをしっかりと食い止めるためにも、森林環境の保護に努めていかなければいけないと思っています。
最近、カーボンニュートラル(※2)などの取組の中で、燃料として使うために森林資源の伐採が進んでいます。また、ウッドショックという状況が発生しました。そのような中で、国産材や道産材を切り出すことが多く進められた3年間でした。本来であれば、法律上、切ったところには苗木を植えるということが義務付けられていますが、林業を担う方々の高齢化や人手不足の問題があり、実際に伐採されたところにいまだ苗木が植えられていないという状況も課題となっています。林活議連の全国の会議や道内の会議に出席しても、一部地域からそのような課題が述べられています。
環境部だけの問題ではなく、しっかりと森林を活用しながら再生にも力を入れていくことを、農政部に対しても求めてきたつもりですので、今日の御意見を踏まえながら、更に努力をしていきたいと思います。
市民
北の森づくり専門学院という、若い林業従事者を育成する学校があります。確か4、5年前に、上川総合振興局の林務課と高等学校と学院の教員とを組合せて、森を親しむ、あるいは林業についての理解を深めるという動きがありました。是非、国の施策だけではなく、市の立場で学生なども巻き込んで、様々な組合せの企画を展開するようなことを、皆さんのリーダーシップで進めていただければよいと思いました。議員
下川町などが先行地域として努力もされていて、木を全部使い切るということで、伐採したものを放置しないでバイオマス(※3)にしたり、温泉や保育園、庁舎でエネルギーとして活用したりと、様々な取組を行っています。それらが旭川市でも参考になるのではないかと考えています。
また、芦別市では、放置された間伐材を活用して市の施設などに木質バイオマスのボイラー等を設置しています。芦別市にある温泉のボイラーも、市で木質バイオマスボイラーを入れており、間伐材をエネルギーに変えるという事業を行っています。
さらに、それらを行うと石油事業関係の業者の皆さんが困るということもあり、山から切った木を持ってくる運搬の仕事は石油事業関係の業者の方に任せたそうです。市が関与して補助金を出しながら、仕事がなくなって困る人たちに仕事を作っていますので、これも大変参考になるのではないかと思っています。道内にも参考になるところがたくさんありますので、旭川市でも様々なことを考えていければと思っています。
※3 バイオマス ~生物資源(bio)の量(mass)を表す言葉であり、「再生可能な、生物由来の有機性資源(化石燃料は除く)」のことを呼び、その中で、木材からなるバイオマスのことを「木質バイオマス」と呼びます。
市民
昨年も意見交換会に参加して、汚泥を肥料化するということについて質問しました。資料の中にも、一人一人が地球を汚さないように活動をしていかなければいけないということが、半分以上にわたって書かれています。私は、個人個人の努力も大切ですが、特に大都会等の大企業が排出している二酸化炭素の影響や責任が大きいと思います。地方には山や木材があります。田園を見ると緑や稲があり、様々な作物があって二酸化炭素を吸収します。これが地方の魅力であり大切な役割だと思います。それと比べると、大都会の経済産業は日本を支えているという自負があると思いますが、逆に地球を汚しており、これが莫大な被害だと思います。それをいかにして解決していくのか。日本は世界一の石炭の輸入国です。これからいかに石炭を減らしていくのかが、温暖化を防ぐ早道だと政府も考えていくと思います。しかし、具体的な対策はなされていません。
そこで私が提案したいのは、石炭コークスに代わり得る燃料をどう作り上げていくのかということで、これが非常に大事なことです。その中核になるのが地方です。特に北海道には、バイオマスの資源が莫大にあります。旭川を見渡すと、森は少し遠いですが林があり、下水処理センターにもバイオマスが眠っています。下水処理センターには、1年間に3万トンという下水汚泥が集まります。これを約4億8,000 万円というお金を使い焼却して埋め立ててしまいますが、これは大切な資源です。なぜこれをバイオコークス(※4)にして石炭コークスに代わる燃料を作り上げないのかと、私は考えています。
今、バイオコークスという、石炭に変わり得る燃料が脚光を浴びています。これは近畿大学の教授によって開発されました。いろいろなバイオマスを1ミリ程度に粉砕し、それを10パーセント程度に乾燥、脱水してシリンダーの中に詰め込み、圧縮して作られるものがバイオコークスというものですが、石炭コークスに匹敵するカロリーがあることが実証されています。
そば栽培で有名な幌加内町では、実際に北海道の補助金を得て、約3億円で工場を建設しています。是非皆さんその工場へ視察に行ってください。そして近畿大学の教授と直接お会いして、話を聞いていただければと思います。下水処理センターの汚泥を燃やさず、このバイオコークスを作るために使っていただきたいという提案をします。
※4 バイオコークス ~植物性バイオマスを原料とした固形燃料のことで、光合成を行う植物資源等を100%原料にしているため、化石燃料に代わる環境に配慮したエネルギーとして期待されています。
議員
個人としての努力も限界があるということで、大企業でも二酸化炭素も減らしていってほしい、バイオコークスを旭川でも進めていってほしいという御意見を頂きました。幌加内町でも行われているということで、市議会としても是非視察に行って、生かしていけるようにしてまいります。
市民
まず質問です。資料にある、旭川市の温室効果ガス排出量の推移というグラフですが、市単体の排出量を計るのは難しいのではないかと思います。どのように計算しているのかを簡単に教えていただきたいです。二つ目として、資料にある、家庭から排出される二酸化炭素というグラフですが、削減するときは大きいところから削減するのが基本だと思います。グラフを見ると、ごみやキッチンからは非常に少なく、ここで削減しても効果はあまり大きくなく、逆に自動車や照明家電製品が大きいので、ここに手をつける必要があるのではないかと思います。
また、導入促進の政策として、地域エネルギー設備に対する補助金と木質バイオマスストーブに対する補助金がありますが、例えば、15年経っている冷蔵庫を買い換えるための補助金を出すなどの方が効果は高いのではないかと思います。地域エネルギー設備や薪ストーブは設置できる家がすごく限られているので、それよりもっと幅広くいろいろな人に行き渡るような補助金の使い方、しかも、簡素な手続でできるようなやり方をする方が、短期的には様々な効果があるのではないでしょうか。
特に旭川市は、恐らく賃金水準が非常に低いので、やりたくてもできないことがたくさんあると思います。LEDを付けたいけど、LEDの値段を考えるとなかなかできないということもありますし、そういうところに届く政策を作るのがよいのではないかと思うのですが、是非御意見をお聞かせいただければと思います。
議員
排出量は、国が出している数値を人口で割り返して旭川市の規模にすると、これぐらいの量になるという数字です。産業別などに分かれたものが国から示されており、そこから推計していくと旭川市はこれぐらいだという数字になっているということです。
今、御提案いただいたとおり、ストーブを変えることにどれだけの効果があるのかということが議論になることもあります。もっと効果的な方法ということも、考えていく必要があると受け止めさせていただきました。
議員
今、言われたとおり補助金を出してでも、様々な効果がある方法を作らない限り、家庭ではお金をかけて太陽光パネルを付けるなど、様々なことはできませんので、大きく切り替えるためには、そういうものが必要であることは間違いありません。
また、二酸化炭素を一番排出しているのは間違いなく産業部門や大都市の経済活動ですので、そこを何とかしない限りはどうしようもないと思います。ただ、田舎の方は何もしなくてもよいか、公共部門や民生部門は何もしなくてよいかというと、そうはならないので、家庭からのゼロカーボンシティの取組を考えましょう、ということが今日の趣旨になります。
私は先週、大阪府の堺市へ行政視察に行きましたが、堺市は脱炭素先行地域として国の認定を受けています。堺市では、都市部と、田舎の方の泉北ニュータウンという開発から50年も経過し高齢化した地区に住んでいる人たちの交通アクセスも、ゼロカーボンシティの取組の中で解決しようという取組を行っています。PPA(※5)契約により、公共部門や産業部門に太陽光パネルを付けてもらい、そのエネルギーを買い取って都市部に電力を回し、田舎の方からも電力を受け入れる仕組みで、また、田舎の方ではAIのオンデマンドバスを走らせるということを公共部門としてやろうとしています。ただ、堺市の庁舎がZEB(※6)化されていないので、それも国の補助金を使って行おうとしています。
国では今、最大で50億円の補助金を出して、脱炭素先行地域の取組を成功させようとしており、モデルケースを作ろうとしています。旭川市でもできるかどうかは分かりませんが、旭川市の新庁舎がZEB化されておらず、課題も多いですが、都市と田舎を結ぶ様々なやり方も、産業界の取組も、課題整理が必要だと思います。
※5 PPA ~Power Purchase Agreement(電力販売契約)の略語で、太陽光発電設備を所有し管理するPPA事業者が、契約者となる企業や一般家庭などが所有する敷地や屋根などに設備を設置し、そこで発電された電気は、敷地を提供している企業や一般家庭を含む電力使用者へ有償で提供される仕組みのこと。
※6 ZEB ~Net Zero Energy Buildingの略語で、快適な室内環境を保ちながらも、建物で消費する年間の一次エネルギー消費量を正味ゼロにする建物のこと。
議員
ただいま頂いた御意見の感想ですが、家庭で省エネを推進していくことが難しいということは、そのとおりだと思います。一つ思い当たるのが、平成21年頃に家電エコポイント制度というものを国全体として行っており、私もそのときに、冷蔵庫やエアコンを買い換えるとかなり電気代が安くなり、買換えの元も取れて驚いたことがあるのですが、それだけ古い家電は電気を使うのだと思いました。新しくすると、逆に電気代も下がり、温室効果ガスが削減できると思いますので、そういう取組を全国で行うとよいのではないかと思います。
また、家庭部門でどうやって削減するかということですが、家庭、産業問わず、発電所で作った電気を使っているので、例えば、先ほど御提案のあったバイオコークスや水素社会の推進など、国レベルの話になるかもしれませんが、根本的な発電のところ、グリーンエネルギーの推進というところも、市から意見として、国に上げていければと思いました。
市民
先ほど、省エネの電化製品に対して助成をという意見がありました。気密の高い住宅を建てる場合、国や道の補助金があるのですが、旭川市として、気密の高い住宅に対する助成や援助はあるのでしょうか。議員
旭川産の木材などを使って家を建てた場合の補助などは行っています。市民
私は大工ですが、気密の高い家に改造してほしいと依頼されることもあります。サッシは国からの助成がありますが、旭川市も是非このような気密の高い家を建てた方への助成を考えてください。市民
資料には、旭川市で行っている省エネ・再エネ設備の導入の事業について書いてありますが、市長は様々な会議で、薪ストーブに助成をしていると積極的に発言されています。大体1件20万円の助成額ということですが、薪ストーブに助成をして、ゼロカーボンシティ、カーボンニュートラルにつながることなのかが、私の理解とはかけ離れており、その辺が丁寧さに欠けると思います。例えば昨年、市制100年で100本の桜を植えましたが、これをカーボンニュートラルという意味が分かりません。市議会議員の皆さんは分かっているかもしれませんが、例えば、人間が普通に生活して出す二酸化炭素排出量というのは、1人当たり年間320キログラムです。その排出量を杉で換算すると、樹齢25年から30年の杉で23本です。100本の桜を植えて、市民4人分の二酸化炭素を吸収しましたと言っていただくと非常に分かりやすいと思います。これで満足してしまわないように、是非皆さんにも頑張っていただきたいと思います。
先ほどの方が電化製品の買換えの話をして、お答えいただきましたが、エコポイントをまたやるということは、恐らく不可能だと思います。今、電化製品の買換えをできるかできないかは、経済対策が大事なのです。既に相当家電を買い換えているというのが電気屋さんの意見です。それからLEDも本当に頑張ってみんな付け替えました。それが現状だと思います。ただ、引き続きそういうものを買い換えられるよう、旭川の所得が低いからと言われたことに皆さんは恥じらいを感じて、我々の所得を上げましょうというところも含めて、皆さん方に頑張っていただきたいと思います。
最後に、市では薪への助成をしていますか。去年1年間で50トンぐらいの薪を薪ストーブで燃やしていますが、薪にも基準があります。切ったばかりの薪は、この辺の針葉樹では50パーセントぐらいが水なので、これを1年から2年乾かして、水分量を20パーセント未満にします。20パーセント未満という基準があるので、そういう薪を是非市としても奨励して、業者や個人も含めた事業者にも理解を得て薪を作ってもらう。それを購入して、薪ストーブで燃やしてくださった方々からは、薪ストーブに関わる炭素税を徴収するというぐらいの気持ちで推進される方が良いのではないでしょうか。
議員
様々な御意見のとおりだと思います。先ほども森林の話がありましたが、森林保護には木質バイオマスエネルギーの活用ということも、非常に重要だと思っています。薪ストーブの話がありましたが、問題なのはなかなか需要が拡大しないことです。需要が拡大しないからこそ、エネルギーの消費が進まないということも大きな課題です。例えば、工場で使う木質バイオマスボイラーの導入も進んでいません。一般家庭でも、薪ストーブやペレットストーブの導入も進んでいません。結果的に森林資源の活用先がないということが、大きな課題になっています。産業化できないからこそ、森林の整備が進まず、それで給料がもらえるような状況になっていないのです。そのようなところも大きな課題だと思います。
資料のことがあったので少し振り返りたいのですが、資料では、本市の温室効果ガスの排出量の内訳について、お示しをさせていただきました。資料に示されているとおり、民生家庭部門28パーセント、民生業務部門20パーセントということで、合わせて半分ぐらいの二酸化炭素が民生部門から放出されています。民生家庭部門は、私たち市民が生活の中で排出する二酸化炭素等の数字です。民生業務部門は、会社内で暖房を使う、湯沸かし器を使う、そのようなところから放出される二酸化炭素のことを示しています。この民生家庭部門に対して特に強力なアプローチが必要であり、また、大企業からの放出も抑制をしていかなければいけないということが事実です。私たち市民がふだんの生活の中で、どのように温室効果ガスの排出を抑制することを考えるか、会社に出勤した場合に、例えば電気を消す、なるべくお湯を使わないようにする、クールビズやウォームビズの対応で冷暖房のエネルギーの消費を節約するなどの取組が重要だと思います。
そういう視点から、市民でもできる簡単な温室効果ガスの排出抑制の取組について意見交換したいということも、本日の目的の一つでありました。例えば、ふだん私たちが活用する自動車について、冬は十分に車を温めて、移動距離が僅か5分ぐらいのところのコンビニに行くのも、まずはアイドリングをするといった実態があると思います。人口30万人の私たちが、アイドリングストップを1日1分、若しくは1日5分短縮するということを考えるだけでも、相当数の二酸化炭素の放出を抑制することができます。
さらに、インターネット等で通販を活用したときに、配達日指定、時間指定をしないで不在にして再配達が行われるケースを、私も含めて、恐らく皆さん経験していると思います。これが課題だと言われており、ドライバーの人材不足のこともありますが、再配達で無駄に放出される、活用されるエネルギーと二酸化炭素は莫大な量だと言われています。
このようなことを、私たちの生活の中で努力する。しっかりと配達日や配達時間を設定して、受け取れるときに受け取る。若しくは、営業所止めにして自らが近くの営業所に荷物を取りに行くという取組を、市民の活動として行っていかなければ、行政がどうだとか、国の取組がどうだとかといったことでは、なかなか環境問題を解決することにはならないと思っています。
バイオコークスについては、平成26年8月に大阪府の高槻市へ行政視察に行き、その頃から興味関心を持っていました。バイオコークスの最も有利な点は、燃やすことなく生の木に圧力をかけてコークス化することで、コークスを形成する段階において二酸化炭素を必要としないことです。ほかのコークスでは、何らかのエネルギーが必要になるので、木質ペレットも含め、二酸化炭素を放出してエネルギーを作るものではないことが、バイオコークスの取組ということを学びました。結果的に地域の林業に活力を与え、人材育成につながり、産業と人材育成の両面においてメリットがあるということも学習しました。私たちが生活の中で放出した二酸化炭素の吸収源である森林を守る取組についても、市民一人一人がしっかりと考えていく必要があると思います。
薪ストーブやペレットストーブの補助制度には上限がありますので、多くの補助金を一人一人に配ることはできませんが、木質バイオマスエネルギーの消費を拡大していくことも、地球温暖化対策を進めていく上で重要なことになると思いますので、市民の皆様とともに、私も努力していきたいと思っています。
市民
今、たくさん説明していただきましたが、二酸化炭素排出量実質ゼロにつながりますか。そこだけ明確にお答えください。議員
二酸化炭素を実質ゼロにするということ、二酸化炭素の放出と吸収を均衡させるという取組であるカーボンニュートラル、また、ゼロカーボンシティの実現については、大変厳しい高いハードルだと思っています。しかし、今、そこに向けて、市民や国民が地球全体で努力をしていかなければならない課題だと認識しています。市民
個人個人の努力は非常に大切ですが、限度があります。一人一人の市民はこの物価高で、必死になって頑張っています。私の妻も、毎朝新聞の広告を確認し、安くておいしいものを選んでいます。毎日毎日、市民は必死に生きているのです。一人一人の努力でもって、ゼロカーボンに向かっていくということは大変美しい言葉ですが、もっと大企業が排出する二酸化炭素に対して地方が物申していく、そういう地方自治体の役割は非常に大事だと思います。ただ中央政府の言いなりになって、そのとおりの政策をやるのではなく、地方ができる政策を訴えていく姿勢が大事だと思います。
市民
今、御意見を伺って少し違和感を持つものが幾つかありました。例えば、暖機運転の話です。私は、2年3年ぐらい前までは、青空駐車場でカーポートがないところに駐車していましたが、暖機運転をしないとなかなか出られません。今は、カーポート付きの駐車場がある所に住んでいるので、もう暖機運転をしていませんが、みんなそこは無駄遣いしようと思って暖機運転をしているのではなく、必要に迫られてやっています。
市民の意識は大事だと思いますが、そうではない部分こそが行政ができる取組なのではないでしょうか。もし、「行政はやることをやっているので市民一人一人の意識をもっと向上しましょう」という意識があるのだとしたら、それは何かとても危険なことだと思うので、よく考えていただければと思います。
市民
温室効果ガス排出量について、資料の中では、2005年度から2027年度に25パーセント減、さらに、2013年度比で2030年に48パーセント減、最終的に2050年にカーボンニュートラル達成となっているのですが、家庭から排出される二酸化炭素の円グラフのどの部分を主に減らせばこれに近い数字になるのかを教えてください。議員
この数字は推計となっているため、実際に旭川市で厳密にこの数字を出すことは難しいです。ただ、旭川市としてもできることをやって、さらに、個人個人の意識の中でやって、ゼロカーボンに向かっていこうということを皆さんと共有していきたいと考えています。
旭川市も財政的な課題があるので、予算の中でどれだけ補助できるかという問題もあります。考え方をしっかりと持ってやっていかなければ、ただやっている感を示しているだけになってしまうと思います。ゼロカーボンを達成するのは大変なことですが、数字的に削減されてきているということも事実です。この数字をいかに下げていくのかは、全体で考えていかなければならないことであり、そのためにいろいろな御意見を頂きました。
頂いた御意見を市政にどれだけ反映させていけるかということは、これから我々議員が市へ伝えていくことになりますので、皆さんからの意見をきちんと受け止めさせていただきます。この数字は国がしっかりとした数字を示さないと反映されないので、旭川市だけはなく、それぞれの自治体が取組を進めていけば、国の数字が下がっていくと思います。
旭川市は、産業といっても大きな工場がそれほどあるわけではないので、先ほど言われたように、大都会の二酸化炭素排出量の方が多いと考えられます。しかし、その熱を吸収する政策を北海道はもっとできるのではないか、排出よりも吸収ということも考えられるのではないかと思います。地域によって特性がありますので、それを最大限活用して、しっかりと考えていく必要があると思います。
議員
皆様のおっしゃっていることは、そのとおりだと思いました。今、若年層は地球環境や温暖化のことを考えにくいという数字が出ています。この社会が失われた30年だと言われている中で、経済的にとても大変な思いをしていて、生活をしていくことで本当にいっぱいいっぱいな中、システムではなく個人の意思で100年後の地球のことを考えて行動できる方がどれだけいるのかということは、私も思うところです。個人の努力だけではなく、ゼロカーボンシティへ向けた取組を、市としてどのようにシステム化し、仕組みを作るのかというところを考えていけたらよいと思います。ストーブや冷蔵庫など、いろいろな話がありましたが、行政の方で予算がないなどと言っておらず、どういった仕組みが作れるのかということを併せて、皆さんの御意見も参考にして考えていきたいと思います。
市民
財政とか予算とか難しいことを言われましたが分かりません。堺市に視察に行ったという先ほどの話ですが、あれは確か脱炭素先行地域づくり事業で、国は100か所の脱炭素先行地域の選定を行うようですが、つい最近、苫小牧市が選定されました。累計74番目ぐらいでしょうか。残り26か所。1か所50億円の交付金ですが、やる気はありますか。問題はそこなのです。市長はやる気満々です。旭川方式でやると言っていました。それから先ほど言っていた住宅はZEH(※7)というもので、この中に含まれています。旭川市役所はZEBの規格に合っていません。残念です。脱炭素先行地域づくり事業を利用して、50億円獲得頑張ろうということでよろしいでしょうか。
※7 ZEH ~Net Zero Energy Houseの略語で、太陽光発電による電力創出、省エネルギー設備の導入、外皮の高断熱利用などにより、家庭で使用するエネルギーと生み出すエネルギーをバランスして、1年間で消費するエネルギーの量を実質的にゼロ以下にする住宅のこと。
市民
議員
一番の課題は、まちづくりの課題が整理されているかどうかです。中心市街地のことや、農村部の交通体系など様々なことも含めて、まちづくりの課題で一番ネックになっている課題が何か。それを解決するときに、カーボンニュートラルやゼロカーボンの取組とセットでやるということが、国の脱炭素先行地域の考え方なのです。それを旭川市として練り上げるための時間はなく、間に合わないと思います。第4回までに74か所が選定されていますが、数の問題ではなく、熟練度として旭川市はもう間に合いません。具体的なゼロカーボンシティの取組の中身として、旭川市は何をやっていくのかを、これからまだ検討しなければなりません。市長がやる気満々だと言っても、中身が必要であり、気持ちだけ満々ではできないので、そこには、私たち議会にも責任がありますが、まちづくりの中身をどうするかということです。
堺市に行ってがっかりしたことは、「新庁舎になって、もちろん庁舎はZEBになっていますよね」と聞かれましたが、「残念ながらなっていません」と答え、悔しい思いで帰ってきたことです。ZEHの方も、取組はまだこれからなので、具体的な事業化ということと、様々な思いがかみ合っていないので、大事なところをこれから作らなければならないと思います。
今、旭川で行っているデマンド交通を、例えばAIを使った電気バスに切り替え、ほかの地域も含めてまちなかまで持ってくる。そのエネルギーはどうするのかといえば、堺市のように、PPA契約により市役所の上やいろいろな空き地に太陽光パネルを設置してその電力を活用し、その活用の中にオンデマンドバスも位置づいているという話なのです。
今、せっかく複数の方々に賛同いただきましたが、旭川市がすぐに先行地域になるという覚悟や決意や熟練度は足りないと思いますので、これからまた別の形で進めなければならないと思います。
議員
また、真庭市では、例えば山を所有する人たちに木を自分たちで切り出してきてもらい、それを買い取ることを行っています。今まで重油を燃料として使っていたものを、まちなかの燃料だけでやっていこうという計画を立ててやっているのですが、旭川市も、議員一人一人がゼロカーボンシティに向けた考えをしっかりと持っていかないと駄目だと思います。
いろいろな御意見を聞いて、お叱りばかりだと思いますが、旭川市は新しい庁舎を建てたりして予算が厳しい状況ですので、先ほどの50億円の獲得に向けては、環境部ともしっかりと話をしていかないといけないと思っており、今日の意見を役立たせていただきたいと思います。
市民
議員
行政がやってきたこと、また、これから目指していくことにプラスして、市民が自らそれぞれの立場や環境でできることが何であろうかと考え、できることをやっていく。そういった取組について意見交換ができればという趣旨でお話をさせていただきましたので、そこについては御理解を求めませんが、訂正をしながらおわびをしたいと思っています。
先ほどありました庁舎の問題は、前市長の中で政策が進められてきました。私たちは当時野党でしたので、例えば、行政ができることという視点でお話をすると、この新庁舎の建設の段階で行政が大きな投資をするべきだというような提案も、当時設置をされた市庁舎整備調査特別委員会の中で何度もさせていただきました。
例えば、雪国ですので、雪氷熱エネルギーの活用として、庁舎の中で何かできないか、大量の雪をためておいて、夏場の冷熱として使う、さらには、ペレットボイラーや木質バイオマスエネルギーを活用した暖房を使う、また、自然換気による空調の仕組みを取り入れるなど、様々な提案をさせていただきました。
行政が求められる課題や要望は多いと思います。改めて、今日頂いた市民の皆様の意見をしっかりと受け止めて、取組を進めていきたいと思いますので、一言おわびも含めてお話しさせていただきました。
市民
更にお願いすることは、もっと皆さん知恵を働かせてください。自分の中で足りないところは、もっと多くの方の知識や知恵だとか世の中の動きから情報を得て、より高いものを目指していただきたいです。先ほどの市庁舎のこともそうです。旭川駅前再開発のことについても、あちこちで再開発を行っていますが、一素人の考えとしては、どうしてどこもここもタワーマンションを建てて、庁舎を新しくして、公園を造って、同じことばかりやるのだろうかと思います。そういう意味では、デベロッパーを探すにしても、大きいからではなく、先進的な知恵を持って動いていけるかで探すなど、そういったことに対して、皆さん方にもっとエネルギーを注いでいただきたいです。
皆さん方は、それぞれ市議を経験されて知恵のある方だと思いますが、最近の世の中には、若い人たち、時代の先を行く知恵を持った学者などがたくさんいます。そのような方々からより多くの知恵を頂いて、世の中を動かしていっていただきたいです。それが今日のお話を聞いて、皆さん方に望みたい最後の一言です。
議員
先ほどおっしゃっていたように、これ以上何をすればよいのかということだと思います。答えになっておらず大変申し訳ありませんが、全体的な目標として、こういうものがあるということを示させていただいたと思っていただければと思います。
議員
また、コロナ禍の中、国から地方創生臨時交付金が何度か交付されました。またそのような交付金が入ってくる予定があります。今、生活が非常に厳しい中、様々な努力をしており、これ以上何を求めるのかという御意見もありました。御意見を踏まえて、さらなる物価高騰対策と温暖化対策について、どのように見合いをつけていくのかということも考えながら、新たな財源を使って、市民目線の政策を提案していきたいと思います。
まとめ
本市もこの趣旨を踏まえ、2021年10月に「ゼロカーボンシティ旭川」を表明しました。
民生班では、「ゼロカーボンシティの実現に向けた今後の取り組みを考える〜家庭ごみ等の減量化など、小さなことからでも出来る地球温暖化対策について~」をテーマに、(1)カーボンニュートラルとは, (2)旭川市の現状, (3)家庭でできる温暖化対策の3つの課題を提案し、旭川市の温暖化対策や家庭で出来る温暖化対策といった視点で意見交換を行いました。
意見交換会では、参加者から、豊富なバイオマス資源の有効な活用方法、省エネ電化製品に対する助成、より効果の高い補助金の在り方、旭川市の新庁舎がZEB化されていない、それぞれの家庭で節約など精一杯行っている市民に対して求めることをより具体的に示してほしいなどの御意見や御提案を頂きました。
頂いた御意見等をしっかりと受け止め、今後、民生常任委員会の中で課題を整理し、ゼロカーボンシティの実現に向けた取組に生かせるよう議論を進めてまいります。

(会場の様子)