「読みもの」のページ 家具の安心
家具の「安全」ってどのようなもの。
「安全」な家具とは、どんなものでしょうか。たとえば、ふつうに使っているときに、たおれたりこわれたりしないこと、体に悪い影響(えいきょう)があるかもしれない化学物質(ぶっしつ)をおさえていること、地震(じしん)や火事などの災害(さいがい)時に危険(きけん)を大きくさせないことなどが考えられます。
「安全」という品質を管理するために
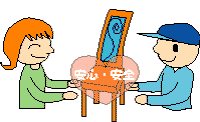
製品(せいひん)の性能(せいのう)や品質(ひんしつ)がよくわかるように、そしてそれを管理(かんり)するために、いろいろな基準(きじゅん)や規格(きかく)があります。
 これらの基準や規格のおかげで、つくる人は製品の品質がわかり、より安心な製品を送り出すことができます。
これらの基準や規格のおかげで、つくる人は製品の品質がわかり、より安心な製品を送り出すことができます。
 そして買う人は、見た目では分からない品質も分かり、製品を選ぶときの参考(さんこう)にすることができます。
そして買う人は、見た目では分からない品質も分かり、製品を選ぶときの参考(さんこう)にすることができます。
 これが、安全そして安心につながるのです。
これが、安全そして安心につながるのです。
ラベル・マーク
見た目では分からない品質も分かるようにするために、「こういう基準や規格をクリアしていますよ」ということを知らせるマークやラベルがあります。
JISマーク 日本工業規格
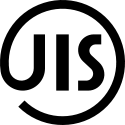
日本工業規格(JIS)では、鉱工業製品の品質を規定しています。JISマークは、鉱工業製品のなかで特に指定された約600品目について、表示されています。家具に係わりが深い品目では、MDFやパーティクルボード、接着剤などに表示されています。また、学校用の家具・オフィス用家具等に表示されているものもあります。
室内環境配慮マーク 社団法人日本家具産業振興会(旧:社団法人全国家具工業連合会)

日本家具産業振興会会員企業の自主表示。
このマークの表示されている家具は、合板、MDF、パーティクルボード及び接着剤などはF以上の材料を使い、塗料はホルムアルデヒドを含まないものを使用して製造されています。
ほかにもこのようなマークやラベルがあります。
安全な家具を作るための取り組み
工芸センターでは、JISなどの規格に基(もと)づく製品(せいひん)や材料(ざいりょう)の試験(しけん)を行っています。
また、これらの基準や規格のないものについても、製品の品質を理解(りかい)するためにはどんな方法(ほうほう)がよいのか、試験をたのみにきた会社の人と相談(そうだん)しながら、試験を行っています。
たとえば、このような試験を行っています。
製品の試験
繰返し衝撃試験(くりかえししょうげきしけん)
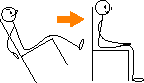
いすの座に60キログラムのおもりを固定し、後ろ脚を支点として背を後方に引張り、前脚を3センチメートル引き上げ落下させる。これを1分間に20回から30回の速度で4000回くりかえす。
強度試験(きょうどしけん)
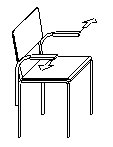
(いすのひじ・水平力の試験の場合) いすのひじを一定の力(家庭用学習いすの場合30キログラム)で、外側に水平にひっぱる。これを10秒間、10回くりかえす。
強度試験では、組み合わせたり、接着した場所、力のかかる部品の強さを主にたしかめます。
耐久性試験(たいきゅうせいしけん)
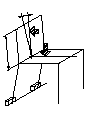
(いすの背と座を同時に行う場合)
97キログラムの力を座に加え、そのまま34キログラムの力を背に加える。背の力を外して、座の力を外す。これを1分間あたり40回を超えない速度で5万回くりかえす。
(ちょうど、いすにこしかけて、背もたれによりかかって、立ち上がるという状態を5万回くりかえすような状態です。)
材料の試験
接着強さの試験(せっちゃくつよさのしけん)

試験片を接着剤で貼りあわせて、どのくらいの力が加わった時にはがれるかを調べます。
恒温恒湿試験(こうおんこうしつしけん)
試験体を温度と湿度を調整できる装置の中に入れ、いろいろな温度や湿度の変化による状態を見ます。
木は水を吸ったり、はいたりするので、ふくらんだり縮んだりします。










