廃棄物を排出される事業者の皆さまへ
その他
家電の捨て方は?(家電リサイクル法について)
家電リサイクル法とは。
家電リサイクル法の正式名称は「特定家庭用機器再商品化法」といい、平成13年4月1日に施行された制度です。これは、一般家庭から排出された特定の家電製品(特定家庭用機器/テレビ・冷蔵庫・洗濯機・エアコン)の部品や材料をリサイクルして、廃棄物を減量し資源の有効利用を促進するための制度です。
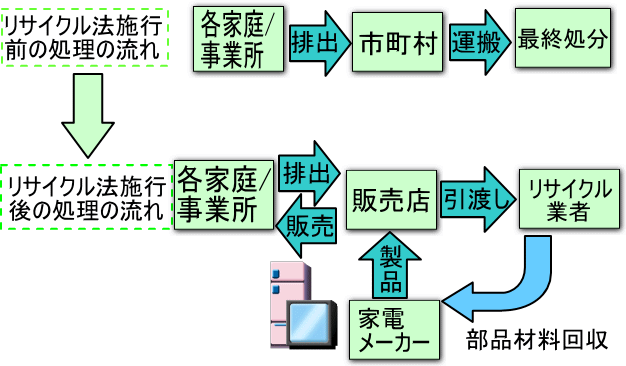
家電リサイクル法では、排出者(各家庭)、販売店、メーカーの役割が下図のように規定されています。各自がそれぞれの役割を果たすことで、円滑な資源循環を達成することができます。市町村は、廃家電の収集運搬・再商品化等を促進するため、普及啓発や情報提供に努めることとなっています。
家電リサイクル法では、(1)テレビ(ブラウン管式、液晶式、プラズマ式、有機EL式)、(2)冷蔵庫・冷凍庫、(3)洗濯機・衣類乾燥機、(4)エアコンの4品目が対象になります。具体的な家電リサイクル対象機器の処分方法については、市クリーンセンターのホームページをご覧ください。
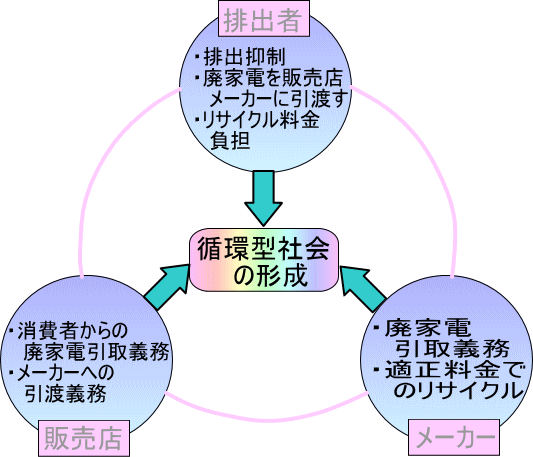
ご注意
- 対象家電(テレビ、冷蔵庫など)の処理にあたっては、上記のような家電リサイクルのながれに沿って処理する必要があります。また、対象外の家電については、一般家庭からの廃家電であれば一般廃棄物収集運搬業の、事業所等からの廃家電であれば産業廃棄物収集運搬業の許可などが必要となります。許可のない業者が、無料回収を行うことや、引取の際に料金を請求することは違法行為にあたるので、絶対に利用しないでください(リサイクルショップなどへ、使用可能な状態の物を売渡す場合を除く)。また、そのような業者を見かけた場合は、旭川市へ情報をお寄せください。
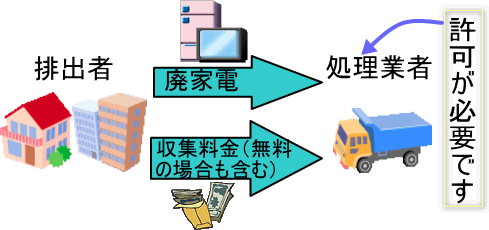
- 廃家電は、ごみとしての収集はできません。
テレビ等の廃家電は、家電リサイクル法により、排出者がリサイクル料金を負担し、リサイクルすることが義務付けられていることから、ごみステーションに出すことはできません。また、分解して捨てることもできません。
用語解説(排出者向け)
これまでに、本文で説明しきれなかった処理の委託契約の際などに用いられる基礎的な用語について説明します。
あ
圧縮(あっしゅく)
主として、廃プラスチック類、金属くず、紙くずの減容化のための処理。
あわせ産廃(あわせさんぱい)
通常、市町村では一般廃棄物のみを処理しているが、本来、排出者に処理責任がある産業廃棄物もあわせて処理事務を行っている場合をさす。現在の旭川市では行われていない。
安定型品目(あんていがたひんもく)
産業廃棄物の種類のうち、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類の5品目をさす(ただし、自動車等破砕物、鉛含有廃プリント基板、廃容器包装、鉛蓄電池電極、鉛管・板、ブラウン管テレビ側面部、廃石膏ボードを除く)。
安定型最終処分場(あんていがたさいしゅうしょぶんじょう)
産業廃棄物の種類のうち、有機物などが付着しておらず、雨水等にさらされてもほとんど変化しない安定型品目を埋立てる処分場のこと。
石綿含有産業廃棄物(いしわたがんゆうさんぎょうはいきぶつ)
石綿含有成形板や石綿含有ビニル床等が解体工事等により撤去された廃棄物をいう。繊維強化セメント板や、石綿含有スレート、同窯業系サイディング、同パーライト板などがある。非飛散性のため、廃石綿と異なり、許可を取得している安定型処分場であれば埋立可だが、運搬の際に割ったり混載したりすることはできない。
汚泥(おでい)
微細な固形物と水の混合物の総称で、排水処理施設や、各種製造業の生産工程から排出されます。無機汚泥と有機汚泥に大別される。一般的な中間処理の方法としては、脱水、乾燥、焼却、固化が挙げられる。
か
がれき類(がれきるい)
工作物の除去に伴って生じたコンクリートの破片、その他の各種の廃材の混合物を含む物。
管理型最終処分場(かんりがたさいしゅうしょぶんじょう)
産業廃棄物の種類のうち、有機物や腐敗しやすい管理型品目を埋立てる処分場のこと。安定型最終処分場よりも厳しい維持管理基準が定められている。ただし、埋立基準に適合しない有害産業廃棄物や、液状の廃油・廃酸・廃アルカリ等は埋立てられない(廃石綿は埋立可)。
管理型品目(かんりがたひんもく)
産業廃棄物の種類のうち、安定型品目以外の品目で一定の要件を満たすものをさす。具体的には、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、動物のふん尿、動物の死体、燃え殻、ばいじん、汚泥(含水率85パーセント以下のもの)、鉱さい及びこれらを処分するために処理したもの。
乾燥(かんそう)
主として汚泥の水分除去のために行われる中間処理。焼却の前段階として行われることが多い。天日乾燥や乾燥機により水分を蒸発させる。
感染性廃棄物(かんせんせいはいきぶつ)
「医療廃棄物」とも言われている。「医療機関等から生じ、人が感染し若しくは感染する恐れのある病原体が含まれ、若しくは付着している廃棄物又はそのおそれのある廃棄物」と定義され、具体的には、紙おむつ、ガーゼ、脱脂綿、輸液点滴セット、血液、注射針、臓器等のうち、医療機関等から発生するもの。判断基準は、厚生労働省のホームページなどを参照のこと。
区間運搬(くかんうんぱん)
排出者・処分業者間に、複数の収集運搬業者が区間を区切って運搬していること。この場合、区間ごとの委託契約が必要。
建設リサイクル法(けんせつりさいくるほう)
建設資材(コンクリートがら、アスファルトがら、木材)の再資源化促進のための法律。建築物の解体は延床80平方メートル以上、新築・増築は500平方メートル以上、リフォーム等は請負代金1億円以上、その他土木工事等は同500万円以上で、同法の対象となるので、事前に市(建築指導課)に届け出る必要がある。
広域処理認定制度(こういきしょりにんていせいど)
産業廃棄物の処理を広域的に行うため、地方公共団体ごとの許可を不要とする環境大臣認定制度である。対象廃棄物が限定されている。
鉱さい(こうさい)
電気炉または高炉を用いた製鉄工程で除去される不純物「スラグ」や、鋳造製品の鋳型として使われた「鋳物砂」などをいう。
コンクリートくず(こんくりいとくず)
モルタル、ブロック、コンクリート2次製品くずなど、建設工事で発生する「がれき類」に含まれない物。
さ
最終処分(さいしゅうしょぶん)
廃棄物の埋立処理のこと。最終処分場には、「安定型最終処分場」「管理型最終処分場」「遮断型最終処分場」の3形態があり、廃棄物の種類により、埋め立てられる最終処分場が異なる。
再委託(さいいたく)
処理受託者が、第三者に処理を委託すること。再委託は責任があいまいになるため、原則として禁止されている。ただし、産業廃棄物については法令で定める基準を満たした場合は、一度限り再委託が可能となる。
再生処理・再生利用(さいせいしょり・さいせいりよう)
中間処理を経て、廃棄物の減量化や安定化を達し、物質回収やエネルギー回収などを図ること。旭川市内においては、がれき類を破砕処理し、砂利等の路盤材に再生すること、木くずを破砕処理しチップ燃料や敷きわらにすること、廃プラスチック類を圧縮や溶融し、固形燃料とする例などがある。
自動車リサイクル法(じどうしゃりさいくるほう)
使用済み自動車に係る廃棄物の減量と再生資源化の促進を目的とした法律。トラックやバス等も含むほぼ全ての自動車を対象としている。リサイクルにあたっては、道や政令市に登録・許可された「引取業者」「フロン類回収業者」「解体業者」「破砕業者」に引渡す必要がある(廃棄物処理とは別のながれになる)。
処分(しょぶん)
廃棄物処理のうち、収集運搬を除く行為で、中間処理と最終処分がある。「処分業」は、廃棄物の処分を営む人、法人。
収集運搬(しゅうしゅううんぱん)
「収集」は廃棄物を取り集め、運搬できる状態に置くこと、「運搬」は廃棄物を排出場所や積替保管場所等から別の積替保管場所や処理施設へ移動させることをいい、積替えを行うことを含む。
収集運搬業(しゅうしゅううんぱんぎょう)
「収集運搬業」は、処理業のうち、収集運搬を営む人、法人をさす。
処理(しょり)
広義では、廃棄物の「排出抑制」「分別」「保管」「収集運搬」「再生」「中間処理」「最終処分」をさす。本稿での処理は、「収集運搬」「中間処理」「最終処分」をいう。「処理業」は、廃棄物の処理を営む人、法人のことで、収集運搬業と処分業の総称。
処理施設(しょりしせつ)
処分(中間処理及び最終処分)の用に供する施設。脱水、破砕、圧縮、焼却、乾燥、最終処分(埋立)などがあり、その種類は政令で定められている。一定規模以上の処理施設は道や政令市の許可が必要となる。
た、な
タールピッチ類(たあるぴっちるい)
タールピッチ(コールタール等)のほか、アスファルトルーフィング、ワックス、ろう、パラフィン等をさす。硫酸ピッチとは別個の物。
脱水(だっすい)
汚泥の水分除去を目的とした中間処理。水分を含んだままの汚泥は、焼却や乾燥が非効率となるため、その前段階として行われることが多い。
中間処理(ちゅうかんしょり)
廃棄物を物理的、物理化学的及び生物学的手法により、廃棄物の減量・減容化、安定化、安全化、無害化が達成させる処理をいう。具体的には、破砕、圧縮、焼却、乾燥、固化、脱水、濃縮、中和などの手法がある。
帳簿(ちょうぼ)
廃棄物の種類ごとに、運搬年月日や量、運搬先を記載する書類。処理業者等に備え付けが義務付けられている。
積替保管(つみかえほかん)
排出事業者から処分業者へ収集運搬する過程で、一旦、ある特定の場所に廃棄物を集積し、一定量が貯まると中間処理業者又は最終処分業者へ運搬する行為を言い、その場所を積替保管場所という。
(特定)有害産業廃棄物((とくてい)ゆうがいさんぎょうはいきぶつ)
特別管理産業廃棄物のうち、廃PCB、PCB汚染物、PCB処理物、廃石綿等、有害金属等を含む産業廃棄物をいう。有害金属等を含むか否かは、「判定基準省令」による。具体的には、水銀、カドミウム、鉛、六価クロムなど。
熱回収施設(ねつかいしゅうしせつ)
焼却施設等のうち、法令で定められた基準をクリアし、熱回収の機能を有すると許可権者から認定された施設。現時点で、旭川市では、熱回収施設はない。
は
廃アルカリ(はいあるかり)
アルカリ性の廃液。廃ソーダ液や写真現像廃液なども含まれる。沈殿物で、pH5.8以上、8.6以下に調整したものは汚泥となる(廃酸も同じ)。
廃酸(はいさん)
酸性の廃液。無機廃酸、有機廃酸のほか、アルコール発酵廃液や染色廃液、写真漂白廃液、炭酸飲料水、ビールなども含まれる。
ばいじん
ボイラーや廃棄物焼却施設において発生し、集じん設備で捕集されたもの。燃焼焼却で発生するスス。
破砕処理(はさいしょり)
廃プラスチック類やがれき類、木くずなどを細かく砕く処理。破砕後の廃棄物は再生利用されることもある。
分離・選別処理(ぶんり・せんべつしょり)
廃棄物の各組成(アルミ缶と鉄缶、がれきと小石など)をその物理的特性に応じて機械的に分離、選別する中間処理。風力選別や、ふるい、トロンメル、磁力選別などがある。
ま
無害化処理認定制度(むがいかしょりにんていせいど)
石綿を含む廃棄物・微量PCB廃棄物の無害化処理について、環境大臣の認定により処理業・処理施設の許可が不要となる制度。
無機汚泥(むきおでい)
汚泥のうち、建設現場、浄水場、金属メッキ等の排水処理等から発生する無機性の汚泥。 建設工事の掘削に伴って生じる汚泥は、特に建設汚泥とよばれる。
燃え殻(もえがら)
電気事業等の活動に伴い生じる石炭がら、灰かすや炉清掃掃出物等。
や
優良処理業者(ゆうりょうしょりぎょうしゃ)
処理業者のうち、優れた能力及び実績(経理的に安定しているか、情報公開を行っているか、ISOなどを取得しているか、電子マニフェストが利用できるか等)を有すると許可権者から認められた処理業者。優良処理業者は、許可証に「優良」のマークが示され、許可有効期間が5年から、7年に延長される。
輸出廃棄物確認制(ゆしゅつはいきぶつかくにんせい)
産業廃棄物を輸出する場合、環境大臣の確認を受けなければならない制度。
輸入廃棄物許可制(ゆにゅうはいきぶつきょかせい)
廃棄物を輸入する場合、環境大臣の許可を受けなければならない制度。
油水分離(ゆすいぶんり)
廃油は一般的に焼却又は再生利用されるが、その前段階として行われる油分と水分の分離処理方法。主として、食品工場や自動車整備工場、機械加工場などで用いられる。
溶融(ようゆう)
電気等により廃棄物を溶解する処理。旭川市内では、主として廃プラスチック類の減容のために中間処理として行われている。
ら
硫酸ピッチ(りゅうさんぴっち)
廃硫酸と廃炭化水素油との混合物であって、著しい腐食性を有する物。石油精製過程の副産物として産生され、人体や生活環境に有害であり、指定有害廃棄物に指定されている。廃棄物の種類としては、「廃油」と「廃酸」の混合物。
ABC
PCB(ぴいしいびい)
「ポリ塩化ビフェニル」の略。特別管理廃棄物。毒性のある化学物質であるが、絶縁性、安定性等に優れているため、昭和47年に製造中止されるまで、コンデンサやトランス(電気機器)などに多数使用されてきた。PCB含有廃棄物を保管している場合、「PCB特別措置法」に基づく届出等が必要である。
WDS(だぶりゅうでぃえす)
廃棄物処理に必要な情報提供を目的とする、物理的・化学的性質等を記入したシート。排出者は、契約時にはWDS等により情報提供しなければならない。
MSDS(えむえすでぃえす)
化学物質等安全データシート。事業者が製品等を出荷する際、相手方にその製品の化学的性質や取扱いに関する情報をMSDSとして提供することが義務付けられている。
お問い合わせ先
旭川市環境部環境指導課廃棄物指導係
〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎5階
電話番号: 0166-25-6369 |
ファクス番号: 0166-26-7654 |
メールフォーム
受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)










