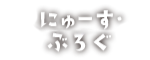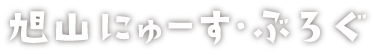- すべて |
- しいくにゅーす |
- お知らせ |
- しいくのぶろぐ |
- 園長(ゲンちゃん)日記 |
- 図書館ぶろぐ
2019年12月のすべての記事
2019年12月31日 | しいくのぶろぐ
今年もありがとうございました!
今年もありがとうございました!
朝起きると雨、雪も極端に少なくもうあと数日で雪解けかと思うような景色でした。昼からは吹雪、こんな大晦日もあるのかと外を眺めています。
今年、動物園界で一番多く話題に上った言葉は「福祉」だったと思います。
身の安全と食べることを保証した環境下での飼育下野生動物の福祉、飼育面積もさることながらとても考えさせられることが多い、議論のつきない言葉です。
目の前にいる個体の福祉が注目されがちなのですが、もう一つとても大切なのが種の福祉なのではないでしょうか。命は生まれて死ぬから命です。だから命を繋ぎます。世界中の動物園が協力して現在飼育している個体群で健全な種を未来に繋いでいくこと、遺伝的な管理も含めとても緻密で、時に大胆な決断も必要かもしれません。
動物園は自然を知る玄関口。個の福祉と種の福祉、そのバランスをどのように取っていくのか?宿題が大きく膨らみ今年が終わります。
みなさま、今年一年ありがとうございました。よいお年を迎えてください。
2019年12月25日 | お知らせ
2020年1月の壁紙カレンダーができました
2020年1月の壁紙カレンダーができました

1月の壁紙カレンダーの動物はモルモットです。
1月の壁紙カレンダーの動物はモルモットです。
令和2年、今年は子(ねずみ)年ということで、子ども牧場で飼育しているネズミの仲間であるモルモット。
本園で飼育しているネズミの仲間はアフリカタテガミヤマアラシ(小獣舎、冬期は見られません)、エゾモモンガ(北海道小動物コーナー)、エゾリス(北海道産動物舎)、カピバラ(かぴばら館)など。
それぞれ体型や生態に違いがありますが、じっくりみてみるとネズミの仲間である共通点が見つかるでしょう。
園内を周って観察してみてください。
なお、こども牧場ではモルモット、カイウサギと実際にふれあえる“ふれあいの時間”があります。
大人の方も参加できますので、ぜひお立ち寄りください。
ふれあいの時間(冬期)
カイウサギ 13時20分から13時45分まで
モルモット 14時00分から14時25分まで
※動物の体調等により急遽中止となる場合があります。
WEBカレンダーのダウンロードはこちら
お使いのパソコンのモニターのサイズ(ピクセル)を選んでクリックしてください。

 カレンダー2001_1280x1024(画像形式(JPG) 715キロバイト)
カレンダー2001_1280x1024(画像形式(JPG) 715キロバイト)

 カレンダー2001_1366x768(画像形式(JPG) 614キロバイト)
カレンダー2001_1366x768(画像形式(JPG) 614キロバイト)

 カレンダー2001_1920x1080(画像形式(JPG) 1,090キロバイト)
カレンダー2001_1920x1080(画像形式(JPG) 1,090キロバイト)

 カレンダー2001_1920x1200(画像形式(JPG) 1,171キロバイト)
カレンダー2001_1920x1200(画像形式(JPG) 1,171キロバイト)

 カレンダー2001_2560x1440(画像形式(JPG) 1,818キロバイト)
カレンダー2001_2560x1440(画像形式(JPG) 1,818キロバイト)

 壁紙2001_iphone(画像形式(JPG) 602キロバイト)
壁紙2001_iphone(画像形式(JPG) 602キロバイト)
過去の壁紙カレンダー
2019年12月23日 | 園長(ゲンちゃん)日記
ゲンちゃん日記・令和元年12月「来年はねずみ年、自らの生命力を高める年にしましょう」
ゲンちゃん日記・令和元年12月「来年はねずみ年、自らの生命力を高める年にしましょう」
(写真:さる山)
今年は初雪が遅いなと思っていたら、いきなりドカッときました。今年は冬季に向かい動物舎の工事が続きます。そのほとんどが屋外工事ですから雪は少なく寒さは緩い方が作業もしやすくていいのですが天候はこちらの都合に合わせてはくれませんね。園路や駐車場の除雪も慌ただしく始めました。駐車場は車で来園される方が一番先に利用する場所になるので開園前には除雪を終わらせなければいけません。冬期開園期間中は西門前付近の駐車場も無料で利用していただけますが、これは地主さんのご厚意により駐車場を無償で貸していただいているからです。冬期開園期間中も多くの来園者を迎えるようになったのでとてもありがたいことです。
話は変わりますが園内で暮らしている動物で一番数が多い動物は何でしょう?実はおそらくドブネズミとクマネズミです。動物園に限らず人が生活している場所にはほぼ間違いなくいる動物です。夏場は日暮れ時になると園内を走る姿を見ることがあります。テナガザルやレッサーパンダのモート(堀)の中に落ちていることもあります。日中はほぼ気配を感じることはないのですがありとあらゆる生きる可能性を探っているのが彼らです。
クマネズミは足がかりがある木の壁や柱ならば駆け上ります。ドブネズミは排水管の中を走り回ります。不用意に開けられた窓、目皿を外された排水口など建物に侵入できる隙を見逃してはくれません。昔の獣舎は土間の寝室が多かったのですが、なんと園路側の舗装の隙間からトンネルを掘り寝室内まで掘り進み侵入してくることもありました。
積雪が進むと彼らは雪の中にトンネルを張り巡らせて移動します。隙あらば食べ物のある獣舎内に侵入を図ります。昨シーズンは数カ所で侵入されました。ニホンザルの寝室では暖房機の配線が何度かやられました。ニホンザルが寝室に出入りする扉(シュート)は夜間解放しているのでそこから侵入したと思われました。しかしネズミが生活している糞などの痕跡が見当たりません。なんとネズミはニホンザルの放飼場の根雪の中に居を構え夜な夜な寝室内に侵入していたのです。担当者が雪割り作業をしていたらまだ目も開いていないほど小さな子ネズミがたくさん見つかりました。そういえば昔マイナス20度に保たれた真っ暗な冷凍庫の中の大きな霜の中に巣穴を掘りクマネズミが繁殖していたことがありました。
ドブネズミ、クマネズミは時に小動物も捕食します。動物園にとっては害獣です。でもその生命力には時に頭が下がります。来年はねずみ年。気候変動が騒がれていますが私たちも自らの生命力、適応力を高める年にしなければいけないかもしれませんね。
旭山動物園 園長 坂東 元
「野菜の時間」
今この部屋には46匹のモルモットが暮らしています。
いつもは隠れ家の中に隠れていることが多いですが、1日の中で1番活発に動く時間が、野菜をあげる時です。扉のカギを開ける音やタッパーと野菜がぶつかり合う音に反応して、一斉に動き出します。
ピーマン、サツマイモ、チンゲンサイ、コマツナを毎日あげていますが、ほとんどのモルモットが、ピーマンから食べ始めます。
不定期ではありますが、モルモットのもぐもぐタイムがあれば、野菜を食べる姿を見ることができます。
こども牧場の室内には他にもカイウサギとイヌがいるので、ぜひ遊びに来てください。お待ちしております。
こども牧場担当:安田恵里
2019年12月19日 | しいくのぶろぐ
『たぬき・タヌキ・TANUKI』
『たぬき・タヌキ・TANUKI』
もうすぐ2019年も終わりですね。
みなさんにとって、今年はどんな1年でしたか?
私にとって2019年は「たぬき」な1年でした!
2018年の年末に公式twitterに投稿した「ただただ雪に吹かれるタヌキ」がバズった(このとき「バズる」という言葉を知りました…)のを始まりに、タヌキ関連のいろんなことがあった1年でした。
まず、春の閉園期間中にゆっくりロードにエゾタヌキ舎が完成し、自然に近い環境で暮らすエゾタヌキを見ていただけるようになりました。
(エゾタヌキ舎にて)
4月後半には新たな個体が仲間入りしました。この個体(「たぬきち(オス)」といいます)は左後脚がありません。交通事故に遭ったところを保護され、旭川市内の動物病院で手術を受け、動物園に来園しました。
残念ながら北海道では「生きているタヌキ」よりも「交通事故に遭って亡くなっているタヌキ」を見たことがある方のほうが多いのではないでしょうか。
たぬきちは野生出身ということもあり警戒心が強いですが、同居している「やえ(メス)」とは仲が良く、ふだんの生活では左後脚がないことでの支障はなさそうです。
(やえとたぬきち)
海外からのお客様にもタヌキは人気です。不思議なことに英名の「racoondog」よりも「TANUKI」のほうが伝わることが多いようです。
おびひろ動物園さんのtwitterでエゾタヌキが話題になったことも今年嬉しいことのひとつです。実は飼育されている2頭のうちの1頭(メスの「あん」)は旭山生まれの個体です。
他園に行った個体が人気者になり、元気な姿が見られるのは嬉しいことです。
そして、以前よりも「タヌキ好きなんです」と言ってくださる方も増えました!
タヌキ好きさんたちのおかげでtwitterやinstagramで検索するとたくさんタヌキが出てきて、見ているとあっという間に時間が…。
地元に普通にいて(なかなか出会えないですが)、取り立てて何かすごい動きをすることもない動物ですが、こうしてたくさんの方に見ていただいて、彼らの魅力が広まっていくことがとても嬉しいです!
もちろん、2020年も引き続き推して行きます!!
ちなみに、冬のほうがモフモフでタヌキの魅力が増し増しです。
(冬毛のタヌキ)
ときどきtwitterやinstagram(どちらも@asahiyamazoo1)でエゾタヌキも投稿しているのでそちらもチェックしてくださいね!
最後にとっておきの一枚を。
(なかなかいい顔が撮れました)
(北海道産動物舎・サル舎担当:佐藤 和加子)
2019年12月18日 | しいくにゅーす
エゾモモンガの展示を再開しました
2019年12月16日 | 図書館ぶろぐ
「旭山動物園だより」&「あさひやまどうぶつえんみにだより」最新号を発行しました!
「旭山動物園だより」&「あさひやまどうぶつえんみにだより」最新号を発行しました!
雪が降ったかと思えば、気温が上がり雪がとけたり雨が降ったり…。
雪かきや防寒対策は大変ですが、この冬の気象は何だか変ですね。
先日、雪の積もった朝、ホッキョクグマが雪と戯れていました。
気持ちよさそうでしたし、楽しそうに見えました。
本来は寒い地域で生きている動物たちは、冬、本当に生き生きとして見えます。
人間は防寒対策をして、動物園に遊びにきてくださいね。
さて、先日、新しい「動物園だより」と「どうぶつえんみにだより」を発行しました。
「動物園だより」では、「初めての冬を迎える動物」として、
夏に生まれたユキヒョウの子どもとキングペンギンのヒナの様子と、
イベントホールにオープンした「旭山動物園号ひろば」を紹介しています。
「みにだより」では、「しろいどうぶつ」を紹介しています。
白く見えるけど、本当は白くない動物もいるんです!
ぜひ動物観察の参考にしてみてくださいね!
投稿者:動物図書館 北川裕美子
旭山動物園だより263号
内容: 初めての冬を迎えるユキヒョウの子どもとキングペンギンのヒナ ほか
「旭山動物園だより」はこちらからダウンロードできます(新しいウインドウが開きます)
あさひやまどうぶつえんみにだより96号
内容:しろいどうぶつ
「あさひやどうぶつえんみにだより」はこちらのページからダウンロードできます。(新しいウインドウが開きます)
2019年12月11日 | しいくにゅーす
アムールヒョウの「ルナ(メス)」が移動します
2019年12月8日 | 図書館ぶろぐ
12月14日(土曜日)午前11時30分から動物図書館で「絵本の読み聞かせ」があります。
12月14日(土曜日)の11:30から
動物図書館で絵本の読み聞かせがあります
12月になりました。
先日、キングペンギンのヒナの様子を観察しに「ぺんぎん館」に行ったのですが、
イワトビペンギンならではの行動が観察できました!

両足を揃えて、ピョンピョン跳んで岩の上を移動していました。
もちろん、頂上まで行くために、一歩一歩(?)跳ねながら登っていきます。

ペンギンの散歩も楽しみですが、4種類いるペンギンのそれぞれを観察してみると、
それぞれの能力に気づけますよ!
さて、動物図書館から本の読み聞かせのお知らせです。
12月14日・土曜日の11時30分から絵本の読み聞かせがあります。
冬期は11時30分からとなります。

今月は、チンパンジーの研究者で動物行動学者のジェーン・グドールさんの
小さい頃の出来事や思いを描いた「どうぶつがすき」という本と、
いろんな動物の「鼻」が原寸で登場する「このはな だれの?」という本を読みます。
もちろん、絵本の読み聞かせのあとには、子どもにも大人にも人気の、
飼育スタッフによる「絵本に出てきた動物の解説」があります。
飼育スタッフならではの、詳しく、興味がわく解説を聞くことができますよ。お楽しみに。

2019年度 冬期の読み聞かせスケジュールのダウンロードはこちら
(投稿者 動物図書館 北川裕美子)
2019年12月7日 | しいくのぶろぐ
【ユキヒョウ愛称集計中】
【ユキヒョウ愛称集計中】
11月23日~12月1日まで、ユキヒョウの子の愛称(名前)を募集しました。
みなさんたくさんのご応募ありがとうございました!ただいま鋭意選考中です。
子は放飼場のオーバーハングにも登れるようになりました。
さてどんな愛称になるでしょうね??
開票・集計作業は大変でもありますが、みなさんが書いてくれた投票用紙を読むのは飼育係のひそかな楽しみでもあります。
お子さんが考えてくれたほほえましい愛称や、凝った愛称。思わず笑ってしまう愛称(まじめに考えてくれたとしたらスミマセンね)などなど・・・。
そんなみなさんの投稿の一部を、こっそりご紹介しちゃいましょう!
「美雪」
なるほど~。美雪、雪子、ユキ、スノウなど、ユキヒョウの「雪」を使った案はけっこう多かったですね。
「れいちゃん」
新元号にちなんだ案も多くありました。メスだから合うかもね!
ただ動物園業界では、今年生まれの動物に「レイ」とか「レイワ」と名付けられる率がめっちゃ高いようです(笑)。
「マヤ」
ヤマトとジーマから文字をもらって、という案もありました。「ヤジマ」なんてのもありましたが(笑)、もはや苗字になっちゃってますかね。
「リープ」
ドイツ語、アイヌ語などにちなんだ愛称も多くいただきました。2016年に生まれた「リヒト」もドイツ語由来でしたね。ジーマはスラヴ語。さて今年生まれのユキヒョウは何語になるでしょうか?
「アサユキ」
「アナと雪の女王」にちなんだ愛称もいただきました。
「アサユキ」ですか(笑)。なかなか盛り込んできましたね。
「トマト」「いちご」「メロン」。
おいしそうな名前ですね~!。お子さんたちが頑張って考えてくれた愛称です。
ご家庭で飼ってるネコの名前だったら採用間違いなしでしょう。
みんな野菜も果物も大好きなんですね。ビタミン豊富で身体にもいいですからね!
「ユキノビジン」
壮年男性のアイディアです。ちょっと長いような(笑)
おそらくですけど、この方きっと競馬好きなのではないでしょうか。
「大外からユキノビジンきた、ユキノビジンきた」みたいな・・・
個人的に一番印象に残った投稿はコチラ!↓↓
「キャーちゃん」
「フハフハしているから」との理由でしたが、われわれ汚れた大人には理解できないセンスを感じました。投稿者の子には、このセンスを持ったまま成長していただきたいものです。
以上、投票の一部をご紹介させていただきました。
飼育係の楽しみである開票作業をみなさんにも共感していただきたくて記事を書きました。
思わずいろんな想像をしながら開票作業に没頭してしまいます。決して投票者のあげ足を取る気持ちはありませんので、ほほえましく読んでいただけたら幸いです。
はたして当選の愛称は今回ご紹介した中にあるのか、それとも別のアイディアになるのか??
当選発表をお楽しみに!
(もうじゅう館・フクロウ担当:大西 敏文)
2019年12月7日 | しいくにゅーす
アビシニアコロブス「カトリーナ(メス)」の死亡について
2019年12月6日 | お知らせ
旭山動物園ラッピングバスが運行開始となりました。
2019年12月3日 | しいくのぶろぐ
【冬のくもざる・かぴばら館】
【冬のくもざる・かぴばら館】
冬、特に雪が積もるくらいの気温になると、クモザルとカピバラは屋外での展示ができなくなります。野生の彼らは中南米の暖かい地域に生息している動物で、寒さが苦手です。
そのため、次の春が来るまで暖房のきいた屋内での生活となり、やはり多少は窮屈な思いをさせてしまうのは心苦しいところです。
さて、そんな冬のくもざる・かぴばら館ですが、屋内観察ならではの良いところもあります。それは「近さ」。
屋外でダイナミックに動くクモザルやスイスイ泳ぐカピバラは見応えがありますが、観察するにはちょっと遠いですよね。その点屋内ではガラス越しではありますが、目と鼻の先くらいの近さで彼らを観察できることも多いです。屋外では細かく見ることが出来ない彼らの体つきや毛並み、エサの食べ方や筋肉の動き方、息づかいなど、近いからこその観察ポイントもたくさんあります。
じっくり彼らの体や動きを観察すると色々な疑問がわいてくると思います。クモザルとカピバラに限りませんが、興味が出たら、展示してあるパネルを見てみたり、飼育員が近くにいたら色々質問してみたり、自分でしらべてみたりしてください。小学生のお子さんならそれらをまとめて冬休みの自由研究にも使えそうですね。
冬のくもざる・かぴばら館のポイントとして近さをアピールしてみましたが、近いのは動物たちにとっても同じです。ガラスの向こうで人間が急な動きをしたら驚きますし、ガラスを叩かれたら怖かったり、不快に感じたりもします。そういったことは無いよう、優しい気持ちでの観察をお願いします。
(くもざる・かぴばら館・あざらし館担当:中野 奈央也)
2019年12月1日 | しいくのぶろぐ
冬のニワトリとアヒル
冬のニワトリとアヒル
4月にオープンしたニワトリ・アヒル舎。冬もその場所で引き続きご覧いただけます。
夏は外の展示でしたが、冬は室内の展示でガラス越しですが、動物を観察することできます。
でも、日差しがある時や気温が高い時は外にも出して、気分転換をしています。
ニワトリたちは砂浴びがとても好きで、外に出た瞬間から砂浴びをしています。室内では、高い所に止まれる木を組むとそこが落ち着くようで、そこで休む姿が見られます。その上、夜は全羽木の上で寝ています。
アヒルたちは、外のプールが使えないので、小さいですが簡易的なプールを設置しています。所狭しとみんなで水浴びをし、体をキレイにしています。
これから雪が降り積もるとどのような行動を見せてくれるのでしょうか?とても楽しみな施設です!ぜひ、みなさんも足を運んでもらえればと思います。
(こども牧場・教育活動担当:佐賀真一)